
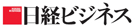
三菱電機は2025年4月、「カルチャー変革室」を立ち上げた。組織風土改革に取り組む専門部署だ。これまで様々な拠点で実施してきた改革の取り組みを引き継ぎ、部署間の連携強化や全社的な研修メニューの策定などに取り組む。組織風土の改革を掲げる企業は多いが、専門部署まで立ち上げる事例は珍しい。なぜ同社はそこまで組織風土を重視するのか。
発端は21年6月に発覚した、鉄道車両向けの空調装置における品質不正だった。当時の杉山武史社長が引責辞任し、その後累計で197件の品質不正が明らかになった。
元凶は組織風土にあると同社は見た。上意下達で上司の意見に逆らえない雰囲気が強かった。組織の風通しは悪く、現場社員の意見はリーダー層に届きづらい。縦割り意識が定着し、組織には内向きの力学が働いていた。加えて、同社ではパワーハラスメントを主因とする労務問題が頻発した過去もある。「三菱電機は風土改革を示し続ける宿命を背負っている」。阿部恵成最高人事責任者(CHRO)はこう話す。
社長直下の「全社変革プロジェクト」
21年7月に社長に就いた漆間啓社長は「組織風土改革こそ一丁目一番地」だと表明。自ら手を挙げた若手・中堅社員45人を中心とする社長直下の「全社変革プロジェクト」を同年10月に立ち上げた。
以来、様々な取り組みに着手してきた。20年ぶりに人事制度を刷新し、成果だけでなく、行動も重視する評価体系に変えた。それまで実施されてこなかった上司と部下との1対1のミーティングも定着させた。
施策は多岐にわたる。たとえば同社では長年、メールの送り先の宛名に「殿」と付ける文化が定着していた。これを「さん」に変えることで社員間の距離感を縮めた。制度刷新から「さん付け」文化の定着まで、あらゆる側面で手を打つことで、漆間社長は組織の在り方を変えようと動いた。
漆間社長自身も製作所などを巡回し、組織風土改革をテーマとした講演を実施してきた。講演回数はオンライン開催も含めて累計で140回を超える。製作所の在り方に大きな影響を与える所長の人選にもこだわった。「一度に半数以上の製作所の所長を入れ替えるなど、漆間社長は自ら改革の先頭に立って意思表示を示してきた。経営者のコミットメントが風土改革の肝だ」。SMBC日興証券の吉積和孝シニアアナリストはこう評価する。
男性多数の製作所で女性目線の職場改革
社長のコミットメントは会社を動かした。風土改革の動きが本社だけでなく、地方の製作所にも波及したのだ。
たとえば名古屋市にある名古屋製作所。主力事業であるファクトリーオートメーション(FA)システム事業を展開している。約3500人が所属する、同社でも有数の大規模拠点だ。
ここでは22年9月から、女性社員が働きやすい職場環境を整える「スマイリー活動」が始まった。発起人は総務部の田村香織さんとサーボモータ製造部の佐藤佳恵さんの2人。男性社員が多い環境の中、女性社員の働きづらさを以前から感じていた2人は、全社的な風土改革の波を後押しに、女性視点のアイデアで職場環境の改善を図った。
たとえば、アルミ製の工業部品を使用して「靴取り名人」と呼ばれる、妊婦の社員がかがまなくても靴を拾える器具を開発し、拠点内の各所に設置した。また、男性社員に妊婦疑似体験の教材を装着して8時間勤務してもらうというキャンペーンも実施し、その苦労への理解を促した。

田村さんと佐藤さんの2人から始まった取り組みは製作所全体に広がり、中心メンバーは6人に増えた。さらに社内報などを通じて改革の動きは他の製作所にも浸透していった。ちなみに「靴取り名人」は特許を出願中で商品化も検討しているという。「一社員の意見を吸い上げてくれる会社の風土が整ってきたように感じる。自分たちのアイデアによって、他の職場にも良い影響を広めたい」(田村さん)
風土改革を恒久化せよ
冒頭の「カルチャー変革室」の話に戻ろう。漆間社長の「全社変革プロジェクト」は3年半で全社的な運動に発展した。それにもかかわらず、わざわざ変革室を立ち上げたのは、運動を恒久的な取り組みとする狙いがある。
品質不正問題やデータの改ざん問題などといった不祥事が発生すると、多くの企業が再発防止に向けたプロジェクトを立ち上げる。ただ、その危機意識は一時的なものに終わってしまうことも少なくない。結果、不祥事が再発してしまう。その轍(てつ)を踏まぬよう、三菱電機は専門部署の立ち上げにより改革の歩みを続けようと手を打った。
「トップダウンとボトムアップの2軸で進めてきたプロジェクトだからこそ、全社的に浸透するようになった。だが変革に終わりはない。これを企業文化として恒久的なものにしなければならない」。カルチャー変革室を統括する小黒誠司・上席執行役員は力を込めてこう話す。

カルチャー変革室を創設したことにより、各拠点で生まれた取り組みは継続しやすくなる。海外を含めた全社で啓蒙を続けるハードルも下がるだろう。既にカルチャー変革室と各事業本部や製作所の変革プロジェクトメンバー250人が議論や事例共有などを行うミーティングを定期的に実施している。
漆間社長のリーダーシップのもとで組織変革の動きは3年半続いた。ただし、その真価が問われるのはこれからだ。トップの手を離れてもなお、常設部署を中心に風土改革を「自走」させられるか。これが実現して初めて、不祥事を発生させない組織が見えてくる。
(日経ビジネス 浜野航)
[日経ビジネス電子版 2025年10月10日の記事を再構成]

|
日経ビジネス電子版
週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。



