
冬の出勤風景のイメージ(NEWSWEEK JAPAN VIA Google Nano Banana Pro)
<首元にタートルの厚みがない。肩に編み地のふくらみがない。寒いのに服が重くない──。街から消えたセーターを数字と現場の声で追う>
数年に1度の寒波が日本列島を覆っている。朝の空気が、それを実感させる。駅へ向かう道すがら、吐く息が白くなり、指先がかじかむ。冬将軍が戻ってくると、自然に着るものを"足す"ことを考える。もう一枚、何かを──。
それなのにホームや車内で周囲を見回して、ふと気づく。昔ならこのタイミングで増えていたはずの"セーター姿"が、思ったほど目に入らない。首元にタートルの厚みがない。肩に編み地のふくらみがない。代わりに見えるのは、薄手のカットソーの上にフリース、あるいはダウンの下に機能性インナーを仕込んだ軽いレイヤリングだ。寒いのに、服が重くない。
冬の暖かさは、いつから"外側"ではなく"内側"でつくるものになったのだろう。
セーターの国内生産は4年で約48%減
「セーターが減った」と言うと、どうしても印象としての話になりやすい。だが変化は数字にも出ている。
経済産業省の「生産動態統計年報(繊維・生活用品統計編)」で、ニット製外衣の内訳にある「Sweaters, cardigans and vests(セーター・カーデガン・ベスト類)」を見ると、国内生産は2016年の 3,844,879点 から、2020年は 2,010,855点 へ。4年で 約48%減となっている。
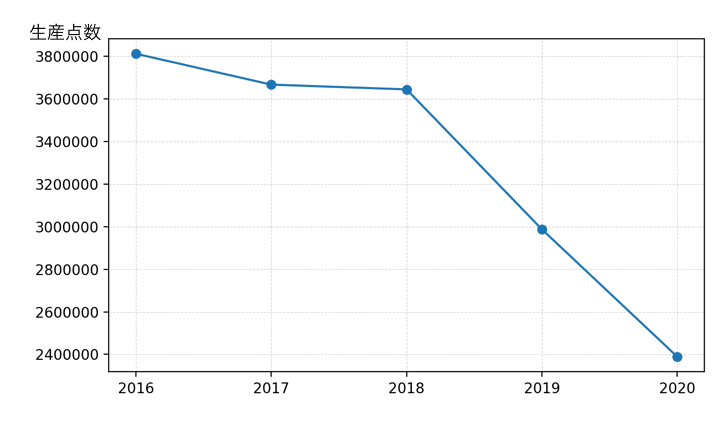
この統計は"国内工場で実際に製造された数量"を集計したもので、輸入品や海外生産への置き換え、在庫の動きまでをそのまま映すものではない。ただそれを考慮しても、冬服のボリュームゾーンが動いていることは読み取れる。では、その"空いた席"に座ったのは何か。

先に冬を変えたのは、「フリース」だった
「インナー革命」を考えると、つい機能性肌着をイメージしがちだ。けれど、日常の冬服を先に書き換えたのは、肌着よりもフリースだったのではないか。
フリースは、セーターが苦手だったことを、ほぼ全部うまくやってのける。軽い。乾きやすい。縮みにくい。洗濯機で洗える。毛玉はできるが少ない。こうした "扱いやすい"という一点で、セーターの優位を奪っていった。暖かさの総量を競うだけなら、セーターが勝てる日もあるだろう。だが日常の生活は、暖かさだけで回っていない。手間、時間、洗濯、取り回し。そういう小さな現実が、冬の定番を決めてしまう。
そして「フリースが冬の定番」になったとき、セーターは"なくても困らない服"に一歩近づいた。
暖かさは「肌」から──吸湿発熱インナーの登場
2000年代、暖かさの主戦場はさらに内側へ移る。セーターやコートで"空気を溜める"のではなく、肌側の一枚で体温の土台をつくる。吸湿発熱のインナー群が、生活の標準装備として浸透していった。
吸湿発熱の発想自体は、ユニクロ以前から芽が出ていた。スポーツやアウトドアの世界では、汗と冷えの問題が切実だからだ。体を動かすほど汗をかき、止まった瞬間に冷える。その落差を埋めるため、肌着の機能が磨かれていく。ミズノの「ブレスサーモ」が、90年代後半からアウトドア用アンダーウエアとして展開されてきたことは象徴的だ。
ただし「技術がある」ことと「街の標準装備になる」ことの間には距離がある。ここで強いのが、大量供給の力だ。機能が"わかりやすい言葉"になり、買い足せる価格になり、毎年同じように店頭に並び、家の洗濯機で回せる。ユニクロは「ヒートテック」でこれを実現。こうして吸湿発熱は、特別な装備ではなく「冬の肌着の常識」になっていった。
結果として、セーターは"暖かさの責任"を少しずつ降ろしていく。インナーで暖を取れるなら、外側は別の役割を担えるからだ。
「二季化」と「ストリート化」
もうひとつ、セーターの居場所を狭めた要因がある。季節の感覚と、街の服装だ。
温暖化の影響で暑い時期が長く、寒い時期が短くなれば、「セーターがちょうどいい」期間は少なくなる。しかも今のファッションはストリート寄りだ。ルーズなトップス、スウェット、ダウン。これだけで冬のカジュアルファッションが成立する。気がつけばセーターを"中に着込む"必要はなくなっていた。
インナーで土台をつくり、ミドルはフリースやスウェットで回し、最後にアウターで風を防ぐ。冬のスタイルがこの形へ寄れば寄るほど、セーターは「必需品」から外れていった。
業界のベテランが語る"アパレルの本音"
「セーターは明らかに減っています。ニットの売り上げそのものがかなりダウンしていて、アパレルメーカーも買い付けが減りました」
こう語るのは欧州系グローバルブランドの元商品担当(MD)Yさん。ニットの売上が減った理由としてYさんが真っ先に挙げたのは機能性インナーではなく、フリースだった。
「絶対的にフリースの登場が影響していると思います。フリースを着て、その下はTシャツでいいっていう感覚が広がった」とYさんは語る。セーターが担ってきた"温かさ"をフリースが置き換え、さらに生活の型まで変えた。決定打は「お手入れ」だという。
「ニットって洗剤をガツガツ入れて洗濯機で洗うっていう感じではないですよね。ウール100パーセントの服を洗濯機に入れて普通に洗うと絶対縮むし、毛玉もできるし」
縮み、毛玉、洗濯表示の確認、クリーニング代。忙しい生活のなかで、その手間は"敬遠される理由"になる。フリースはその面倒を、ほとんど丸ごと引き受けてしまった。
さらに気候と街のファッションも、セーターに追い打ちをかけた。
「今、四季じゃなくて"二季"の時代になったので、Tシャツを着る時期が、3月から下手したら11月ぐらいまで続きますよね。冬はそれをトレーナーに変えるっていうパターンになってきています」
では、セーターはどこへ行くのか。Yさんの答えは「消える」ではなく「嗜好品化」だった。
「ファッションとしてある程度お金があって本当に好きな人だけが買うみたいな、かなりニッチな商品になっていて、昔のようにシャツの上にセーターを着ることはすごく少なくなっています」
さらにYさんは、いまの服選びを「肌触りの時代」だと解説する。ヌメっとした感触、ふわっとした柔らかさは、化繊のほうが作りやすい。若い世代が惹かれる"ふわもこ"は、ニットではなく、フリースの発展形のような素材のカットソーが得意なところだ。モヘアやアンゴラが担っていた触感の贅沢は、価格と手入れが壁となって日常から遠ざかり、それを化繊が埋めた──Yさんの見立ては、そんな構図を指している。
天然素材は「別の席」で生き残る──メリノウールという存在

Yさんはウール100%の「自然の良さ」を認めつつも、現実の壁を強調する。
「ウール100パーセントって気持ちいいですけど、洗うとすごく縮んじゃう。やはりお手入れの手間があるかないかが結構ポイントかなと思います」
ただし、天然素材がただ負けているだけでもないという。天然の価値はある。しかし、日常のコットンの代わりにはなりきれない。だから市場は二極化していく----Yさんはそう見る。ひとつは、質感や"編まれた気配"を楽しむファッションとしてのニット。もうひとつは、メリノウールなどをタートルネックのセーターとして使うパターンだ。
「タートルネックのセーターっていうのは必ず一定の売り上げは絶対担保できるんですよ。フリースではやっぱり真似できないから」
セーターが"防寒の主役"を降りた一方で、ウールの一部は、別の実用の席──きちんと見えて、肌にもやさしい──を確保している。
セーターは消えたのではない。役割が変わっただけだ
地球温暖化が叫ばれる昨今だが、冬になれば寒波が来る。大寒ともなればしっかりと寒い。それでもセーターが当たり前ではなくなったのは、冬の暖かさが分解され、移動したからだ。フリースが外側の防寒を軽くし、機能性インナーが内側で体温の土台をつくる。暖かさの主戦場がインナーとフリースへ移ったとき、セーターは"暖を取る道具"としての責任を降ろし、好みと質感の服になっていく。
「冬になったからセーター買わなきゃっていう感じがないかも」
Yさんのこの一言に、いまの冬服の地図が凝縮されている。暖かさは、インナーとフリースとダウンの担当となった。セーターは、そのぶんだけ"着る理由が必要な服"になった。温かさの道具から、好みと質感と気分の服へ。セーターが消えたのではない。居場所が変わったのだ。
経済産業省「生産動態統計年報(繊維・生活用品統計編)2020」
ファーストリテイリング「沿革」
東レ「東レの歴史(2000年代)」
ミズノ「BREATH THERMO HISTORY」
【関連記事】
【動画】異常寒波、寒さのあまり樹木が爆発
「これは天才的」フード付きコートを「4倍暖かく」着る方法を発見した女性がSNSで話題に
「異常低温や異常高温に関連して年間500万人以上が死亡している」との研究結果
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。



