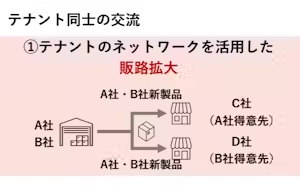企業のオフィスにエンゲージメント(働きがい・貢献意欲)の醸成や、イノベーションの創発の場としての機能を期待する機運が高まっている。野村不動産が計画する2棟の大型複合ビル「BLUE FRONT SHIBAURA(ブルーフロント芝浦)」は、ベイエリアの持つ自然環境などのポテンシャルを生かし、新しいオフィス像の提案を目指す。

組織と人が自然に集う
ブルーフロント芝浦は2月に「TOWER S(S棟)」が竣工。最寄りのJR浜松町駅からの通路も整備された。TOWER Nも含めた再開発全体は2030年度に完成する予定だ。
「オフィスビルの立地場所として、従来、芝浦の評価は高いとは言えなかったが、東京の重心が徐々に南下していく中でエリアのポテンシャルは高まってきていると思う。羽田空港へのアクセスがよく、水上バスやクルーズ船が出入りする日の出ふ頭も近い。リニア中央新幹線の始発駅になる品川もすぐだ。また、近くには増上寺や東京タワーがあって、昔から人が集まり、生活や遊行の場としての利便性が高いところでもあった」
「交通の便がよく、生活感覚のある場所というだけでなく、海の匂いがしたり、空が開けていたり、感性に訴えかける立地という特性も持っていると感じる。人が本能的に望む環境ともいえるだろうか。他のオフィスエリアと競合しないオンリーワンの場所であり、ここにそうした環境や経営の目標に沿った建物を造れば新たなオフィス、新しい働き方を提案できるはずだ。これからの企業の課題であるウエルネス(心身の健康)経営にも役立つだろうし、エンゲージメントも含めた社員同士の交流も促進できるだろう。こうしたことがイノベーションの創発などにもつながっていくと考えている」

「建物はひとつのフロアが1500坪とサッカーコートの7割くらいの広さがあるのが特徴だ。最上層部の面積を絞って、その分オフィスのフロアを広くとる設計になっている。ふらっと息抜きなどにも使えるコーヒーショップなどがある共用部分も、東京の最新大型ビルが3〜5%程度であるのと比べ約10%と突出している。28階にはジムやサウナ、東京湾を見晴らすテラスもある。近隣の東京ポートシティ竹芝や世界貿易センタービルディングなどとも連携して地域情報アプリなどを共有し、イベント情報などの利便も充実させる」
野村不動産自身も新宿野村ビルから本社を移転した。
「この10年ほどで業容が拡大し、新宿のビルでは全体の有機的な意思疎通をはかるのに手狭になった。本社とグループ会社の間にはヒエラルキーのようなものが生まれがちだったと思うが、そんなことを言っていてはこの変化の速い時代、現実に対応できない。開発部署がこれでいいと思ってやっていることも、お客様にじかに接する販売や管理側から見るとおかしなことがある。広いフロアに同居し垣根のないフラットな組織を作ればそうした情報が伝わりやすくなり、間違いの修正も早くなる。部門連携が高度化すれば、創発も起こりやすくなるだろう。お客様起点の経営を進化させたい」
「取り壊してN棟を建てる予定の当社保有の浜松町ビルディング(旧東芝ビル)の空いたフロアを活用し、本社を移転する準備として、いくつかの部署が交代でそこで一定期間、仕事をしていろいろな人が交わる働き方を試した。例えば、週末は簡単な懇親会なども企画する。強制ではなく、何時にきたらここに人が集まっているよというかたちで告知すると自然に人の交流ができることがわかってきた。昭和的な職場の宴会でない、気楽な交流を求めていたところもあり、それが解き放たれたようにも感じる」

芝浦で新しいオフィス像や働き方に取り組む姿勢には、使命感もあるという。
「当社としても一般論としても、コロナで変質した働き方や職場を作り直す必要があると考えている。まずは社員と会社のつながりが大切で、目指すのは組織と人が自然に集う場所だ。下手に出るわけでもなく、上から目線で言うのでもなく、来たくなるオフィス、ここに来たらいろんな人に会えるというオフィスをつくっていけたらいい」
「それをエンゲージメントと言うのだが、そう構えたものではなく、同じ趣味の人の集まりなど、気がついたら同じ場所にいて話をしている、そんな舞台装置が必要。ブルーフロント芝浦は立地もビルのハードもそうした作りになっている」
「当社は公共財に近いものを売っており、会社がサステナブルでないといけない。インクルーシブ(包摂的)な職場を作って健康、エンゲージメント、創発に取り組むのは、いままで当社の商品を買っていただいた方々への責任だという感覚が強くある。芝浦で当社なりの新しい働き方をつくり、入居していただくお客様にも伝えられることがあると思う」
編集後記 海・空・緑のもと、いまどきの交流の場に
コロナの時期にばらばらになった職場を新しい前提のもとでどう作り直すかは多くの企業の課題だ。おりからのSNSの興隆と相まって社員の気風が変わり、昭和的な強制で組織をまとめるのは難しくなった。一方で企業の競争力はかつての団体戦ではなく、一人ひとりの創造力が左右する個人戦の様相が強まってきている。
ただ個々人がスマホばかりと付き合って陰にこもれば仕事上の考えも陰謀論のような現実から遊離したものになりかねない。組織とつかず離れずのいまどきの気風に合った交流の場を上手に作り、いかに血の通ったエンゲージメントや創発、個の力の向上につなげていくかが新しい前提条件下での職場の方向性ではなかろうか。
こうした点で感性に訴える海や広い空、緑などの芝浦の環境を生かせばその実現に近づけるのではないかという松尾大作社長の考えは説得力があるように思われる。人間の幅を広げて創造性を伸ばそうと、リベラルアーツを見直す近年の流れとも整合的だ。
職場の再構築は大きくみればコミュニティーの再構築という社会的な意味合いもある。往時の家族的性格はなくなったとはいえ職場はいぜんそこで生まれる個人的な出会いや人間関係も含め、人が所属する主要な場所。職場にはSNSと違って自分と異なる考えの人がいて妄想的な考えの修正に役立つ。職場のありようは社会のバランス感覚とも関係がありそうに思う。
(編集委員 深田武志)
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。