多収の新品種 北海道で広がる
田んぼのあぜ道にかかるほど、長く垂れた稲穂。そして、びっしりとついた黄金色のもみに息をのんだ。

9月上旬、北海道奈井江町の生産者、杉本雄馬さんに田んぼを案内してもらった。そこに植えられていたのは「そらきらり」と呼ばれる品種。杉本さんは去年から本格的に生産を始めたという。
「そらきらり」は、北海道立総合研究機構で外食用をはじめとした業務用のコメとして開発され、去年から本格的に栽培が始まった新たな品種だ。北海道で作られる業務用のコメは、長年、「きらら397」という品種が主力だった。それに比べてもみの数が多く、試験段階では面積あたりの収穫量が2割近く多かった。

これまで「きらら397」を手がけてきた杉本さん。去年、「きらら397」を生産していた田んぼすべてを「そらきらり」に置き換えたところ、面積あたりの収穫量は、前の年より6%多かったという。そこでことしは、およそ9ヘクタールに面積を広げて作付けをした。

杉本雄馬さん
「同じ面積で収入を増やすとなったら、量をとるしかないと思い、作付けを始めた。去年は熟しきっていない青いコメが多かったが、それでも『きらら397』より収穫量があったので、もっとうまく作ればより収入につながると感じた」
杉本さんは、ほかの品種と比べて、生育や管理の手間がかからないというメリットもあると話す。

苗を植える間隔を広げることで、株が太く育って必要な苗の数が少なく済み、生産コストの削減も見込めるという。
じわり普及に手応えも

扱いに慣れていない品種だけに課題もある。杉本さんは、「そらきらり」は刈り取りの時期の見極めが難しいと話す。多くのもみが実るゆえに、同じ穂の中で成熟の度合いに差が出てしまうからだという。収穫を前にして、杉本さんは農協の職員から全体の7割ほどが育った時期に収穫するとよいとアドバイスを受けていた。

地元の農協の管内で、ことし「そらきらり」の生産に取り組むのは19の生産者で、作付面積はあわせておよそ96ヘクタール。おととし、杉本さんを含む2人が取り組んで以降、少しずつ広がりを見せている。農協の担当者も、確かな手応えを感じているという。

JA新すながわ 販売部 室井文博部長
「ブランド米の生産にこだわっている産地としては、品質がよくないという意見もある。しかし、品種をすみわけて生産できれば、お客さんのニーズに応えられるし、農協としても量がとれれば取り扱いが増えるメリットがある。今後、品種の切り替えを進めていって増産につながればいい」
「減反」が多収の軽視に
コメの歴史を振り返ると、長らく「量」よりも「質」を追い求める時代が続いてきた。
食糧難に苦しんだ戦後からしばらくの間は、コメの増産が喫緊の課題だった。水田を拡大するとともに、面積あたりの収穫量も増え、昭和30年代から40年代前半にかけて生産量が飛躍的に伸びた。
当時、開かれたコメの生産技術を競うコンクールでは、10アールあたりの収穫量がおよそ1トンにのぼる農家まで現れた。ところが、コメの生産量は順調に増える一方、消費は落ち込み続け、むしろ過剰が問題になる。
昭和46年にはコメの生産調整、いわゆる「減反政策」が本格的に始まった。

専門家からは、「コメ余り時代」に入ったことで、国などの研究機関が品種の開発にあたって「量」よりも「質」を追い求めることになり、面積あたりの収穫量が伸び悩む一因になったという指摘が出ている。
去年、日本の10アールあたりの収穫量は540キロ。世界に目を向けてみると、アメリカやオーストラリア、中国より低い水準だ。専門家は、増産につなげていくためにも、多収品種の導入は重要になると指摘している。

日本国際学園大学 荒幡克己教授
「これまでは各県が競い合って味がよい品種を作る傾向があった。今度は国が積極的に多収に取り組むことで、各県の産地間競争ではできなかったことをぜひ進めてほしい」
1度の田植えで2度収穫
収穫量を増やすため、1回の田植えで2回イネを収穫する、「再生二期作」と呼ばれる取り組みも広がりつつある。

日本では、一般的に春に苗を育てて田植えをし、秋に収穫。よくとしの春にまた田植えをする。もともと1年に2回収穫する「二期作」という方法はあるが、この場合は1回目の収穫のあと、再び田植えが必要になる。
一方、再生二期作は、1回目の収穫後に切り株から生えてくる芽を育てて、再度、年内に収穫する方法だ。イネを刈ったあと、数日で芽が出て成長する。1回の田植えで2回刈り取ることができるため効率が良く、生産コストを抑えながら収穫量を増やせると期待されている。
「にじのきらめき」と呼ばれる品種を使った試験では、4月に田植えをした場合、10アールあたりの収穫量が、1回目でおよそ600キロ、2回目はおよそ300キロと、あわせると900キロほどになった。
日本の10アールあたりの収穫量は540キロなので、同じ面積でかなり多くのコメがとれることになる。

浜松市の生産者、宮本純さんは、ことし10ヘクタールの田んぼで「にじのきらめき」の再生二期作に取り組んでいる。これは多くとれるだけでなく、暑さに強い特徴もある品種だ。
ことし、見込んでいる収穫量は1回目と2回目あわせて90トン。地元の弁当業者への販売も決まっていて、宮本さんはより多くのコメを届けたいと意気込む。

宮本純さん
「年々、厳しくなる夏の暑さに強い品種で、同じ面積あたりの収量をあげられるのであれば、やらない手はない。生産者が高齢化する中で、安定して地元産のコメをとれるようにしたい」
国の研究機関「農研機構」によると、再生二期作は通常より長い期間イネを育てるため、生育期間全体を通じて用水を確保する必要があるなどといった課題がある。それでもことしの栽培面積は去年と比べて倍以上に広がり、関東から九州にかけての19の県で、60ヘクタール以上になる見通しだ。
農研機構では、まだ普及は限定的ではあるものの、将来的に収穫量を確保していくための方法として広がっていくとみている。
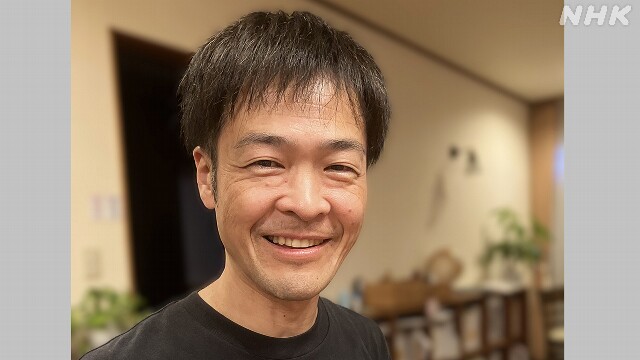
農研機構 中野洋 主席研究員
「再生二期作は、足元ではコメの価格が上昇する中で、収益性を向上できるとして関心が高まっているが、中長期的には、コメづくりの担い手が減る中で、収穫量を確保し、コメの生産を効率化する1つの技術として非常に重要になってくる」
多収が増産の後押しとなるか

多収をより確実なものにしようと、国も動き始めている。農林水産省は、来年度予算案の概算要求で、多収のコメをはじめとした品種の種子の生産体制などを強化する費用を19億円盛り込むなど、重点を置く姿勢を示している。
コメの生産現場では、農業に携わる人の不足や耕作放棄地の増加など課題が山積している。現状のままでは、政府がいくら増産の旗を振っても、絵に描いた餅に終わりかねない。
多収の重要性が生産者の間で見直されるかどうかが、“令和の米騒動”を根本的に解決するカギを握るといっても過言ではない。
(9月5日「ニュースウオッチ9」などで放送)
佐野 裕美江
2016年入局
青森局やむつ支局を経て現所属
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。


