“細胞の運命を変える”ことができるiPS細胞技術の可能性
京都大学の山中伸弥教授が2006年に発見したiPS細胞(人工多能性幹細胞)の樹立方法は、皮膚細胞や神経細胞、骨細胞などの体細胞を胚のような柔軟性が高い状態に「初期化=リプログラミング」する技術だ。これまでの常識では、神経細胞は神経細胞のまま、皮膚細胞は皮膚細胞のままと、一度決まったら変化することがなかった細胞の運命を変えることが可能になった。
iPS細胞の技術は、失われた臓器や組織を作りだす再生医療の分野で実績を上げてきたが、山田教授はiPS細胞を活用して、がんなどの疾病のメカニズムを明らかにする研究に取り組んでいる。また、近年は老化のプロセスを解明する研究が活発化し、老化した細胞を「若返らせる」可能性も注目されている。理論上、iPS細胞技術により細胞の運命をリセットすることで、老化による機能低下を解消できるからだ。
「細胞レベルでは、どれほど老化した細胞からもiPS細胞を作ることができます。いつとはいえませんが、いずれ生物の『若返り』を可能にし得る技術であることは間違いありません」

実際に近年、iPS細胞を用いたアンチエイジング研究が世界中で話題となっている。中でも注目を集めているのが、「パーシャルリプログラミング」と呼ばれる手法を用いた研究だ。これは、細胞を完全にiPS細胞に変えるのではなく、部分的に初期化を進めることで、老化形質(老化の特徴)を解除する手法である。
例えば、2021年に設立されたアンチエイジング研究のスタートアップであるアルトス・ラボには、アマゾン・ドット・コム創業者のジェフ・ベゾス氏らが巨額の出資をし、注目された。
2022年3月には、米ソーク研究所と、大手製薬企業ロシュの子会社であるジェネンテック社が、科学雑誌『Nature Aging』で、中高齢のマウスにiPS細胞をつくるための4種類の遺伝子(山中因子)を送り込んで部分的に細胞をリプログラミングし、組織の機能低下など老化の兆候を逆転させることに成功したと報告した。その後の長期的な観察でも、がんやその他の健康問題の増加は見られず、将来的にヒトに応用できれば、老化に伴う神経変性疾患などの治療や、細胞の機能・回復力の向上に役立つ可能性があるとして世界的に話題となった。

老化メカニズムの解明が研究の重要ポイント
山田教授もこの動きを注視しているが、「部分的な細胞のリプログラミングで老化を防ぐことができる、と短絡的に考えるわけにはいきません。研究はまだ『入り口』にも立っていない状況です」と慎重に推移を見守る。
「(上記の)『Nature Aging』とは違う論文では、マウスの細胞に2日間だけ山中因子を発現させ、5日間オフにするサイクルを繰り返すことで、早老症モデルマウスの寿命が2~3割延びたというデータが発表されました。しかし、なぜ寿命が延びたのか、どの細胞がどう関与しているのか、その詳細なメカニズムはほとんど分かっていません」
山田教授は、「何より『老化』という現象そのものが、分子レベルで十分に解明されていない」ことが課題だと言う。
「老化とは何か、細胞老化と個体レベルの老化の関係すら十分に理解されていません。たとえマウスの寿命が延びたとしても、部分的なリプログラミングが生体に与える影響や、人間に応用した場合の安全性は、まったく分かっていないのです。iPS細胞技術で細胞を初期化するということは、皮膚だった細胞は皮膚ではなくなり、骨だった細胞も骨ではなくなるということなので、『若返り』にならなないどころか、生物として生きていけません。つまり、論文のニュースから想像するほど単純な話ではなく、研究はまだようやく動き出した段階なのです」
若返りとがんのリスク
山田教授がそのように強調する理由は、自身が「部分的な細胞のリプログラミング」によって、がんの発生メカニズムの解明に取り組んでいるからだ。驚くべきことに、部分的なリプログラミングが「若返り」ではなく、「がんのリスクを高める可能性」もあるのだという。
「がんは、たばこなどに含まれる有害物質や放射線が遺伝子の配列に異常をもたらし、その結果、細胞ががん化して発症することが広く知られています。しかし、20年ほど前から、遺伝子の配列が正常であっても、遺伝子の使われ方の異常によってがんが発生する可能性があると考えられるようになってきました」
遺伝子配列そのものではなく、遺伝子の機能を制御する仕組みは「エピゲノム」と呼ばれる。生物の設計図であるDNAを構成する4つの塩基のうち、シトシンにメチル基がついたりはずれたり、細胞の核の中のヒストンというタンパク質が化学修飾を受けることで、「どの設計図をオン・オフにするか」が決定される。iPS細胞技術による細胞の「リプログラミング」とは、遺伝子の配列を変えずに、このエピゲノムを人為的にリセットしたり、変化させたりする技術といえる。
「私たちの研究チームでは、マウスに1週間だけ山中因子を発現させると、初期化の途中で小児がんに似たがんが発生することが確認されました。中途半端なリプログラミングががんを引き起こすことを、マウスモデルで証明したのです。これにより、遺伝子の傷だけでなく、『エピゲノムの変化』ががんの原因となりうることが明らかになりました」
山田教授のグループも、先のアンチエイジングの研究も、完全にリプログラミングするのではなく、「中途半端に初期化」する点が共通している。しかし、数日の期間の違いによって、かたやがんが発生し、かたや寿命が延びるという、真逆の結果が生じるのである。

夢の技術を社会実装するために
「この違いがなぜもたらされるのかは、非常に興味深いテーマですが、そのメカニズムはまだ明らかになっていません。もし本当にiPS細胞技術による延命が可能になったとしても、それを社会に実装するまでには、非常に多くの倫理的な議論が必要になるでしょう」
そして山田教授はこう続ける。
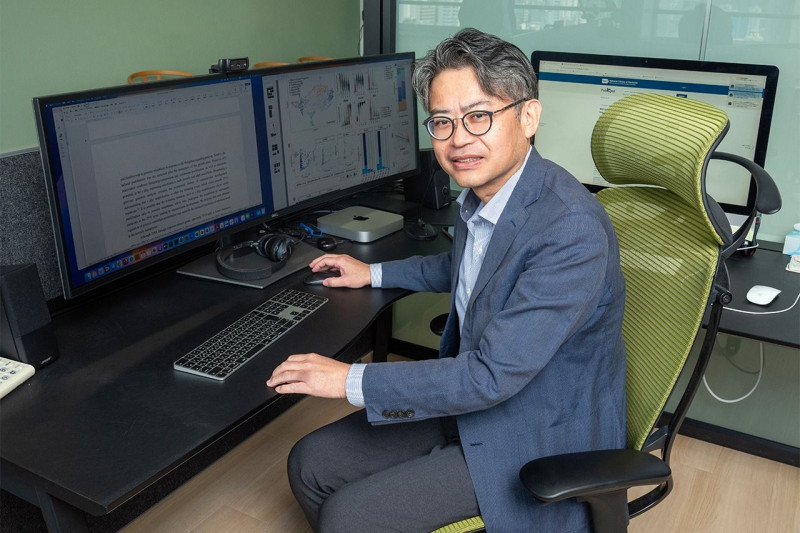
「過剰な期待は禁物ですが、基礎研究を積み重ねていけば、将来的にがん細胞の運命を変えて治療に役立てることや、健康寿命を延ばす技術が実現する可能性はあります。ただ、そのために異常に高額な薬が開発され一部の裕福な国、裕福な人だけが使えるものでは意味がありません。研究者としては、iPS細胞の技術が、社会全体が持続可能な形でその恩恵を受けられるよう意識することが大切だと思っています。言い換えれば、社会全体が持続可能な形でその恩恵を受けられるよう、責任を持って取り組んでいくべきだと考えています」
iPS細胞による若返りは、確かに我々に魅力的な未来の希望を見せてくれる。しかしそれを実現するためには、山田教授が言うように、「老化という現象そのもの」の解明を見据えた研究のさらなる進展が求められるだろう。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。



