
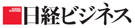
世界を震撼(しんかん)させたあの事件から、9月で丸10年を迎えた。独フォルクスワーゲン(VW)グループによる排ガス不正問題。通称「ディーゼルゲート」だ。
厳しい規制をクリアするため、VWは、試験中のみ有害物質の排出を抑えるソフトウエアをディーゼルエンジン車に搭載。その結果、試験では排ガス基準を満たしていても、通常運転中には基準の最大40倍の窒素酸化物を排出する車両を世に送り出した。「ディフィートデバイス(無効化機能)」を自動車に搭載することは、米国の大気浄化法に違反していた。
2015年9月18日。米環境保護局(EPA)がこうした調査内容を公表すると、VWのブランドイメージは失墜した。対象車両は世界で1100万台に上る可能性があると発覚し、大規模なリコール問題に発展。当時の経営幹部は次々と刑事訴追され、会社としても多額の罰金を支払った。15年通期決算は創業以来最大の赤字となり、解体的出直しを迫られることになった。
VWはこのディーゼルゲート事件の反省から、電動化にかじを切る。ヘルベルト・ディース前CEO(最高経営責任者)の下、電気自動車(EV)シフトを一気に推し進めた。
道半ばのEVシフト
21年12月には、向こう5年間で次世代の電動化技術やデジタル化に890億ユーロ(当時の為替レートで約11兆4000億円)を投資すると発表した。ディース氏は25年までに世界のEV販売台数で米テスラを抜くと公言するなど、「世界最大のEVメーカー」を本気で目指した。だが25年現在の状況は、まだ道半ばだ。
VWグループの24年のEV販売台数は約74万4800台。首位テスラ(約178万9200台)のみならず、中国の新興メーカー比亜迪(BYD、約176万5000台)にも大きく水をあけられた。
とはいえ、全く光明が見えないわけではない。実は25年に入って、VWグループのEV販売台数は伸びている。25年上半期(1〜6月)は前年比47%増の約46万5000台となり、欧州市場ではついにテスラを抜いた。
テスラを率いるイーロン・マスク氏の政治的姿勢が嫌気され、欧州でテスラ離れが進んでいるという事情はあるが、VW「IDシリーズ」や、独アウディ「Q6 e-tron」、チェコ・シュコダ「Enyaq(エンヤック)」など新型EVの引き合いが強い。このままのペースを維持できれば、25年には欧州最大のEVメーカーになりそうだ。
収益に貢献しないEV販売
しかし現状、EVが収益に大きく貢献しているとは言い難い。
VWはグループ全体で年間900万台を超す新車を販売している(24年の実績)。そのうちEVの割合は10%に満たない。プラグインハイブリッド車(PHV)を加えても11%台という状況だ。
欧州市場でEVの売れ行きが伸びているのも、値下げの影響が大きい。値下げ分だけ利益はそがれる。10年かけて進めてきたEVシフトは、むしろVWの経営を圧迫する要因となった。
24年9月以降、VWでは労使対立が鮮明になった。新車販売の落ち込みを受け、経営陣はドイツ国内の工場閉鎖などリストラ計画を提案した。
従業員側は徹底抗戦に出た。労使間交渉は平行線をたどり、ついにVWの労働組合は24年12月初旬にストライキを敢行する。同月20日になって合意に達し、ドイツ国内での工場閉鎖は見送る代わりに、30年までにドイツ国内の従業員3万5000人を削減する内容で決着した。
欧州最大、世界2位の自動車メーカーの経営危機は日本でも驚きをもって受け止められた。ディーゼルゲート事件以来の衝撃といえるかもしれない。
ソフト開発で混乱、CEOが退任
なぜ、VWはここまで追い込まれたのか。大きく3つの誤算がある。3つとは「ソフトウエア開発体制の混乱」「欧州市場への過信」「過度な中露依存」だ。
1つ目の誤算であるソフト開発体制の混乱について、VWが20年にグループ横断のソフト子会社「CARIAD(カリアド)」を立ち上げたことに遡る。アウディ、ポルシェなど傘下ブランドから技術者約6000人が結集。次世代EVを担うソフトウエア開発の内製化をもくろんだ。
しかしブランドごとの意識の強さが裏目に出てしまい、ソフト開発は遅れに遅れた。これにより、当初予定していたEVの発売時期も先送りになった。カリアドを設立したディース氏は混乱の責任を取る形でCEOを退任。グループを追われた。
VWは第2次世界大戦前の1937年、ドイツの国営企業として誕生したが、現在の筆頭株主はポルシェ家とピエヒ家の資産管理会社であり、議決権の過半数を握る。本社のあるニーダーザクセン州も20%の議決権を持つなど、特殊な企業統治を敷いており、それがしばしばトップ人事にも反映される。
ディース氏は創業家の不興を買い、その後任としてポルシェCEOのオリバー・ブルーメ氏が就任し、現在に至る。グループの総力を挙げるべきソフト開発で大きくつまずいた。その間にライバルのテスラや、BYDがベストセラーを生み出し、簡単には追いつけない差となった。
2つ目の誤算は、欧州市場の強さを過信したことだ。
環境意識の高い欧州では、欧州連合(EU)が主導してEVの普及を促してきた。加盟国がEV購入補助金や減税などの支援策に乗り出し、それがEVの販売拡大につながった。しかし、2023年12月、ドイツが予算の枯渇を理由に補助金支給の打ち切りを発表。これにより、ドイツ国内でのEV人気に急ブレーキがかかった。
市場の急成長を見越して増強してきた生産能力が過剰になり、リストラをしなければ乗り切れなくなった。アウディは25年2月、ベルギーのブリュッセル工場を閉鎖している。
3つ目の誤算は、過度な中露依存だ。
VWをはじめとしたドイツの製造業は、ロシア産の安価な天然ガスの輸入に頼ってきた。しかし、22年のロシアによるウクライナ侵略以降、ロシアからの天然ガス調達が難しくなり、エネルギーコストの高騰を招いた。
VWの場合は、もともと高コスト体質だったのも災いした。大株主である州政府、強固な労働組合との関係上、工場の再編やリストラがなかなか進まなかった。そこに、光熱費の上昇が追い打ちをかけた格好だ。
ドル箱だった中国市場が、変調したのも大きい。デフレ圧力が強まり、地元中国メーカーの低価格車に押されるようになった。19年には年間400万台を超えた中国での販売台数は、24年に300万台を割り込み、中国トップの座をBYDに明け渡した。
ロシアと中国に頼り切ったビジネスモデルが、逆回転しているのだ。
それでもEVに懸けるVW
足元では米国のトランプ政権による関税政策が逆風に働く。VWグループの25年上半期は、3割超の大減益となったが、新車攻勢は続ける。9月にドイツ・ミュンヘンで開催された自動車展示会「IAA MOBILITY 2025」では、4つの新型モデルをお披露目した。27年には約2万ユーロ(約340万円)の低価格EV「ID.EVERY 1」を投入する。
CEOのブルーメ氏は25年上半期の決算会見で「新製品の成功がけん引し、極めて厳しい環境下でも、確固たる地位を維持している」「欧州では電動モビリティーで主導的地位を拡大し、市場シェア28%を達成。受注残も堅調に推移している」と語り、EV強化の姿勢を改めて示した。
中国では新興EVメーカーである小鵬汽車(シャオペン)と提携し、ソフトウエアのシステムを共同開発した。今後、さまざまな車種に導入し、巻き返しを狙う考えだ。米国でも24年、新興EVメーカーのリヴィアン・オートモーティブに最大58億ドル(約8500億円)を投資すると発表した。
ディーゼル車からEVへかじを切った後の10年、VWはもがき苦しんだ。「それでもなおEVに懸ける」という選択は、吉と出るのか。次の10年が本当の勝負になる。
(日経BPロンドン支局 酒井大輔)
[日経ビジネス電子版 2025年9月5日の記事を再構成]

|
日経ビジネス電子版
週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。


