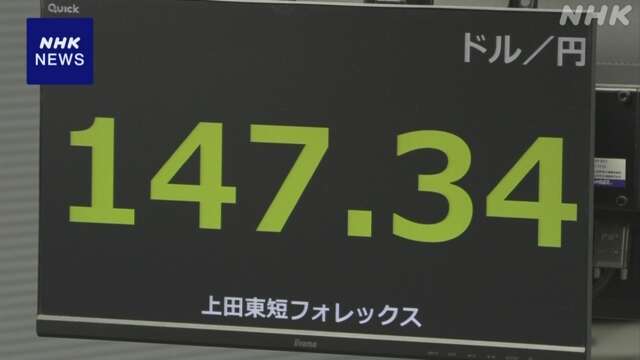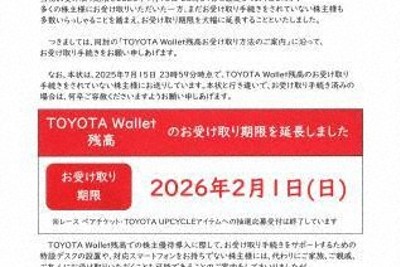これからのビジネスや暮らしを支える生成AI(人工知能)は、膨大な情報処理を担うデータセンター(DC)の増設と切り離せない。いまのところ立地の9割は需要地に近い東京、大阪の二大都市圏に集中している。
大都市圏は用地の確保が難しいうえ、大量のクリーン電力の確保にも不安が残る。AI活用を進めるため、DCの地方分散の促進策づくりを急ぐ必要がある。
多数のサーバーや通信機器を備え、24時間稼働するDCは、設備の冷却などに大量の電力を使う。電力広域的運営推進機関はDC向けの電力需要が今後10年で13倍に増え、2034年度に600万キロワットを超すと予測する。これは原子力発電所6基分に相当する。人口減少にもかかわらず、今後の総需要の増加が見込まれる主因だ。
増える電力は脱炭素化が不可欠だ。しかし発電時に二酸化炭素(CO2)を排出しない再生可能エネルギーは北海道や九州、稼働中の原発も西日本に偏在する。
このため需要増への対応にあたり、地方の電力を送電線で大都市へ運ぶのではなく、DCを地方に建設し、データを光ファイバーで大都市へ運ぶ構想が浮上している。電力の単位のワットと通信の単位ビットを合わせて「ワット・ビット連携」と呼ばれ、政府が2月に閣議決定した「GX2040ビジョン」で推進を掲げた。
一般に送電線より通信回線の方が整備費用が少なく、建設期間も短くてすむ。DCを全国に分散配置すれば広域災害への対策ともなる。AI時代の新たな産業集積の早急な具体化を望みたい。
推進には課題も多い。DC事業者の地方投資を後押しするよう、投資優遇などの政策誘導が欠かせない。現地での人材確保策を含めて自治体の誘致策任せにせず、政府が主体的に取り組むべきだ。
電力事業の法規制も再考余地がある。発電事業者は需要家に電力を平等に売らねばならず、特定の顧客に安くは供給できない。DC事業者が発電所の建設・運営に参画し、一定の電力を引き取るといった選択も可能にしてはどうか。
出力が変動する再エネなどを地域間で融通するため、政府は広域送電網の増強に6兆〜7兆円を投じる長期計画を策定済みだ。ワット・ビット連携が動き出せば、そうした計画の再検討も必要になろう。国民負担の軽減につながる全体最適を考えてもらいたい。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。