
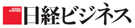
日本食業界は今、かつお節の原材料不足に直面している。カツオの水揚げ量の減少に加えて、カツオやマグロを原料とするツナ缶が安価で保存しやすいタンパク源として、新興国を中心に需要が増えているからだ。需給の引き締まりから、総務省の消費者物価指数では、2024年のかつお節の価格は前年比22.7%上昇した。日本食に欠かせないかつお節を使ったダシをどのように持続可能にしていくのか。
この課題の解決に取り組んでいるのが、業務用チョコレート大手の不二製油だ。同社は植物由来の油脂とタンパク質を組み合わせ、鶏肉や豚肉、魚介系などの風味を表現したダシを自社開発。老舗そば屋やラーメン店などが、そのダシを活用したメニューを展開している。原材料の安定調達だけでなく、インバウンド需要に備えたビーガン(完全菜食主義者)向け商品を展開できる点や日本食の海外進出の一助となる点でも注目を集めている。
不二製油が開発したのは、パーム油や大豆たんぱくなど植物性原料を使ったダシ「ミラダシ」である。23年から主に業務用向けに展開している。ミラダシで表現したダシの風味は、鶏肉と牛肉、白湯、かつお、貝の5種類。その多くがペースト状になっており、水やお湯に溶かすだけでダシを作ることが可能だ。

筆者はいくつかミラダシの味を試してみた。例えば鶏肉風味のミラダシは、透明感のある色合いは鶏ガラのダシそのもので、白湯の白濁感も本物そっくりだ。味のほうも、一口飲むとそれぞれの素材らしいうまみやコクが再現されている点に驚かされる。
「おいしさ」だけでなく、「満足感」を追求
「ダシのうまみから得られる『満足感』をどう表現するかに最もこだわった」
こう話すのは、ミラダシの企画を担当する風味基材事業部の平垣内一子氏だ。植物性原料を使う代替食品の大きな課題の1つは、動物性特有の食べた時の「満足感」を表現することだった。
同社が実施した調査によると、植物性の加工肉やスープなどを食べて「おいしい」と回答した消費者は一定数いるものの、「満足感があった」と回答する消費者はその半数以下にとどまったという。
おいしいと思ったとしても、「満足感」がなければリピートにはつながらない。この課題を同社は、パーム油などの植物性油脂と大豆たんぱくを乳化や加熱などを経て融合させることで克服した。これが同社が独自開発した動物性らしいうまみを表現する「ミラコア」という技術だ。
平垣内氏は「肉や魚はタンパク質と油脂が主要な要素であり、これが満足感を生む要因と考えている。植物性の油脂とタンパク質を両方事業で扱っている企業は少なく、不二製油ならではの強み」と話す。
ミラダシは、このミラコアの技術をベースに野菜エキスや酵母エキス、大豆ペプチドなどを配合してダシの味を表現した。味の表現方法にもこだわりがある。
平垣内氏は「一般的には表現したいダシの味の成分を分析し、それに近い材料を探し集めて作る。しかしミラダシの場合はそのダシの原料の成り立ちや育った環境などをたどることが味の表現につながるという発想を持っている」と話す。
例えば貝風味のダシの場合、貝が海藻を食べることから、昆布エキスを加えた。また海藻は海の底でミネラルを吸収しながら育つことから、海洋深層水も配合している。食材のルーツから着想を得ることで、ただ機械的に分析するだけでは表現できない「貝らしさ」を追求している。
老舗そば屋がビーガン向けメニューに採用
23年に販売を始めたミラダシは、飲食店に徐々に浸透している。動物由来の材料を使っていないことからビーガン向けのメニューに使われることが多い。
ミラダシを使用している飲食店の1つが東京・麻布十番に本店を構える1789年創業の老舗そば屋、更科堀井だ。
近隣に大使館が点在しており、利用客全体の約1割が外国人だという。堀井良教代表取締役は「ビーガン向けのそばメニューを作るにあたって、一番の課題はつゆに使うかつおダシだった」と話す。
一般的に江戸前のそばつゆはかつおダシに濃い口しょうゆを合わせて作る。堀井氏は「代替として野菜だしなどで試してみたが、どうしても濃い口しょうゆの味に負けてしまい、納得のいくつゆが作れなかった」と振り返る。
救世主となったのが、ミラダシのかつお風味だった。堀井氏は「動物由来の材料を使わなくても、しょうゆの味に負けないかつお味の濃いダシが初めて作れた」と話す。
かつおだけでなく、普段そば屋では取らない鶏肉や白湯などのダシもミラダシがあれば簡単に作れる。堀井氏はこのミラダシをベースに様々なメニューの開発に力を注ぐようになり、現在は月替わりでビーガン向けメニューを展開している。
例えば6月に提供された「シチューさらしな」は、不二製油が開発した豆乳クリーム由来のバター様素材「ソイレブール」を加えて濃厚さをプラス。大豆ミートなどをトッピングしてシチュー風に仕立てた。

堀井氏は「ミラダシを配合すれば和洋中様々な料理に挑戦でき、そばの可能性を広げられる」と強調する。

堀井氏は「もしもかつお節が枯渇するようなことが起きた時に、江戸前の伝統的なそばの味を残せるのかという危機感がある。そのような事態に備えて、かつお節だけに頼らないメニューの選択肢を広げることは大切」と話す。
日本食の海外進出にも一助
そば以外にもミラダシの活用方法は広がっている。その1つがラーメンだ。不二製油は鶏肉風味や白湯風味などを配合して開発した豚骨風、味噌、塩の3種類の業務用ラーメンスープを2月に発売した。
長野県白馬村のスキー場、エイブル白馬五竜のレストランではその製品をベースにしたビーガン向けの豚骨風ラーメンが提供されている。

ミラダシはラーメンやそばといった日本食の海外展開の一助にもなる。家畜伝染病の一種、豚熱の影響で日本から海外への豚肉輸出は制限を受けているほか、欧州連合(EU)はかつお節に含まれるベンゾピレンという物質を有害と捉えており、かつお節やかつお節由来のめんつゆの輸入に規制をかけている。
代替材料で開発されたミラダシはそうした規制を受けずに輸出でき、日本で親しまれている味を海外で表現できる。平垣内氏は「日本食独特のダシの取り方を現地のスタッフに教育する手間を省き、水に溶かすだけなので人手不足の解消にも役立つ。今後は海外展開を狙う飲食店と協力しながら、海外での販売比率を増加させたい」と話す。
植物性油脂と大豆たんぱくを駆使し、様々な代替食材の開発に取り組む不二製油。代替食材の進化は原材料不足の解消だけでなく、ビーガンやアレルギーを持った消費者にも食事の楽しみの幅を広げられるなど、広義の食のサステナビリティー(持続可能性)を支えられる。
(日経ビジネス 濵野航)
[日経ビジネス電子版 2025年7月14日付の記事を再構成]

|
日経ビジネス電子版
週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。

