
津田塾大学(本部・東京都小平市)は2023年6月に性自認が女性であるトランスジェンダー学生の受け入れを決定し、25年度から受け入れを開始した。受け入れが始まった現在、在学生や教職員へはどのようなサポートが行われているのか、また在学生は受け入れに対してどのような思いでいるのか取材した。【津田塾大・筒井真桜(キャンパる編集部)】
検討開始から8年
津田塾大が受け入れの検討を始めたのは17年5月。学内で副学長、学部長などで構成された「トランスジェンダー学生受け入れのための検討委員会」を発足させた。同委員会でガイドライン、受け入れ手続き要項の策定など制度面での整備を行った。

また設備面では、学内の多目的トイレが性別を問わず使える「オールジェンダー」トイレであることを出入り口に明記。授業などで着替えが必要になる場合を想定し、同トイレ内に着替えボードも設置した。
受け入れ開始までに時間を要したのは、制度や施設などの整備に加えて在学生、保護者、教職員への説明や研修など受け入れるための態勢構築に時間をかけたためだ。また検討を行っている最中の20年度には新型コロナウイルスの感染急拡大により、検討が一時停止したことも大きく影響した。
専用の相談窓口を開設
コロナ禍が収束し、議論が再開した後の23年度には、受け入れ開始に先立ち、在学生、教職員を対象とした専門家によるジェンダー・セクシュアリティー(性と性のあり方)相談室「にじいろルーム」を小平、千駄ケ谷の都内2キャンパスに開設した。受け入れのための態勢構築に携わった同大情報サービス課の斉藤治人課長によると、在学生の権利保障について議論をしている際に「ジェンダーに関して専門家に相談できる場所がほしい」という要望が寄せられていた。そのため、トランスジェンダー学生受け入れに伴う不安を受け止めるとともに、ジェンダーやセクシュアリティーに関する相談を受け付ける場が必要と考え設置を決めたという。
現在は3人のカウンセラーが各キャンパスでカウンセリングを行っている。相談者は対面、もしくはオンラインで匿名、非対面で悩みを相談することができる。カウンセリングは、各キャンパスとオンラインで行われている。また、在学生の保護者も相談室を利用することができる。
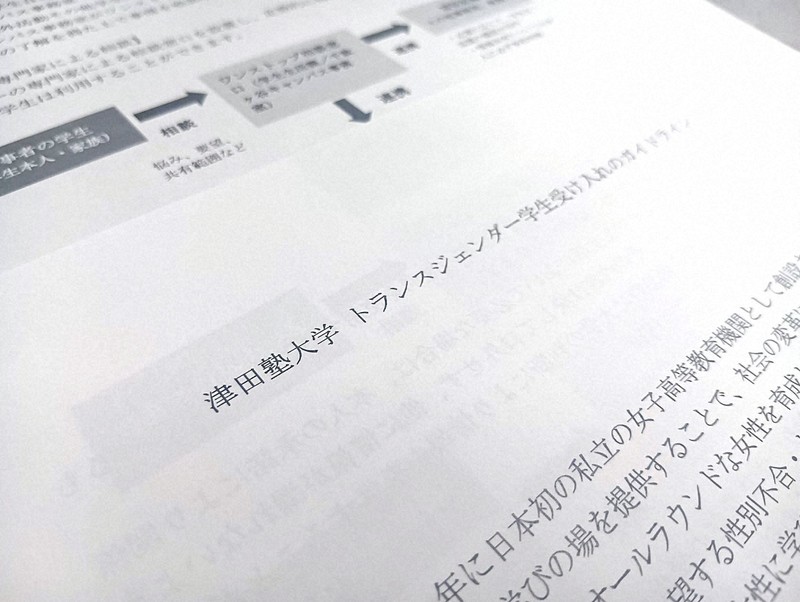
開設から3年目となる現在は、在学生の要望もあり、恋愛観の悩み、性別に基づく固定観念や偏見などについて、さらに幅広く相談を受けるようになった。相談室の利用者数は開設初年度の23年は約70件、24年は約80件とやや増加した。相談室を担当する同大学生生活課の三宅美則専門員は「にじいろルームを通して多様性を認め合い、大学でも安心して過ごせるセーフスペースを持っていただければ」と語った。
また、にじいろルームでは「もっと相談室へ気軽にきてほしい」という思いから24年度から定期的に読書会やお茶会といったイベントの開催を始め、悩みがない学生もイベントを通して、ジェンダーやセクシュアリティーについて学べる機会を作っている。
受け入れる在学生たちの思い
このように津田塾大は受け入れ態勢の整備を進めてきたが、在学生たちの思いはどうだろうか。25年度から受け入れが始まったが、大学側は実際に入学したトランスジェンダー学生の有無については、一切公開しないとしている。また同大はトランスジェンダー学生受け入れに際して発表したガイドラインで、学生本人の申し出により通称名を使用することを認めている。学生本人が自らカミングアウトしない限り、在学生に知られることはない。

記者が在籍する総合政策学部の1~4年生にオンラインで現在の胸中を尋ねたところ、13人から回答が得られた。トランスジェンダー学生の受け入れについて「何らかの不安を感じることはあるか」という問いに対して、「不安を感じていない」と回答した学生は3人だった。一方で、「不安を感じている」と回答した学生は10人だった。
「不安を感じていない」学生に理由を尋ねると、「トランスジェンダー学生の受け入れ前に自分自身で知識を身につけていた」「サポート態勢として相談室が設置されているのは安心」という回答が寄せられた。
一方で、「不安を感じている」学生に理由を聞くと、「実際は性自認が男性なのに、女性のふりをして入学する『なりすまし』が起こるのではないか」などといった声が上がった。また、「今後何らかの問題が発生した際に、大学が適切に対処してくれるのか強い不安を抱いている」との意見もあった。
道半ばの「多様性尊重」
多様性を重視する立場から決めたトランスジェンダー学生の受け入れだが、交流サイト(SNS)などネット空間では、現在も学生が不安になるような投稿が目立つ。また米国のトランプ政権が女子スポーツ競技からトランスジェンダー女性を除外したように、多様性見直しの動きもある。学生が抱く不安の背景には、そのような世相や風潮があるように感じる。

こうした学生の不安を受け止める役割が期待される「にじいろルーム」だが、その存在を知っているかどうか尋ねたところ、「はい」と回答した学生が13人中12人だった。多様性尊重のために大学側が行った措置と対応策への認知度は高いと考えられる。ただ不安を感じる学生は現実におり、「にじいろルーム」の利用者や利用度合いをさらに増やすなど、トランスジェンダー学生受け入れに対する理解促進の取り組みが必要と言えそうだ。
自然と深まったジェンダー観
回答してくれた13人の在学生のうち、了承が得られた1人に個別取材で直接、話を聞くことができた。「受け入れに関して不安を感じる」というこの学生にどんな点で不安か尋ねたところ、トランスジェンダー学生と接する際に、適切な配慮ができず「相手を傷つけてしまうのではないか少し不安を感じる」のだと話した。ただ現在は、その不安は解消しつつあるという。受け入れについて考えている中で「一人一人と関わる中で、気をつけていけばよい」と前向きに考えるようになったからだ。
同学生は「にじいろルーム」の利用経験があり、相談後はルームから届く案内で興味を持って、定期的に読書会やお茶会などのイベントに参加した。読書会ではジェンダーを題材とした課題図書を読み、同世代の参加者と本について語り合う中で「自然とジェンダーについての考えを深めた」という。オンラインでの個別相談から対面でのイベント参加までの一連の体験をしたことで「ジェンダーについて前向きに調べてみる、考えてみる、ということを楽しんでできるようになった」と振り返った。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。



