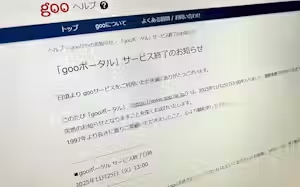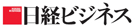
今や自動車に次ぐ輸出規模となった日本のコンテンツ産業。輸出額の約6割をゲームが占める。政府が海外売上高20兆円の目標を掲げる中、「東京ゲームショウ2025」を主催する一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)の辻本春弘会長(カプコン社長)にゲーム産業の可能性などを聞いた。
――国内外のゲーム市場について足元の業況をどう見ますか。
「個別の国の状況については正確に把握していませんが、日本のパブリッシャー(販売元)の業績を見ると、海外売上高比率が上がっています。海外でゲームを買う人が広がってきているという実感があります」
「ソニーグループの『プレイステーションストア』や、ゲームの配信プラットフォーム『Steam(スチーム)』といったデジタルを使ったビジネスがゲーム業界を180度変えました。小売店を経由しなくてもユーザーがゲームを買えるようになり、昔のゲームを安い値段で遊んでもらえるようにもなりました」

――日本のコンテンツ産業の輸出額は半導体や鉄鋼を上回り、政府は2033年に20兆円という目標を掲げています。経済産業省が6月に策定した「エンタメ・クリエイティブ産業戦略」ではゲーム産業への期待も大きいと感じました。
「24年9月、岸田文雄前政権の時に総理官邸に招かれました。その際、CESAとして人材育成や外貨獲得に向けた海外売上高比率の向上、(個人や小規模企業が開発する)インディーゲームの支援などを提案しました。東京ゲームショウに関係者を招待しましたが、『ゲーム業界ってすごいね』とびっくりされました」
「以前の『クールジャパン戦略』では映画やアニメ、漫画が中心でしたが、ゲーム産業の輸出額はコンテンツ産業全体の約6割にも上ります。成長しているという客観的なデータが出てきているので、政府も後押ししやすいのだと思います」
――他のコンテンツ産業における海外開拓が不十分な中、なぜゲーム業界は先行しているのでしょうか。
「ゲーム産業は業務用ゲーム機からスタートしました。当時から日本だけでは頭打ちになるだろうということで海外展開を意識してきました。1983年に家庭用ゲーム機『ファミリーコンピュータ』を発売した任天堂も『ドンキーコング』や『マリオブラザーズ』といった業務用を手掛けていました。ゲーム業界というのは、もともと海外を意識してビジネスを進めてきた歴史があります」
――ゲームが、他のコンテンツ産業をけん引できる分野はありますか。
「海外もそうですし、デジタルもそうでしょう。日本において成長産業がなかなか見いだせない中、僕たちは『日本のゲーム産業はこれからの成長産業であるべきだ』と思っています」
「ゲーム業界では10年前ぐらいからデジタル化を推進しています。カプコンが26年2月に発売する予定の『バイオハザード レクイエム』では過去シリーズのデータを多面的に分析した上で、どのように売っていくか考えています」
「ゲームは他のコンテンツ産業よりもデジタル化が進んでいます。デジタル人材がゲームから映画、漫画、アニメといった業界に行って活躍することがあってもおかしくはないですよね」
裾野広がるゲーム産業
――東京ゲームショウ2025の見どころはどこでしょうか。人工知能(AI)の活用でしょうか。
「AIは時代背景として取り組まなければならないテクノロジーです。ただ今回のゲームショウについて『AIが見どころか』と聞かれればそうではありません。来場してもらえれば分かりますが、ゲーム会社だけでなく、ニトリホールディングスやミズノ、キヤノンといったゲームに関係がなかった企業も接点を見いだそうと、出展しています。前回と比べてもゲーム産業の裾野が広がっているというところが見どころだと思います」
――活況な日本のゲーム産業ですが、課題はありますか。
「人材育成だと思います。もっと突っ込んだ取り組みをしていかなければならない。カプコンで言えば、新卒採用時点で専門学校卒の開発者の比率が5割ぐらいなんですよね。ゲームのビジネスは専門性が高い。ただゲーム業界の大手企業は時価総額も高く、いわゆる一流企業と言われているので、就活生の親御さんたちは『大卒じゃないとダメだろう』と考えがちです」
「僕は、義務教育はしっかり受けてもらわなきゃいけないとは思いますが、ゲームが好きな人はゲームをやりながらゲームに携わるための勉強をした方が、これから先のゲーム産業の人材として有望ではないかと考えています」
「これはCESAとしてではなく、カプコンという個社の考え方ですね。ゲーム業界に進むにはどういう勉強をすべきなのか。専門的なことを勉強すべきだと啓蒙していくことが必要だと思っています」
――ゲーム産業も家庭用、PC、モバイルとあります。特にモバイルでは日本よりも中韓勢の勢いが増していますが、危機感はありますか。
「カプコンに関して言えば、10年ぐらい前にモバイルがうまくいかず、家庭用やPCをやっていこうと切り替えました。だから足元で、モバイルを手掛けるゲーム会社が何に苦戦しているのかは正確には分かりません」
「モバイルは無料で遊べる『フリー・トゥ・プレイ』で、都度の課金によって一部の人たちから収益を上げてきました。それとは反対に、僕たちのビジネスモデルは最初の段階からお金を払ってもらって遊んでもらう、そして楽しかったから続編も買ってもらえるという本来のゲームのビジネスモデルになります。そこを突き詰めていこうと思っています」
「カプコンは『バイオハザード』も『モンスターハンター』も『ストリートファイター』もユーザーに付いてきてもらえていると考えています。僕たちがちゃんとカプコンのゲームユーザーに応えられるようなゲーム作り、ビジネスをやってきた結果でしょう。良い点は他社にもまねしてもらいたいと思っています」
新規を手掛けて気付きを得る
――ゲーム産業はレッドオーシャン(過当競争市場)が続きそうです。
「業界として潤っていればいろんな企業が参入してくるのは世の常です。これはもう仕方ありません。ゲームというのは生活に関係するものではありません。だからこそ、僕たちはユーザーに喜んでもらえるように将来においても継続してやっていかなければなりません」
「幸い、近年は小売店に販売してもらうだけでなく、グローバルな規模でデジタルイベントなどを通じ、どこの国でどれだけ見てくれているのか、SNSでの評判はどうかといったデータを自分たちで取得できます。それらを分析し、場合によってはゲームの一部を修正することもできます。ユーザーがいるからこそゲームを買ってもらえる。満足してもらえるゲームを作り続けることが根底にあります」
――ゲーム開発費の高騰もあり、日本のゲーム産業は新規有力IP(知的財産)の創造に苦戦している印象があります。
「いろんなジャンルのゲームが出ており、シリーズ作品が出ている中、ユーザーに振り向いてもらえる新規のものを作るというのはなかなか難しい。カプコンとしてもそれを痛感しています。今回、展示している新作の『プラグマタ』も話題にはなっていますが、本当に買ってもらえるのか。ユーザーが使える年間の購入予算だけでなく、ゲーム以外も含めた時間の取り合いなんですよね。非常に障壁が高い」

「このあたりは各社の考え方もあるでしょう。カプコンとしては新規をやり続けなければ、新しいものを展開するためのノウハウが蓄積されないなと。これは経験と勉強であろうと。モンスターハンターは2000万本、3000万本売るのは当たり前ですが、プラグマタは1000万本売れるのか、分かりませんよね。場合によっては100万本売るのも大変かもしれません。それでも新規のものをやることによってマーケティングやプロモーションで新たな気付きがあります」
(日経ビジネス 高城裕太)
[日経ビジネス電子版 2025年9月26日の記事を再構成]

|
日経ビジネス電子版
週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。