
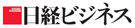
北海道南西部、渡島半島から船で2時間の日本海上に浮かぶ奥尻島。人口わずか2000人ほどの島に1台の移動販売車が走る。「いつも楽しいサツドラ、いつも近くにサツドラ」――。スピーカーから楽しげなテーマソングが流れると、1人、また1人と住民が集まってくる。
一人暮らしだという87歳の女性は「車もなく、通院以外で遠出もしない。毎週の移動販売が楽しみで必ず買い物する」と話す。島で生まれ育った92歳の女性は「ここでお菓子を買い、近所の家へ遊びに行く」と顔をほころばせる。

2022年8月に島内を走り始めた移動販売車は、北海道でドラッグストアを展開するサツドラホールディングス(HD)とヤマト運輸が手を組んで実現したものだ。きっかけは、ヤマト運輸の一人のドライバーの思いからだった。「小売店が少なく、買い物に不便を感じている高齢者も多い。島のために何か新しい取り組みができないものか」。
島の課題解決に動いたその人はヤマト運輸、奥尻営業所の泉沢輝基グループ長。自身も奥尻に生まれ、毎日の配達で顔を合わせる島民のほとんどが顔なじみだ。トラックを走らせていると、すれ違う島民らが手を振り、挨拶を交わすような関係にあった。
当時、北海道統括マネージャーだった奈須川洋平氏(現・宅急便部地域創生課長)が泉沢氏の提案を聞き、検討を進めてたどり着いた提携相手がサツドラHDだった。もともと両社の間には、サツドラの店舗でヤマトの宅配便ロッカー「PUDOステーション」を設置していた関係性があった。2社の奥尻での連携は、21年11月にヤマトの営業所の一角でサツドラの商品を販売することから始まった。
その後、実験的に販売車を導入し、食料品、さらに冷蔵品や冷凍品へと扱う商品を増やしていった。奥尻島行きの船は一日1、2便。島に荷物が届くまでの待ち時間などを生かし、ヤマトの配達員が移動車で販売する。現在は月曜から金曜に島内の各地域を回り、島民の買い物需要を支えるようになった。
奥尻島での取り組みは、今のサツドラHDの経営戦略を表す象徴的な事例の一つだ。北海道内各地で地域の課題解決に動こうとする企業や自治体と連携しながら、普通では商圏が成立しないような小規模な市町村で挑戦的に出店を続けている。
コンセプトは「北海道の『いつも』を楽しく」
かつては個性の薄いローカルドラッグストアチェーンの一社だったサツドラHDは会社のリブランディングを進め、「北海道の『いつも』を楽しく」というコンセプトを打ち立てたことで変わり始めた。
さらに同社は19年、「ドラッグストアビジネスから地域コネクティッドビジネスへ」という新たなビジョンを打ち出した。地域の課題を解決する企業に変わろうとする取り組みについて、富山浩樹社長は「社会的責任(CSR)活動ではなく、あくまで経営戦略だ」と話す。
総務省によると、24年10月1日時点の人口推計で北海道内の人口は504万3000人。前年からの減少率は0.97%で、全国平均(0.44%)を上回る状況だ。都道府県別の人口密度が最も低いだけに、過疎地域をどうしていくかは大きな課題で、サツドラHDも自治体と組んで正面から向き合っている。

オホーツク海に面する小清水町で24年10月、サツドラ小清水店がオープンした。商圏人口を1万人前後に設定するドラッグストアが多いことを鑑みると、人口約4300人の同町はその商圏が成り立つ規模とは言い難い。売り場面積は1274m2と、決して小さな店舗でもない。
そんな中で何が出店の決め手となったのか。ポイントは店舗の駐車場を挟んで位置する小清水町の新庁舎だ。町民の要望を受け、サツドラの店舗をここに誘致したのは他でもない小清水町。23年5月にできた新庁舎は「防災拠点型複合庁舎」と呼ばれ、コインランドリーやジム、カフェなどを併設する。災害時には洗濯、シャワー、炊き出しなどの防災拠点として使う。

サツドラの店舗も災害時には町の備蓄庫へと姿を変える想定だ。民間施設を集めたことで、以前は年間4800人ほどだった庁舎への来訪者数は12万超に増えた。小清水町の石丸寛之産業課長は「生活インフラとしてドラッグストアを求める住民の声はずっとあった。知恵を出し、公民が協力したことで実現できた」と話す。
地元の商工会も独自に運営していたポイント制度を廃止し、代わりにサツドラグループが運営する地域共通ポイントカード「EZOCA(エゾカ)」を導入した。町内のポイントが流出する恐れがあると懸念する事業者もいたが、「町外の客がポイントを町内で使ってくれる可能性もあると柔軟に考え方を変えた」(石丸氏)という。それまでは紙のスタンプ券を台紙に集める形だったが、エゾカの導入によってデジタル化を進めることもできた。
サツドラ店舗内に町役場の支所

札幌市にほど近い当別町の太美地区にも、サツドラ当別太美店が24年6月に開店した。特徴は店舗内に設けた当別町の「西当別支所」だ。外観は一般的なサツドラの店舗に見えるが、共通の店舗入口から入ると、向かって右にサツドラの売り場、左に当別支所と分かれている。
太美地区は役場庁舎のある地域から10kmほど離れている。地区内の郵便局に出張所が設けられていたが、対応できる内容が限定的で、住民は不便を感じていたという。大型の小売店もなく、車で札幌市に買い物へ向かう住民も少なくないため、地区内の消費が外に流れているという問題意識もあった。
支所の開設によって行政手続きの幅が広がり、もとの出張所と比べて利用者はおよそ1.5倍に増えた。待望の小売店が開店したことで、買い物もしやすくなった。サツドラにとっても、店舗内に西当別支所が入ったことで、町から賃料収入を得られるというウィンウィンの関係を築けた。行政窓口を訪れる人が店舗に寄る相乗効果もあり、サツドラ店舗の売上高も目標を上回る状況が続いているという。

同社の地域戦略の軸である自治体や他社との連携策は、その輪を広げつつある。ヤマト運輸との取り組みや小清水町、当別町への出店などは、いずれも相手からの提案に応える形で実現した。「サツドラなら動いてくれるかもしれない」という期待感から様々な連携の話が各地から舞い込むようになってきたことも背景にある。
同社にはこうした取り組みを推進する専業の担当者がいるわけではない。エゾハブ事業、新規出店など、それぞれの担当者にビジョンが浸透し、現場社員が自律的に動いていることが実現につながっている。
利益率は1.7%、改善が課題

1000億円の大台に乗った売上高だが、内訳を見るとそのほとんどをリテール事業が占めている。インバウンドの動向や販管費などの外部環境に利益が左右される面もある上、営業利益率は1.7%と、収益性の改善も喫緊の課題だ。
「地域が稼ぎ、サツドラも稼ぐ」というビジネスモデルを実現するために、他社や自治体とどうウィンウィンの関係を築けるか。国内でも過疎化の問題が深刻な北海道での挑戦は、同じ課題を抱える国内の過疎地域で持続可能性を高める参考になりうる。
(日経ビジネス 橋本真実)
[日経ビジネス電子版 2025年10月15日の記事を再構成]

|
日経ビジネス電子版
週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。



