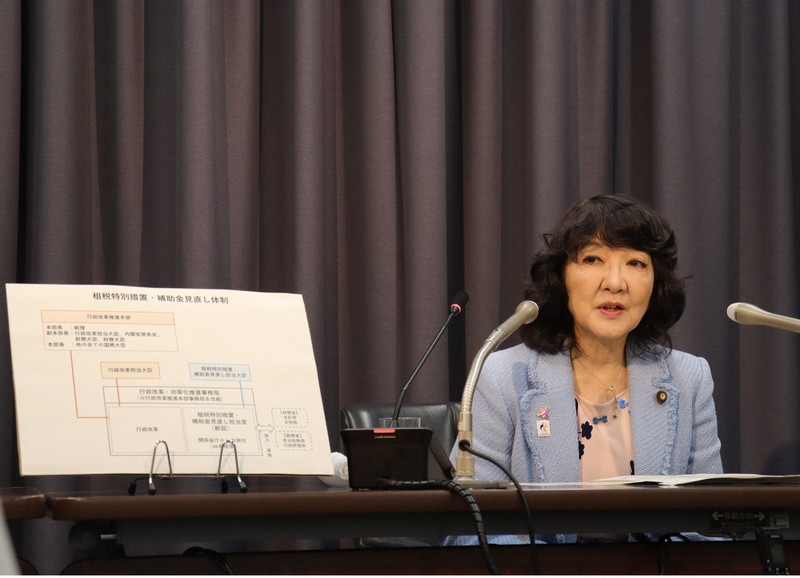
政府は25日、効果の乏しい政策を洗い出し、無駄な歳出を見直すための「租税特別措置・補助金見直し担当室」を内閣官房に新設した。米国で歳出削減に取り組んだ政府効率化省(DOGE)になぞらえて、企業などに向けた減税措置である租税特別措置(租特)や補助金、基金を総点検する。どこまで実効性があるのか注目される。
担当室は、自民党と日本維新の会の連立政権合意書に盛り込まれた「政府効率化局」の構想に基づいた組織で、改組された内閣官房の行政改革・効率化推進事務局内に設置された。関係省庁の約30人が併任して業務に当たり、維新の遠藤敬首相補佐官もメンバーとして参画。査定官庁である財務省や総務省とも連携する。12月上旬にも初会合を開き、具体的な検討作業に入る。
担当相を兼務する片山さつき財務相は25日の閣議後記者会見で、予算・税制に見直しが本格的に反映されるのは2027年度分からを見込むと説明した。一方で「すぐに反映できるものは反映する」とも述べ、一部は来月にもまとまる26年度予算案や税制改正大綱に組み込む可能性を示唆した。政府関係者によると、連立合意で掲げた以上、結果を出す必要があり、ガソリンなどの暫定税率廃止や教育無償化に伴う財源として、租特の改廃を見込んでいるという。
租特は企業などの税負担を軽減し、特定の政策目的を達成することを目指して講じられるものの、「公平・中立・簡素」という税の大原則から外れるなどの批判が絶えない。
財務省によると、法人税の租特による減収額は23年度で2・9兆円程度に上る。このうち賃上げ促進税制(7278億円)と研究開発税制(9479億円)の減収額が大きく、1・7兆円近くを占める。
賃上げ促進税制は、一定の基準を超えて従業員の給与総額を増やした企業の法人税額を控除する。制度ができた13年の日本経済はデフレ(物価の下落)下で賃上げを促したが、現在は物価高の中で一定程度の賃上げが定着した。しかし同税制による減収額は22年度以降大幅増加。財務省は24年度の減収は1・3兆円になると試算する。
研究開発税制は、研究開発をした企業に対し、本来払う法人税額から控除する。財務省によると、適用先はほぼ大企業で、巨額の研究開発費を投じる自動車や医薬品などの製造業で適用額の約8割を占め、減税による恩恵が偏っているとの指摘がある。また、減税額に比べて研究費が増えず、11月に開かれた政府税制調査会(首相の諮問機関)の専門家会合では、委員から「単なる追い銭になっている可能性が高い」などと厳しい指摘が相次いだ。
ただ、自民税制調査会の会合である議員が「将来に向けた研究開発税制について、暫定税率の代替財源として手をつけるのはやめてほしい。将来性がない国だと言われてしまう」と主張するなど制度を支持する声は根強く、どこまで見直しが進むかは未知数だ。
補助金や基金も同様に、特定の分野の政策決定に影響力を持ち、業界関係者から支援を受ける「族議員」を中心に見直しを否定する声は強いとみられ、政府関係者は「補助金や基金を削るのは至難だ」と話す。
大和総研の久後翔太郎シニアエコノミストは「大型の補正予算が見込まれ、財政悪化が懸念される中で歳出面の無駄にメスを入れる意義は大きい」と評価した。その一方で「目標とする見直しの額を表明していないので、実効性をどこまで担保できるかが今後の焦点だ」と指摘。基金については「民間の投資を活性化するために複数年度の予算をつけて予見可能性を高めようとしているところに、政権の価値判断次第で方針がころころ変わってしまえば予見可能性が低下するリスクもある」と述べた。【加藤結花、井口彩、妹尾直道】
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。



