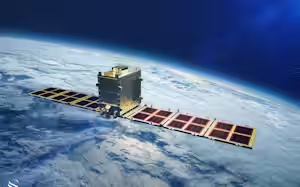地方銀行の2025年4〜6月期の決算が14日、出そろった。連結純利益の合計は前年同期比で12%増の約4300億円となった。金利上昇で利息収入が増えたものの、国債など有価証券の含み損処理で増益幅は縮小した。小規模地銀を中心に減益となる銀行も増えており、金利ある世界で収益力の差が鮮明になっている。
上場する地銀73行・グループの決算を集計した。全体の6割にあたる47社が増益を確保したものの、減益となった地銀も26社と前年同期(14社)から2倍に増えた。増益の主因が、好調な貸し出しや日銀の利上げを背景とした貸出金利の引き上げだ。利息などの資金利益は約1兆1100億円と11%増えた。

米国との関税交渉が続いて企業の投資行動に影響を与える可能性があったものの「設備投資は堅調だった」(しずおかフィナンシャルグループ)という。貸出金は非上場地銀も含めた97行で約325兆円と前年同期から3%増加した。預金のうち貸し出しに回った資金の比率を示す預貸率も78%と2ポイント高まった。預金の増加を上回るペースで貸し出しが伸びた。
量の増加に加え、金利面でも資金利益は押し上げられた。日銀の3回の利上げを受け、各地銀は貸出金利の基準となる短期プライムレートを利上げ前から0.4%引き上げた。貸出金利回りを開示している25行の平均値(国内店舗)は1.34%と前年同期から0.22%上昇した。
資金利益が24%増加したほくほくフィナンシャルグループは、「市場連動の貸し出しを増やしたことで金利感応度が高まった」と話す。貸出金利が0.25%分上昇した群馬銀行も資金利益が35%の増益となった。
本業の改善に比べると、純利益の増加幅は24年4〜6月期の15%増から減速した。重荷となったのは国債などの含み損だ。債券の売却損は約700億円と前年同期から4割増加した。政策保有株など足元の株高を受けて含み益のある株の売却益を約1200億円計上しており、債券の売却損の穴埋めに充てた。
ただ、円建て債券の含み損は25年6月末に約2兆6300億円と1年前に比べ2倍と依然、高水準だ。さらなる市場金利の上昇が進めば「株の売却益を充てながらロスカットのピッチを速める可能性もある」(十六フィナンシャルグループ)といった声もある。
米トランプ関税の影響や足元で増える企業倒産への警戒感から予防的に企業の倒産に備えた引当金を積み増す動きも出ている。与信関係費用は約150億円と35億円の戻し入れ益が発生した前年同期に比べ増加した。与信費用が増加したのは73行・グループ中47社だった。西日本フィナンシャルホールディングスは、関税などに備え予防的に与信費用を増やしている。
含み損や与信費用はとりわけ規模の小さい地銀で影響が色濃い。減益に転じた26社のうち20社は与信費用が増えた。このうち8社は総資産が2兆円未満の小規模地銀だ。
有価証券は含み益のある株の保有が少なく、足元で倒産が増加する零細事業者向けの取引が多いためだ。26年3月期の通期の純利益は地銀全体で1兆3900億円と2期連続の最高益を見込んでいるが、好調さを維持できるかは不透明な側面もある。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。