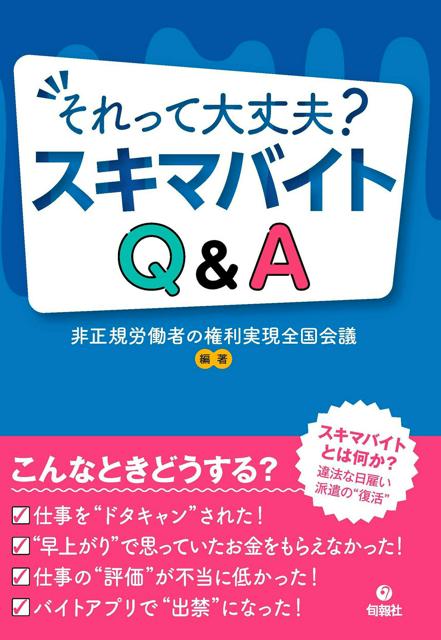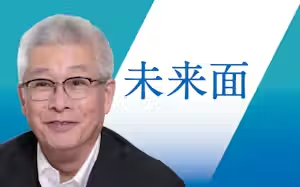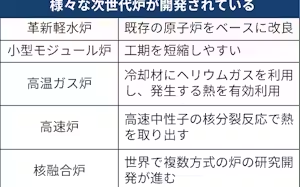野菜価格の乱高下が止まらない。最大手のサラダクラブは3月にカット野菜を創業以来初めて値上げした。今後は需給に応じて価格を動かすダイナミックプライシング(変動料金制)を導入するほか、年内に新商品のテスト販売も始める。新谷昭人社長は「全体の供給網が成り立たなくなるリスクもある」と危機感を語った。
――3月に創業初の値上げを実施しました。
「2024年11月ごろから野菜価格が上がってきた。経験上、相場の高騰はおよそ1カ月で収まると思っていたが、その後も収まらなかった。『何十年に1度』の供給不足が毎年のように起きている。創業から26年間、乱高下があっても、その後の5年は何もないようなことが多かった。現在は待ったなしの状況だ」
「契約産地でも収穫量が少ないと、別の地域の収穫を前倒しして、それでも足りない分を市場で買う必要が出てくる。市場で買うとさらに相場が上がる『負の連鎖』が起きている。収支上でも厳しく、値上げをした」
「キャベツの場合、夏から冬にかけて北から南に産地をリレーして生産していく。従来は気候の影響などを深く考慮しておらず、産地との深い対話が足りていなかったと反省している」
――商品の変動料金制導入を検討しています。
「農家が減ると商品も作れない。経済的にもタッグが組めるような形になることが重要だ。その手段としてカット野菜の価格も変動させることを考えている。詳細は検討中だが、最低1カ月は価格を固定する形で売ることを考えている。野菜価格の乱高下に対応しないと、全体の供給網が成り立たなくなるリスクもある」
――新しいカテゴリーの商品も企画しています。
「単品の野菜をカットした『素材』の商品が伸びる可能性が高い。洗わずに使えて、汎用性の高い商品を年内にテスト販売して、26年春に展開していきたい。新鮮な状態で長持ちする点を訴求する」
――今後取り組みたいことはありますか。
「供給網の連携に取り組みたい。生産者との関係をつくりながら、優先して出してもらえるような関係づくりに取り組みたい。産地情報だけではなく、生育リスクをリアルタイムで把握できる仕組みや、貯蔵方法の研究も進めたい」
「新型コロナウイルスで時代が変わったと言われることが多いが、この業界は供給不足が深刻になった24年末で変わった。カット野菜の加工工場は元旦だけでも休めないか調整している。働き方の改革も含めて挑戦していきたい」
(聞き手は柴田唯矢)
にいや・あきと 97年(平9年)愛媛大学農学卒、キユーピー入社。2024年サラダクラブ取締役などを経て、25年2月から現職。愛媛県出身。最近の趣味はマラソン【関連記事】
- ・キャベツ卸値は昨冬の10分の1 生育良好で葉物が安い
- ・サラダクラブ、減らしたカット野菜を元の容量に キャベツ安定調達で
- ・「物価の優等生」カット野菜、5年で1割高 コスト増響く

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。