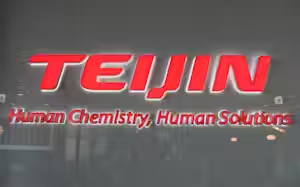“伝説のスポーツカー” 生産終了の日
2025年8月26日、日産の栃木工場には多くの報道陣が集まっていた。「NISSAN GT-R」の最後の1台がラインオフ(生産ラインから出てきて完成すること)すると、会社側から事前にアナウンスされていたからだ。

正午前に「ミッドナイトパープル」と名付けられたカラーの最後の1台が、ゆっくりと姿を現すと、一斉にメディアのカメラが向けられ、集まった技術者や部品メーカーの関係者から拍手が起きた。この車に関わりたくて入社したという技術者も多く、堪えきれず涙を流す人の姿もみられた。
「スカイラインGT-R」の後継車として、2007年に登場した「GT-R」。当時のCEOだったカルロス・ゴーン氏のもと、日産復活の象徴として開発が進められ、強力なV6ターボエンジンと四輪駆動により、日常での移動だけでなく、サーキットでも高い性能を発揮。レースでも実績を残し、世界で高い評価を得た。

エンジンは9人の「匠」と呼ばれる職人が1基ずつ手作業で組み立て、1つ1つに手がけた職人の名前を入れたプレートが取り付けられている。その徹底した品質へのこだわりは、この車を単なるスポーツカーではなく、会社の「シンボル」に押し上げた。
ファンの間からは生産終了を惜しむ声が聞かれた。
「どこまでも走っていたくなるような気持ちにさせてくれる車だった」
「スポーツカーの頂点の車でオーラが違う。スポーツカーの1つの役目が終わった気がする」
規制が技術の進歩を生んだ

2007年に発売された初期モデルと2025年の最終モデルを比べると、見た目は大きく変わっていない。しかし、18年間で中身は大きく刷新されている。それは単に馬力のアップや、走行性能の改善や走りを磨き上げるといったことだけではない。背景にあるのは規制の強化だ。排ガス規制、燃費規制、騒音規制、安全規制…これらをすべてクリアして初めて販売を続けることができるのだ。
例えば、直近で大きなハードルとなったのが「車外騒音規制」だ。
この車の場合、時速50kmで走行したときの騒音を「73dB以下」に抑えることが義務づけられた。これは2メートル離れた位置で聞くセミの鳴き声ほどの音量だ。ドライバーにとっては愛車が奏でる排気音も魅力の1つ。それだけに“静かさ”は高いハードルだった。
そこで開発チームが目を付けたのが航空機のジェットエンジン。そのエンジンの出力のわりには排気音が小さいからだ。ジェットエンジンで使われる排気の流れを分散・吸収する構造をマフラーの内部に導入することで音量を抑えることに成功。一方で、排気の流れを細かく調整することで、アクセルを踏み込んだ時の力強い音質は残すよう工夫したという。
この会社の技術者に話を聞いてみると、この車の成り立ちからして規制が大きく関係しているという。
前身の「スカイラインGT-R」は2002年に排ガス規制への対応や採算性などから生産を終了せざるを得なかった。

その後のモデルの開発では排ガス規制の突破が絶対条件だった。当時エンジン開発に関わった仲田直樹さんは「とにかく早く規制を乗り越えて、性能面の向上に力を割きたかった」と振り返る。検討したのが排気を浄化する装置(触媒)の位置だ。触媒は温度が低いと性能が低下するため、エンジンのすぐ近くに配置し、エンジンの熱ですぐに温めて性能を発揮できる構造を取り入れたという。
こうして排ガス規制をクリアして復活する中で、仲田さんは何よりも「アクセルを踏んだ瞬間に気持ちよく加速する感覚」にこだわった。アクセルを踏めばドライバーの思いのままに力強く加速する。そこで実現した加速時の体感を数値化することで、電動化時代の量産車にも反映させたという。
仲田さんは「これからの世代につないでいきたいのは『努力は夢中には勝てない』ということ。ただ仕事をするだけでなくて、これを何とかしたいみたいなところを技術開発していくと、楽しくなるのではないかと思う。どんな分野であっても言えることだ」と開発のだいご味を語った。
規制に対応 でも値段は…
その一方で、自動車メーカーは車を売って稼ぐビジネスモデルであることは無視できない現実だ。さまざまな規制をクリアするためには開発コストが膨らむ。コストを投じると、販売価格に反映せざるを得なくなる。
2007年の初期モデルの最も安いグレードの価格は税込777万円。しかし、最終モデルは1444万円だ。性能の向上もあるが、18年間で価格は1.8倍余りに跳ね上がった。今後も規制の強化に対応していくと、値段が上昇しかねない。それでも作り続けるのか…。こうした葛藤の中で、会社は生産の終了を決断した。

20年以上にわたって開発に携わってきた松本光貴さんは「開発は規制との戦いでもある。本当は規制ではないところで性能向上に全精力を注ぎたい。しかし、今後も規制は厳格化されていくし、リーズナブルな価格で提供し続けられなくなることが、生産終了の要因だ」と率直に語った。
三菱総合研究所によると、2024年の国産スポーツカーの販売台数はおよそ2万8000台。一概に比較できないが、日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会がまとめた同じ年の乗用車全体の販売台数が約440万台だったことに比べると市場規模は小さい。高性能・少量生産のスポーツカーは投資回収が難しいという。
もちろん規制は理由があって作られている。それはものづくりに取り組むエンジニアにとって挑戦の原動力にもなり、結果的に社会に新たな価値を生むことにもなる。一方で、ビジネスの観点から見れば、開発コストの増加と採算の悪化というハードルを生むことにもなるのだ。
GT-Rの復活は?
では、この車の復活はないのか。イヴァン・エスピノーサ社長は生産終了に合わせて寄せたビデオメッセージで次のように語った。
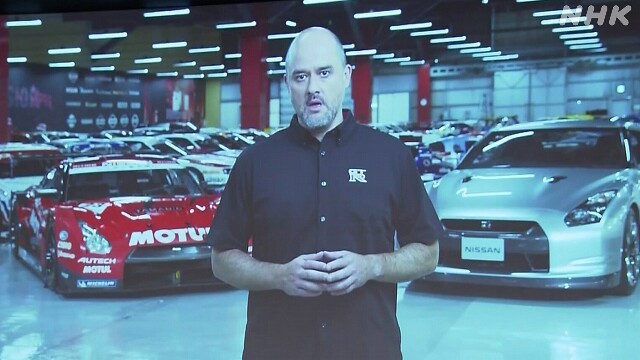
日産自動車 イヴァン・エスピノーサ社長
「R35(GT-R)が自動車産業に決して消えない足跡を残したことに疑問の余地はありません。これは決して永遠の別れではありません。いつか復活させることが、われわれの目標です。皆さんの期待値が高いことは承知しております。どのクルマでも名乗れる訳ではありません。現時点では確定したことはありませんが、GT-Rは進化を遂げ、再び姿を現します。その日まで辛抱強くお待ちください」
日産は2024年度の決算で巨額の赤字に陥り、経営再建を迫られている。世界で7つの工場を削減する方針を打ち出し、国内でも神奈川県の「追浜工場」と「湘南工場」での生産を終了する方針だ。

だが、経営を立て直すには、こうした固定費の削減だけでなく、販売台数の回復に向けた商品力・ブランドイメージの強化も喫緊の課題だろう。規制に向き合って改良し続けてきた開発陣が新型モデルの開発に着手するのかどうかは、スポーツカーファンだけでなく、自動車業界を担当する経済記者にとっても注目すべきテーマと言えそうだ。
(8月26日「ニュース7」などで放送)
西園 興起
2014年入局
大分局を経て経済部
国土交通省やエネルギー、金融の担当を経て
現在は自動車産業を取材
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。