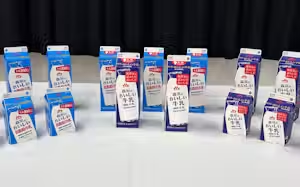福岡市周辺で地価の高騰が続き、価格が手ごろな郊外で住まいを選ぶ人が増えている。職場と住居の距離が近い「職住近接」が市の魅力だったが、都心部は富裕層向けのマンションが増え、庶民は電車やバスで数十分かけて通う街に変わりつつある。
予算6000万円でも購入できず
「電車で30分ほど立ったままです」。最近、筑後地区のとある駅の近くに家を建てた30代男性は苦笑いする。夫婦共働きで、男性は福岡市内の大手企業に勤めている。6000万円を超える強気の予算で駅から徒歩圏内の物件を探した。「子どもと庭で遊べる家」も譲れない条件だったが、庭や間取りの狭い物件ばかり。福岡や隣接の市では満足のいく戸建てやマンションを見つけられなかった。
新型コロナウイルス禍前の2010年代、福岡市の繁華街は終電後も飲み明かす人であふれていた。タクシーで家まで3000円以内や、徒歩圏の会社員も多く、「俺たちの飲み会は終電前に終わらない」と豪語する人もいた。

しかし、この頃から地価は急激に上昇。九州各地から福岡都市圏に人口が流入し、福岡市だけでも年1万人ペースで増加し、日銀の大規模金融緩和や都心部の再開発などで福岡県内外の資金が不動産に向かった。
16日に発表された25年の基準地価(7月1日時点)で、福岡県は前年比プラス3・7%となった。上昇幅はやや鈍化したものの全国5位。上昇は10年連続だ。福岡市の住宅地に限るとプラス7・2%で、価格は1平方メートル当たりの平均で21万8100円。5年前より約5割も高くなった。
男性の会社では、地価が高騰する前に福岡市内で戸建てのマイホームを手に入れた先輩も多い。「時期が数年違うだけで……。言っても仕方ないが、不公平ですよね」と男性はこぼす。
市内では、戸建て1軒分の土地が高すぎて売りにくく、2~3区画に分けて狭小住宅として販売するケースが増加。また、人気の地域では1億円を超えるマンションも続々と登場している。
郊外にタワマン、農村地帯にも注目
こうした中、手ごろな価格でゆとりのある住居を求める人向けに、郊外の宅地開発も加速している。福岡市地下鉄七隈線の沿線では、博多駅から約30分の終点・橋本駅で大和ハウス工業と西日本鉄道が27年の完成を目指して14階建てマンションを開発中だ。大和ハウスは福岡市中心部から約40キロ南のJR久留米駅(福岡県久留米市)でもタワーマンションを建設している。
久留米のタワマンは、70平方メートルの物件で4000万円台半ばから5000万円近くまでと周辺では強気の値付けだが、先行募集した約200戸はほぼ完売した。「地元の富裕層をターゲットとしていたが、福岡市内より格安で、新幹線や在来線で博多に通勤できる点もウケたようだ」と担当者は言う。
北九州市の西部でもJRの特急列車が止まる鹿児島線の駅付近でマンション開発が盛んになっており、不動産鑑定士は「博多への通勤圏として存在感が高まっている」と解説する。
住宅ローン金利も上がっており、住宅の買い控えが目立つ中、割安感のある郡部や農村地帯も注目されている。博多まで片道70分のバスが出ている筑前町は近年、人口増加が続き、近隣の桂川町もJR筑豊線・桂川駅をリニューアルし、「博多まで約30分」をうたい文句に移住をPRしている。
郊外から通勤する人が増え、JR篠栗線の24年度の利用者はコロナ禍前の18年度比で2%増加。リモート勤務の普及や人口減少で多くの路線が利用者を減らす中、異例な状況となっている。JR九州は沿線自治体と協力して街づくりを進めている。福岡市内の鉄道では混雑率が130%超と、首都圏並みの朝の通勤ラッシュが見られる路線も珍しくなくなった。
福岡は都市機能がコンパクトに集積する街として知られるが、ライフルホームズ総研の中山登志朗副所長は「今はベッドタウンが広域化している」と説明。今後についても「福岡市は九州各地や首都圏からの移住先として注目されており、5~10年は地価の上昇が続くだろう」と見込んでいる。【久野洋】
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。