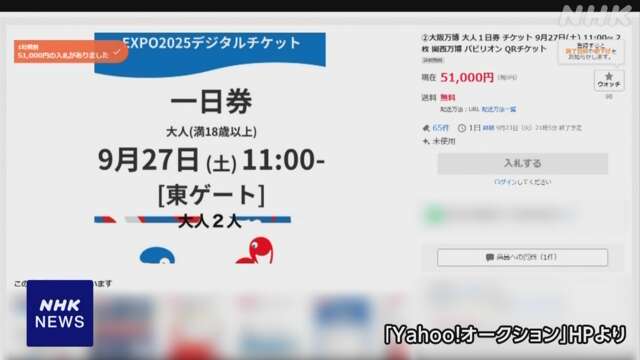グローバル化する世界でますます重みを増す「多様性」。それを雄弁に物語るものが古今の「文化」であり、それらが残した「文化財」だ。大阪・関西万博で9月上旬、世界遺産の法隆寺(奈良)を軸に据えて文化財の未来が議論された。各国が集う多様性の祭典で、それぞれのアイデンティティーを担う歴史遺産の役割と防災を考えた。
法隆寺が完成させた世界遺産制度
内外の来訪者が行き交う万博会場の一角であったシンポジウム「世界遺産 法隆寺と文化財防災の未来」。朝日新聞社と法隆寺が進める「法隆寺みらいプロジェクト」の一環で、朝日放送と共催した。文化財の継承を世界的視点から考えようとの趣旨だ。
「法隆寺は世界遺産の考え方を変えた。文化財を守るにはどうするかを教えてくれている」。元文化庁長官の青柳正規・多摩美術大理事長は、そう語った。
7世紀創建の法隆寺は、世界最古の木造建築として知られる。日本が誇るこの古刹(こさつ)は国内の文化財保護制度の原点であると同時に、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の世界遺産制度を真の意味で完成させた象徴でもある。
1949年、東アジア仏教美術の至宝とうたわれた金堂壁画が焼けた。これを機に文化財保護への機運が高まり、翌50年、文化財保護法が成立。国内の保護体制が整った。
一方、世界では72年に世界遺産条約がユネスコ総会で採択。日本の参加は92年と遅れたが、翌93年に国内第1号のひとつとして法隆寺が登録された。
当時、西洋諸国が主導した同条約は石造建築中心で、アジアやアフリカに目立つ木や土の歴史遺産は軽視されていた。法隆寺登録の翌94年に奈良市で催された国際会議で、木造建築など遺産の性格や成立背景を含む多様性を認める奈良ドキュメントが採択され、国際社会は多文化尊重に舵(かじ)を切った。
つまり、法隆寺の登録がこの潮流に道を開いたともいえるわけで、世界中のさまざまな人類遺産を広くカバーする保護システムの確立を促した〝記念碑〟なのだ。
「人間はほかの動物と違って過去を活用し、未来を映し出せる。文化財を守ることは人間の尊厳を守ることだ。自分の文化を大切にするのは、他の文化を尊重し認めることでもある」。諸文化の相対化は多様性につながる、だからそれを証明してくれる文化財を守らなくてはならない、と青柳さんは説く。
危機に瀕する文化財
だが、文化財を取り巻く環境は相変わらず厳しい。
シンポではイタリアの古都フィレンツェやベネチアで発生した川の氾濫(はんらん)や高潮による歴史的建造物の被災が紹介され、世界的な気候変動との関連も指摘されている。2019年にはノートルダム大聖堂(パリ)や琉球王国が築いた首里城(那覇市)が相次いで火災に見舞われ、不慮の事態に十分対処できているとも言いがたい。
ウクライナとロシア、イスラエルとパレスチナなど各地で勃発する戦争や紛争も多くの文化財をおびやかし続ける。
シンポの副題は「シルクロードの記憶が結ぶ、新たな連携」。が、ユーラシア大陸を貫いて洋の東西をつなぐシルクロード沿線も不穏だ。アフガニスタンの仏教遺跡バーミヤンやシリアの隊商都市パルミラは破壊され、内戦の続くイエメンでも古都が危機に瀕(ひん)する。ユネスコがリスト化する「危機遺産」も少なくない。
このシルクロード東端に位置する法隆寺こそ、「文化の集大成でありタイムカプセル。インドのアジャンターや中国・敦煌の流れとも、金堂壁画は東西文化の融合を表す」と井上洋一・奈良国立博物館長。その安定的な維持態勢の構築は他の寺社はもちろん、国内外の歴史遺産保護につながる。
宗教や信仰心が薄れゆく昨今、法隆寺も伽藍(がらん)や寺宝の維持に苦慮しているのが現実だ。古谷正覚管長は「国の補助があっても負担は大きい。伽藍をどうやって守り、バトンを未来へつなげていけるか。それが課題です」。
「法隆寺みらいプロジェクト」では焼損した金堂壁画の一般公開をめざすとともに、今後クラウドファンディングなどで支援を呼びかけていく。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。