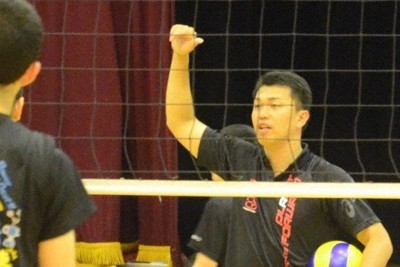今、日本ワインのトレンドのひとつはデラウェアといっていいだろう。
理由はいくつかある。
まず、テロワール。メルローやシャルドネといった国際品種と比べて、日本の気候風土で無理なく栽培できる。
次に、醸造用ブドウとしてのポテンシャル。甲州のように国際ブドウ・ワイン機構に品種登録されず、またグレープジュースのような特有の甘い香りが欧米では敬遠されるといわれ、従来ワイン用品種としての評価は低かった。だが、嗜好の多様化や最近の造り手の醸造の巧みさから、日本では抵抗なく受け入れられている。むしろ「粒が小さく、皮が厚く、糖度と酸のバランスが良いなど、ワイン用ブドウの条件があてはまる」と語るのは、デラウェアによるワイン造りの経験豊富な「島之内フジマル醸造所」(大阪市)、「清澄白河フジマル醸造所」(東京・江東)を営む藤丸智史さんだ。
生食用から醸造用へ転換するデラウェア畑も増えた。後押しするのがワイナリーの増加だ。自園産だけで原材料を賄えず、農家から仕入れるワイナリーは少なくない。その数が増えれば、醸造用ブドウは引く手あまたとなる。
有数の産地である山形のデラウェアを全国のワイナリーが取り合う様相もある中で、注目すべき存在が枝松祐介さんと古内重光さん、若手生産者ユニット「ぶどうと活(い)きる」だ。山形市本沢地区でデラウェアやナイアガラを栽培する。ともに39歳、揃(そろ)って兼業。枝松さんは家業の農業資材販売業に従事し、古内さんは牛肉生産販売会社に勤務しながら、平日の本業前2時間と後の1時間、土日は5時間ずつ、週25時間を畑仕事に費やす。

始まりは2016年。枝松さんが地元農家を回っていた時に、あるおばあさんから「デラウェア畑をやらないか?」と言われたのがきっかけだった。「近々やめる。でも、他界した夫との思い出の畑を潰したくない」。本業があるから無理と思ったが、初期投資ゼロでチャレンジできるチャンスではある。こうして畑が消えていったら、本業が立ち行かなくなるとの危惧も頭をよぎった。「醸造用として育てるなら、兼業でもできるかも」と決断した。
ご存じのように生食用のデラウェアは種なしである。ワイン醸造には、色素とアロマを含む果皮や、タンニンを内包し周囲に酸をまとう種が不可欠なため、種ありで育てる。「種ありのほうが手間は掛からない」と枝松さん。種なしにするためのジベレリン溶液に浸(つ)ける処理が不要なだけでなく、肩落とし、房落とし、粒抜きといった栽培から出荷に至る過程での果実の間引きなど、醸造用に転換することで不要となる手間は多い。「買い取り価格はぐっと下がるが、値段より畑を守りたかった」
温暖化が進む中でのメリットもある。ブドウの成熟には昼夜の寒暖差が欠かせない。日中に光合成をして、夜間の低温時に実は色づく。しかし、ここ数年、夜の気温が下がらず、着色が進まない事態が各地で起きている。「着色不良は、生食用の場合、ランクが下がる。でも、ワイン用なら問題にされない」
むしろ、まだ青い状態で仕込む、通称「青デラ」需要が顕著になってきた。その背景を、フジマル醸造所の藤丸さんは次のように解説する。

「夜の気温が下がらないと、着色不良だけでなく、酸に乏しい締まりのない味のブドウになります。低温下ではブドウが休息状態となり、呼吸が抑えられ、酸の消費も抑制されるのですが、夜の気温が高いとワインに必要な酸が消費されてしまうためです」。ならば、酸のある青いうちに仕込むほうが味わいの輪郭が得られるというわけだ。
枝松さんいわく「青デラは、元はといえば、間引きだった」。温暖化を逆手に取って、ブレンドして酸を補うのみならず、最近では青デラ100%仕込みも登場するまでに。「青デラと完熟の中間、ピンクデラで仕込むワイナリーも。1つの品種で3つの生育カテゴリーを持つほど、デラウェアの活用幅が拓(ひら)かれた」
「ぶどうと活きる」の卸先は全国に広がる。藤丸さんのワイナリーとは17年からの付き合いだ。「國津果實酒醸造所」(三重県)、「ファットリア アル フィオーレ」(宮城県)、新潟県のジャン・マルク・ブリニョさんなど顧客は著名な造り手揃い。地元山形の卸先が「イエローマジックワイナリー」1軒なのは、「山形県本沢をワイン用ブドウ産地として日本中に認知させたいから」と意図は明快。「兼業でも農業を始められるという働き方のモデルケースを示したい」との思いもある。
「それもこれも『農彩土(のうさいど)』のおかげ」とブドウ仲介会社の名前を挙げた。農彩土とは山形産デラウェアのワイン用途の開拓を手掛けた立役者だ。ワイナリーと農家の間に立って受発注と配送を担ってきた。「直接の取引の場合、買い取りや価格が安定しないことも多く、売り先に困る農家もあった。農彩土は全国のワイナリーと連携して必ず買い取ってくれる。青デラ活用も農彩土のアドバイスでした」
ワイナリーに醸造を委託してワインを造るブドウ農家も増えているが、「僕たちは栽培に集中したい」。今では6軒の農家から引き継いだ1.3ヘクタールを手掛ける。育種にも挑戦中だという。栽培者の2人に敬意を表して「ぶどうと活きる」の名前をボトルに記載したり、ワイン名にしたりするワイナリーもある。
「海外から問い合わせが来るんですよ、『この品種、何ですか?』って」
世界的にもデラウェアの価値観に変化が起こるかもしれない。
フードジャーナリスト 君島佐和子
吉川秀樹撮影
[NIKKEI The STYLE 2025年10月5日付]
 【関連記事】
【関連記事】
- ・創刊125年ミシュランガイド、仏グルメ番組とタッグ 影響は?
- ・「キノコのカフェ」誕生 徳島・神山発の地産地消を東京でも
■取材の裏話や未公開写真をご紹介するニューズレター「NIKKEI The STYLE 豊かな週末を探して」も配信しています。登録は次のURLからhttps://regist.nikkei.com/ds/setup/briefing.do?me=S004
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。