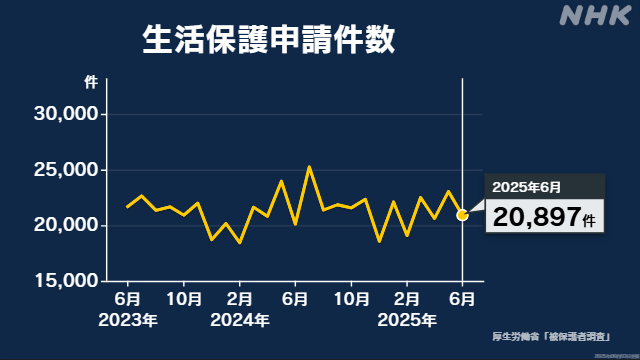体内の不要な細胞を“食べさせる”新たなたんぱく質を開発したと、京都大の鈴木淳教授(細胞膜生物学)らの研究チームが発表した。マウスに投与したところ、がん細胞や自己免疫疾患を引き起こす免疫細胞を取り除くことに成功したという。不要な細胞が蓄積すると、さまざまな疾患が引き起こされるが、選択的に細胞を除去することで新たな治療法の開発につながることが期待される。
人間の体内では毎日100億~1000億個の細胞が役割を終えて死ぬと、「貪食細胞」によって消化、分解されて体内から取り除かれる。しかし、加齢などによって不要な細胞が死なずに蓄積すると、がんや自己免疫疾患などの病気の原因となる。細胞死を誘導するため、化学物質や抗体を使った治療法の開発が進んでいるが、全てを除去することは難しかった。
そこで、生きたままの不要な細胞を直接除去するため、研究チームは死んだ細胞と貪食細胞の橋渡しをするたんぱく質に着目。標的として不要な細胞を認識して結合するように合成したところ、貪食細胞による除去を導くことができた。
研究チームはこの合成たんぱく質を「クランチ」と名付け、皮膚がんの一種「悪性黒色腫(メラノーマ)」を移植したマウスに投与。がん細胞が20~30%取り除かれたことが確認された。また、自分の免疫が誤って正常な細胞や組織を攻撃する自己免疫疾患を持つマウスでも、原因となる細胞が約15%減少した。
研究チームはクランチの実用化に向けてスタートアップを設立し、3年以内の治験開始を目指す。鈴木教授は「幅広い細胞を狙って食べさせることができるのがクランチの強み。既存の治療法と併用することも可能となり、実用化できれば病気の予防にもつながる」と話す。
成果は3日、英科学誌「ネイチャー・バイオメディカル・エンジニアリング」に掲載された。【田中韻】
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。