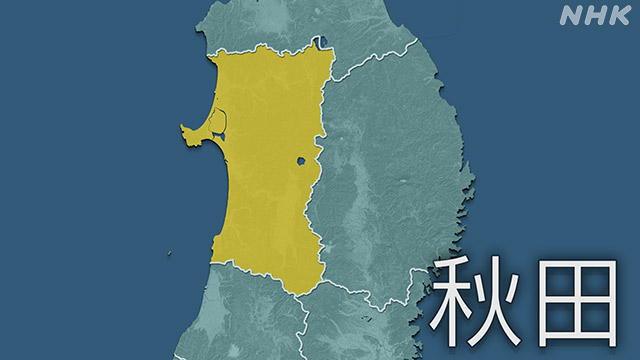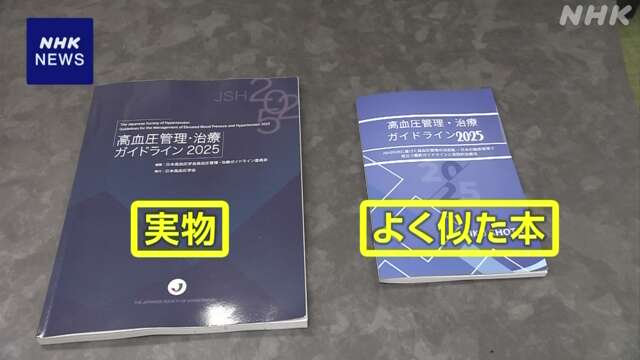小中学校の授業で受精や妊娠の経過について取り扱わないとする学習指導要領の「歯止め規定」の撤廃を求め、性教育に取り組む団体がオンライン署名を始めた。10日夜にはキックオフイベントが開かれ、メンバーは「人権に根ざした包括的性教育を進めて」と訴えた。
文部科学省の有識者会議では現在、小中高校で教える内容の基準を示す学習指導要領について、10年に1度の改定に向けた議論が進められている。現行の指導要領では、小学5年の理科では「人の受精に至る過程は取り扱わない」、中学の保健体育では「妊娠の経過は取り扱わない」と明記している。
これらは「歯止め規定」と呼ばれ、学校の一斉授業で性交については教えないことの根拠とされている。文科省は受精や妊娠について学校の判断で教える際は、保護者の事前の了解などを得た上で、個人や小集団に対する「個別指導」を想定していると説明している。
署名は教員らでつくる一般社団法人「“人間と性”教育研究協議会」(性教協)などが8月25日に署名サイト「Change.org(チェンジ・ドット・オーグ)」で開始した。
「多くの子どもたちがネット上の不正確で暴力的な性情報に触れ、誤った理解を持つことが、性感染症や予期せぬ妊娠、性暴力の被害を拡大させる一因となっている」として、「性教育の内容を狭め、萎縮を招くような歯止め規定は必要ない」と訴えている。
10日のイベントに登壇した元教員で、現在も東京都足立区内の学校で性教育の講師を務める樋上典子さんは「ある区教委の職員には『歯止め規定があるから(性教育は)できません』と言われた。現場は『保護者から文句が来ると怖い』と萎縮している」と指摘した。
文科省の説明については「結局は危険な性行動が発覚してからの事後的な指導にとどまってしまう」として、「性教育がきっかけで性行動が活発になるというのは大きな間違いで、授業後の子どもたちのアンケートや、海外のデータからはむしろ性行動に慎重になることがわかっている」と強調した。
性教育講演や正しい性情報の啓発に取り組むNPO法人ピルコンの染矢明日香さんは「中学校によっては『コンドームのイラストもやめて』という学校もあり、温度差が大きい」と明かす。
歯止め規定ができた1998年を念頭に「LINE(ライン)もTikTok(ティックトック)もない時代の規定が続いている。今は小学生間でも性的画像送信などの性被害が起きており、子どもが信頼できる情報から学ぶことが大切だ」と訴えた。
教育評論家の尾木直樹さんは、名古屋市や横浜市などで教員による子どもの盗撮被害が相次いで発覚していることを挙げ、「子どもだけではなく、教員や保護者、子どもに関わる大人が正しい性の知識を学んでいないのは決定的な弱点だ」と語った。
署名は10日までに2万1600筆超に上る。11月中に文科省に提出するという。【西本紗保美】
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。