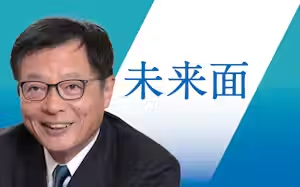年収は上昇傾向
アニメ産業の労働問題が表面化したのは、15年ほど前からだ。2009年に「日本アニメーター・演出協会」(JAniCA)が実態調査を基にまとめた「アニメーター労働白書」を契機に、アニメーターの長時間労働や低収入が社会問題として顕在化した。
同白書では、現場の作画担当者(アニメーター)の職種の一つである動画職において、平均年収が約110万円との調査結果が公表され、世間の注目を集めた。筆者は、2013年ごろからアニメ産業の労働現場でフィールドワークを行っている。本稿では、現時点のアニメ産業の働き方の動向と今後の課題について見取り図を示したい。
まず、現状では、基礎的な労働条件に改善傾向がみられる。2023年の「アニメーション制作者実態調査報告書」(JAniCA)では、動画工程の平均年収は263.2万円に上昇、作画工程の中で一番人数が多い原画工程では399.8万円。(アニメーター、監督、脚本家、プロデューサーを含む)アニメ制作者全体の平均は455.5万円で、同年の給与所得者の平均年収の460万円(国税庁「民間給与実態統計調査」)と同水準だった。
待遇改善の背景としては、映像のクオリティー向上志向の中でアニメーターの獲得競争が起きていることや、働き方改革関連法の影響などが指摘されている。近年の製作費高騰は、人件費の増加が一因であるようだ。こうしたアニメ制作市場の動向や法制度の影響についても論ずべきことは多々あるが、ここでは、近年のアニメ産業で起きている変化に焦点を当てる。
フリーランスと雇用労働
アニメーターの労働問題を検討する際、アニメ産業固有の労働問題を論ずる以前に、自営業やフリーランスといった企業に雇用されない働き方を巡る労働問題の存在が前提となる。
JAniCAの調査では、年によって若干数字にぶれはあるが、自営業あるいはフリーランスとして働く制作者の割合は5割から7割程度となっている。日本の有業者に占める自営業の割合が7.6%(総務省「令和4年就業構造基本調査」)であることを踏まえると、アニメーターは雇われずに働く割合が顕著に多い職種といえる。2025年3月公表の「フリーランス白書」(フリーランス協会)によると、年収400万円未満の人が47.2%と約半数を占めた。そもそも自営やフリーランスは、就業条件が雇用に比して不利な状況にあり、アニメーターも例外ではない。
労働問題の研究者には、自営やフリーランスが収入や社会保障の面で不利な以上、雇用労働の側に包摂していくことが解決策だとする考え方が多い。確かに、雇用して労働関係法の下で労働者の権利を守ることは、労働環境改善のための最も基本的な在り方だ。実際、後述するように、アニメ業界では自社雇用が増えている兆候がある。
ただし、日本社会の雇用慣行が、過労死をはじめさまざまな労働問題を引き起こしてきたことを考えると、雇用以外の働き方が維持できる社会であることが望ましい。筆者自身は、フリーランスが持続的に働ける環境を維持する仕組みを同時に模索するべきだと考える。
「内製化」と結び付いた雇用への動き
東京に集積するアニメ制作会社の大半は、一部の工程に特化した小規模企業(下請け・専門スタジオ)だ。しかし、2010年代には、アニメ産業において「内製化」、つまり制作工程の大部分を一つの制作会社の内部で完結できる体制づくりへの模索が始まっていたとの指摘がある(※1)。デジタル化などを背景に工程特化型専門会社の収益が悪化したことや、直接制作を受託・完成させる能力を持つ元請制作会社が外注費の節約を図ったことなどが背景にある。実際、近年はM&Aなどを通じた企業統合が進行しているようだ。
こうした内製化への動きは、雇用労働を促進する効果があった。一般に、一つの企業内で商品やサービスをつくり続ければ、その企業独自のノウハウが蓄積していく。そのノウハウを継承し企業の強みにしていくために、雇用労働者を長期的に育成しつつ活用するインセンティブが働く。実際、日本企業では新卒一括採用からの長期的な人材育成が制度化してきた。
現時点では、内製化の動向に伴う労働力構成の変化や、具体的な労働条件の変化を体系的に捉える調査はない。だが、筆者が調査研究のなかで出会う若手アニメーターにも正社員として働く人が増えている印象がある。また、2023年のJAniCAの調査でも、自営・フリーランスが47.3%と、19年調査の69.6%から低下していることから、実際に雇用労働力への包摂が進んでいると思われる。前述の平均年収の改善は、内製化の動きに雇用が結び付いた結果と考えられるだろう。
小規模スタジオの持続性が課題
内製化を通した雇用への動きは、雇用労働を対象とした労働法制のもとにアニメ制作者が保護される度合いが高まることを意味し、指摘されてきた低収入や長時間労働の改善には寄与するだろう。
一方で、内製化が進めば、アニメ産業内での大企業と中小企業の間で労働条件の差がますます広がる可能性がある。元請制作会社や大手エンタテインメント企業、プラットフォーマーの資本力のもとに内製化が進行しても、小規模制作会社が消えるわけではないからだ。
小規模の会社が全て大手に統合されれば解決するという考え方もあるかもしれないが、そう単純ではない。アニメのように、クリエイティビティや作家性が重視される業界では、大手で活躍した後に独立して小規模のスタジオを起業したり、フリーランスになったりする人たちがいる。そこで継続的に働ける環境がなければ、アニメ産業の持続性という観点でも、多様な作品を楽しみたい消費者からみても、望ましい結果とはならない。アニメ業界では、これまで小規模のスタジオからも柔軟な発想や斬新な手法が生まれてきたからだ。
また、アニメ産業で進行している地方展開についても、今後働き方に関する課題が生じ得る。元請制作会社が地方に支社を設置する動きは以前からあるが、近年は(アニメーターや監督など)制作者が地方圏に移住してスタジオを設立する動きが目立つ。今後、アニメ制作に携わりたいが東京への移住が難しい若者たちの受け皿として機能する可能性がある。
小規業スタジオにおける労働問題に対応する指針が必要であるとともに、こうした地方スタジオをどう支援するかも今後の課題である。
フリーランスの連携を支援する仕組み
これまで述べてきたように、フリーランスや下請け、小規模スタジオの労働環境の改善は、中長期的に取り組むべき課題である。具体的に、どんな方策があるだろうか。
筆者はまず、フリーランスが孤立しないようにコミュニティー形成を促し、そのネットワークを支える仕組みを作ることが重要だと考える。個人として働くことがイメージされがちではあるが、実際にフリーランスが働きやすい条件を整えるには、フリーランス同士の連携が欠かせないからだ。特に、アニメーターがフリーランスとして長期的なキャリアを形成するには、仕事に関する情報収集や、スキル向上につながる相互扶助のコミュニティーの存在が必要だ。
労働組合の中央組織である連合は、フリーランス支援の一貫として、「アドバイザリーボード」や「フリーランスサミット」の開催など、フリーランス同士が自ら直面している問題を共有し解決策を模索するプラットフォームづくりに力を入れ始めている。アニメ業界に即して言えば、業界で経験を積んだアニメーターなどが「私塾」を開いたり、交流会を開催したりしている。こういったネットワークづくりの取り組みを支援するために、自治体などが助成する仕組みがあってもいいのではないか。
「フリーランス新法」を改良
日本に限らず、雇用と自営・フリーランスでは受ける社会保障に大きな差がある。それでも、海外には自営やフリーランスにも雇用労働者と同様に雇用保険(失業保障給付)を適用する国もある。また、2024年に施行された「フリーランス新法」では、報酬額に関する規定がないなど、フリーランス保護の法制度としてはまだ改良すべき点が多い。フリーランスを巡る労働法政策の改善は、アニメ産業にとってもプラスに働く。
「基幹産業」を支えるアニメーターたちのさらなる労働環境向上のためには、雇用と自営・フリーランスの待遇や社会保障における格差改善への取り組みに力を入れるとともに、アニメ産業内で起きているさまざまな変化を冷静に捉えた議論が必要だ。
(※1) ^ 半澤誠司『コンテンツ産業とイノベーション』(2016年)参照
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。