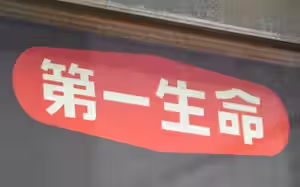みやぎ森林・林業未来創造機構などは16日、宮城県林業技術総合センター(同県大衡村)で林業関係者が交流するイベントを開催した。安全な伐倒作業のノウハウや新規就業者の確保に向けた取り組みが共有された。プログラムを通して得た知見を各事業者の経営や施策に活用してもらい若者に選ばれる林業を目指す。
「みやぎ森林・林業未来創造カレッジ 2025オープンカレッジ」が開かれ、林業従事者や自治体関係者など約70人が参加した。「これからの林業事業体経営」をテーマに、若い世代が魅力に感じる林業のあり方などについて意見を交わした。
冒頭ではカレッジの伐倒技術指導者養成研修の受講者がチェーンソーを用いた作業を実演。木を狙った方向に倒すための受け口(V字型の切り込み)の作り方や伐倒時の姿勢などについて、安全を確保するノウハウを披露した。
林業では労働災害の多さが課題となっている。林野庁によれば1年間の労働者1000人当たりに発生した死傷者数の割合は全産業の中で最も高い。2024年に全産業で2.3だった一方、林業では23.3と10倍の水準だった。
足場の悪い山中でチェーンソーを使って重い立木を伐倒する作業は危険を伴う。宮城県では24年に作業者が死亡する事案が相次いだことをうけ、伐倒作業の実演を冒頭に設定した。宮城県林業技術総合センターの向川克展所長は「林業を選んでくれた若者が安心して働けるよう、経営者には安全をより意識してほしい」と話した。

午後には基調講演として栃毛木材工業(栃木県鹿沼市)の関口弘社長が若手社員の確保と教育について話した。週に1度の安全会議で事故につながりかねない「ヒヤリハット」の経験談を話すように社員に促し、安全意識を高める取り組みが紹介された。参加者からは所有山林の拡大方法など多くの質問が寄せられた。
宮城県内の2つの事業者は林業の価値や獣害対策について共有した。鎌田林業土木(宮城県加美町)の鎌田渉社長は「水源保持など公益的な意義は目に見えづらい」として、周知の必要性を訴えた。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。