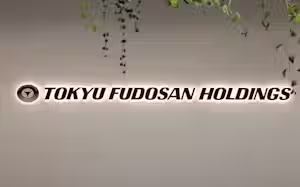堺市は4日、中心市街地で10月から実験中の自動運転バスについて、報道各社向けの試乗会を開いた。路上駐車に遭遇するたびにドライバーが手動で回避しなければならず、その時間は全体の約半分にのぼった。車や人通りが多い都市部で自動運転を実現するための課題が垣間見えた。
堺市が計画している自動運転バス「SMI都心ライン」は、南海電気鉄道の堺駅と堺東駅を結ぶ幹線道路(往復3.4キロメートル)を走る。2027年度までに一部区間で、運転手が介在しないレベル4を目指している。今回の実験は、状況に応じて運転手が操作するレベル2で、26年2月まで実施する。

試乗時は荷下ろしや休憩のための路上駐車が目立ち、自転車が車道の中央を走る場面もあった。自動運転バスはそのたびに運転手の手動操作に切り替え、センターラインをまたいで回避した。「自動運転は道路交通法にのっとって設定されており、ラインの内側で立ち往生する恐れがある」(交通政策課の甲野純課長)
交通量の多い都市部は道交法の緩やかな運用で成り立っているケースがあり、自動運転が厳格運用を前提としている限りなじみにくい。市は今回の実験で、道幅を1メートルほど広げて車1〜2台の片側半分が収まるスペースを2カ所つくったが、路上駐車がその範囲にとどまるかは不透明だ。
永藤英機市長は同日の定例記者会見で「実験結果はすべて国土交通省に報告し(道交法の運用も含めて)議論したい」と語った。路上駐車の削減に向けて、市民の協力も必要になりそうだ。
(高橋圭介)
【関連記事】
- ・堺市の自動運転バス、本格運行へ前進 国の補助金で3年ぶり実験
- ・ニューモと堺市、自動運転タクシーで連携協定 レベル4めざし実験

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。