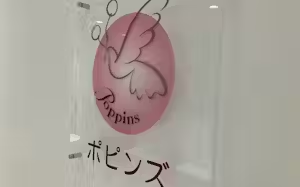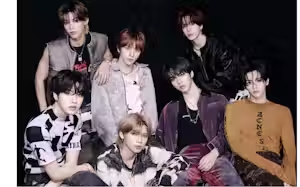国の借金である国債の返済のための国債費が膨張している。2026年度予算の概算要求で財務省は過去最大となる32兆3865億円を見込んだ。
「驚いた。こんなに上がるなんて」。財務省の担当者が気にするのは足元の長期金利の上昇だ。27日には代表的な指標となる新発10年物国債の利回りが一時1・63%まで上昇(債券価格は下落)した。
金利上昇は、国債の利払い費を算定する際の「想定金利」に影響する。財務省は足元の金利水準に、過去の急騰時を参照しリスク分として約1%を加味して算定しており、26年度予算の概算要求では2・6%まで上昇した。その結果、利払い費は25年度予算比24・0%増の13兆435億円を見込む。
利払い費の増加は段階的に進むのも特徴だ。国債の発行残高は1100兆円超となっており、過去に低利で発行したものの償還期限が来ると、現在の金利水準の国債に置き換わる。
財務省は4月、26年度以降に金利が想定よりも1%上昇した場合、利払い費は27年度で2・1兆円、34年度に8・7兆円増えるとの試算を公表した。財務省幹部は「国債残高を減らさなければ、金利上昇の影響を受けるリスクが高くなる。国債費の歳出に占める割合も増えると、予算を組むための自由度も低下する」と危機感を示す。
金利上昇の要因は、日銀による利上げや国債買い入れの減額といった金融政策の変更だけではない。日本の財政悪化に対する懸念の広がりも大きく影響している。
与野党で協議が進むガソリン税の暫定税率の廃止によって税収が減ったり、秋の臨時国会で物価高対策や米国の関税措置への対応を盛り込んだ大型補正予算が組まれるなど歳出拡大圧力が強まったりすれば、更なる金利上昇を招き、利払い費の増加も加速しかねない。【加藤結花】
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。