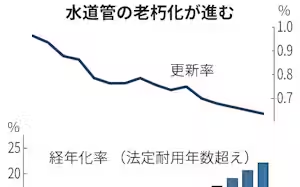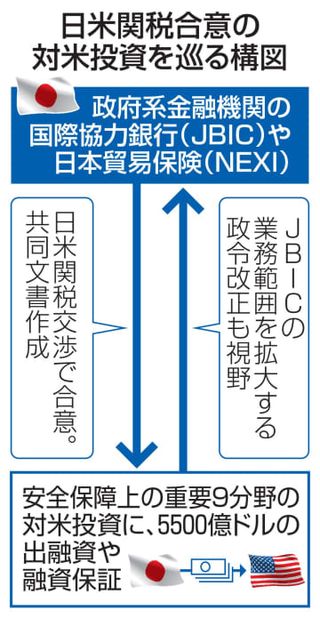中国40都市に192カ所の倉庫
2016年設立のOnedot(ワンドット、東京・文京)という日本のスタートアップは、中国でペット用品の電子商取引(EC)「Petnote(ペットノート)」を提供している。ほとんどの従業員が上海の子会社「万粒(ワンリー)」に所属する。
ペットノートはフードやおやつなどのペット用品を仕入れて都市部にある自社倉庫に在庫を置く。25年4月時点で中国40都市に192カ所の倉庫を持つ。利用者から注文が入った場合、「美団」などの出前サービスの配達員が注文から30〜60分間で自宅に届ける。
Onedotは日用品大手のユニ・チャームの新規事業が創業のきっかけとなっている。支援していた米ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)の鳥巣知得氏がOnedotの代表に就任し、ユニ・チャームの子会社として事業を始めた。20年に東京大学協創プラットフォーム開発(東大IPC、東京・文京)などの出資を受ける形でカーブアウト(事業切り離し)した。

ペットビジネスは「日本に強み」
なぜ中国でペットビジネスなのか。鳥巣氏は「日本のペット市場は50年の歴史がある。意外と気付かれていないかもしれないが、世界に出てみるとペットビジネスは日本に強みがある産業であることがよく分かる」と話す。
フードやペットケア用品の使いやすさ、品質面だけではない。スーパーやホームセンター、ネットで欲しい商品がすぐに手に入るというユーザー体験を含め、企画開発や生産、流通の仕組みが成熟している。
日本では1980年代から90年代にかけて第一次ペットブームが起きた。ペットが家族の一員となり、フードやおやつから産業が発展した。その後はさらに動物病院のような医療、保険商品などにビジネス領域が広がり、最近では介護や葬儀といった事業を展開する企業もある。
一方で中国は、空前のペットブームの最中にある。中国の調査会社「iiMedia Research」は2025年の市場規模が8114億元と23年比で37%増えると予測する。英調査会社のユーロモニターなどによると、中国のペット頭数は22年に合計で約2億2000万匹と日本人の人口よりも多い。
過去5年でペット市場が急速に盛り上がった中国には、ペットケアのバリューチェーンが存在しなかった。都市部で暮らす住民がペットをかわいがり、ときには人間以上にお金を投資するというカルチャーそのものが希薄だったと言っても過言ではない。

日本発ソフトパワーに注目
Onedotはこうしたペット用品の流通の仕組みや新たな生活様式に目をつけ、日本企業ながら現地最大手の一角に育った。「作っている製品そのものを輸出するのではなく、ペットケアの文化を輸出する」と鳥巣氏は話す。
「ソフトパワー」という言葉がある。米ハーバード大学教授やクリントン米政権の国防次官補などを歴任し、外交・安全保障分野で米国を代表する研究者として知られたジョセフ・ナイ氏が提唱した言葉だ。軍事力や直接的な経済力ではなく、価値観や文化を共有することで他国に対して影響を及ぼす考え方を指している。
自動車などの製品を輸出することで成長してきた日本だが、実はこうしたソフトパワーとして文化を輸出することの重要性が増してきている。日本でいえばアニメや漫画のようなコンテンツ、和食、禅のような伝統が分かりやすい。
一方、ペットケア以外にもマンガ喫茶など日本の中で培われてきた独自の文化はまだある。もはや日本人にとってみれば取り立ててイノベーティブには思えないこうした業態も、場所が変われば一気に大きな注目を集める可能性があるかもしれない。現地のニーズに合わせてうまくローカライズすることでより受け入れられやすくなる。
(杜師康佑)
次回は9月7日に公開します。
- ㊤水だけで洗える皿はどう生まれた? WHYから始めるデザイン思考

この書籍を購入する(ヘルプ): Amazon楽天ブックス
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。