
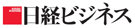
「成長戦略の中に再び技術戦略が描かれ始めた」
東芝は2025年5月、社内向けに新しい成長戦略を発表した。中身を外部には公表していないが、足元の業績改善を受けて中長期も見据えた戦略として社員に説明した。その中で短期、そして中長期ともに技術を基盤にいかに成長していくかというストーリーが描かれた。最高技術責任者(CTO)の佐田豊上席常務執行役員はその内容に確かな手応えを感じた。
東芝の成長の源は常に「技術」だった。源流となる芝浦製作所を興した田中久重氏は「万般の機械考案の依頼に応ず」との看板を掲げ、技術立脚を鮮明にした。サーバーやパソコンの長期記憶を担うNAND型フラッシュメモリーや日本語ワープロなど世界初・日本初の機器は、東芝の躍進を支えてきた。ファンド傘下で再建を進める中、再び技術で光る会社へと転換させようと狙う。
技術の復権を目指す東芝の象徴として33年ぶりに復活させたのが、総合研究所だ。先端研究や基盤技術などを担ってきた研究機能と、一部の事業に直結した開発を担ってきた組織を25年4月、総合研究所に集約した。「研究が東芝にとって一つの競争力の源泉ということを社内外に示す」と佐田氏は意気込む。
複雑さを増す社会課題解決に必要だった総合研究所
複数の技術分野を同じ総合研究所の傘下に置くことで、技術の融合を促進する。背景には、社会課題が複雑さを増していることがある。
例えばエネルギー部門でいえば、以前は単に機械やプラントを発注者に納入すれば成長できた。だが今は省エネや電力制御といった技術までカバーする必要がある。「以前より業界ごとの境界が曖昧になった」(総合研究所長の落合誠氏)。社会課題解決には複数の技術の組み合わせや融合が「必然となった」(同)のだ。
東芝には、事業部門の枠を超えて技術を持ち寄り実用化した、成功体験がある。半導体ウエハーに回路パターンを転写する、「マルチビームマスク描画装置」だ。
26万本の電子ビームを基板に照射し回路を描く同装置。同じ数だけのシャッターを使ってビームを通したり遮断したりして回路を形成する。電子ビームの制御やシャッター部品の堅牢(けんろう)性など様々な課題が浮かび、装置を担当する子会社のニューフレアテクノロジーの前にはいくつも壁があった。
乗り越えた原動力は、画像解析や回路設計、メカトロニクスなど様々な他部門の技術の結集だ。実用化にこぎ着けた装置は効率性の高さを売りに販売を伸ばしている。
複数部門の技術が融合することで新しい価値を生み出す利点を、強さへと昇華するのが総合研究所の役割だ。融合を誘発する仕組みづくりとして、研究者が研究内容を説明するポスター発表会を定期的に実施。参加には上司の了承などはいらず、自由な意見交換の場として活用される。
連携するのは、社内だけではない。外部連携に向けて東芝は2024年、川崎市に「イノベーション・パレット」という研究開発施設を開いた。執務スペースと交流スペースを分け、外部の人も入りやすい場所を用意。オープンイノベーションの加速に向けた体制づくりを進める。
研究開発施設や総合研究所の新設という目立つ取り組みの裏で、重要な改革も断行した。「人によってはストレスがかかった」(佐田氏)というのが、研究予算の決定プロセス改革だ。
研究テーマに本社・事業部の意向を反映
東芝の研究部門は非常に自由度が高いことが特徴だった。研究計画の策定においては、これまでも事業部や本社の意向も聞いていたが、研究部門の意向が強く反映されてきた。その結果、「実用化できない研究が多くあった」(同)。
成果が出ても社会実装されない研究に注力した結果、本来必要な研究が遅れていた可能性も否定できない。25年度から研究予算の半分を本社や事業部と擦り合わせたテーマに充てることで、そんな投資対効果の改善を進める。

25年度予算の検討が始まった24年夏。研究部門と事業部の会議は、「まず、出だしの議論からかみ合わなかった」(同)。研究者の提案したテーマが厳しく糾弾されることも、一つや二つでは済まなかった。それが大きなストレスになっているという声は、技術トップの佐田氏にまで複数届いた。
佐田氏は「研究の成果が出てから(実用化できないという)ストレスがかかるか、初期からストレスがかかるかの差」と説明し、研究者らに意識変革を求めた。
「バランスの問題だ」
総合研究所長の落合氏は「バランスの問題だ」と話す。これまでの研究部門の良さだった自主的な研究テーマをゼロにするわけではない。革新には、自主的な研究活動を奨励する「机の下活動」のような文化も捨てられない。短期的な収益貢献を含む事業部に寄り添った規律ある研究と、長期の柱につながるイノベーションを生む自由度を両立できる仕組みの構築を目指す。
東芝は25年3月期、経営再建の一環として固定費削減に取り組んだ。研究開発予算ももちろん対象となり、実用化に時間のかかる案件などは大きく影響を受けた。
佐田氏は「(東芝の非公開化を主導した投資ファンド)日本産業パートナーズは、東芝の技術を理解してくれている」とし、「特定領域では研究開発予算が足りていないという認識は経営陣にあり、成果を出せば増える可能性がある」と話す。短期的な成果が、長期的な研究開発力を担保することにつながる。
かつて日本企業は製造業を中心に各社が中央研究所を持ち、商品化に時間がかかる基礎研究から自前で手掛けてきた。1990年代以降は効率性を求めて商品化に近い開発機能を残し、シーズとなる研究は大学やスタートアップなど外部に任せる動きが広まった。東芝が総合研究所を廃止したのも、その頃だ。
足元では外部連携に向けて目利きをするにも研究視点が必要と見て、揺り戻しの動きもある。東芝は短期も長期も見据えた新しい総合研究所の姿を描けるか。これからの研究機能の在り方を示す試金石になるかもしれない。
(日経ビジネス 岩戸寿)
[日経ビジネス電子版 2025年7月29日の記事を再構成]

|
日経ビジネス電子版
週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。



