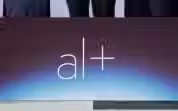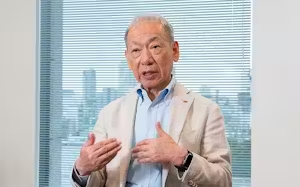東邦ガスや名古屋大学、東京大学などが共同研究する大気中の二酸化炭素(CO2)の回収技術が実用化に向けて本格的に動き出した。通常はCO2を吸収した専用の液体を高温で加熱し分離するが、今回の回収技術ではドライアイスを用いて熱源なしで回収する。熱源が不要なため従来よりエネルギー使用量を6割減らせる。大阪・関西万博で披露し、注目を集めている。
東邦ガスなどが実用化を目指すのは、大気からCO2を直接回収する「DAC(ダイレクト・エア・キャプチャー)」技術のひとつだ。大気中から吸収したCO2をマイナス160℃ほどに冷却し、ドライアイスにする。通常はCO2を回収した吸収液を高温で温めて分離させる。燃料コストがかかる上に、加熱時のCO2排出が課題だった。
CO2体積が800分の1に
東邦ガスなどが手掛ける手法は液化天然ガス(LNG)を気化させる際に発生する冷熱を用いる。冷熱でCO2を一気に冷やすことでドライアイスにする。ドライアイスになったCO2は体積が800分の1ほどに減るため、装置の中の圧力が急激に下がりCO2を取り出すことができる。
大阪・関西万博で名大が実証施設を開設し、LNGの替わりに液体窒素を用いた。これまでは室内での実験が多かったが屋外の空気を装置に取り込む。空気の温度や湿度、CO2濃度などは天候により左右するため、万博での実験を通じあらゆる条件下でより多くのCO2が回収できるよう工夫する。

これまで小規模プラントでの実験を進めてきており、実用化に向けて早ければ2030年にもスケールアップした実証に取り組む。小型の試作機と東邦ガスが作成したシミュレーターを使い、大型のプラントにする際の課題を分析する。
現状は高さ2メートル、幅4メートルほどで年間1トンのCO2を回収する規模だが、さらに吸収の効率を高めるためにはどういった構造が望ましいかなどを研究する。液の量を増減させた際の消費エネルギーの量を比較したり、ドライアイスをより多くつくることのできる冷却温度を分析したりといった実験も想定する。
エネルギー使用量6割減目指す
実現すれば従来の手法より、CO2回収にかかるエネルギー使用量を60%削減できる見込み。政府の大型プロジェクト「ムーンショット型研究開発事業」に選ばれており、最長29年度まで研究にかかる費用は国が全額負担する。

東邦ガスは再生可能エネルギーや海外事業を戦略分野に掲げ、北米で次世代の脱炭素ガスとされるeメタンの量産にも乗り出す。22年には愛知県知多市と共同でCO2と水素からメタンをつくる「メタネーション」技術の実証試験を始めると発表した。
CO2の分離回収技術が確立できれば、将来的にeメタンの製造にも寄与する。28年3月期までの中期経営計画では30年度にeメタンなどの導入量を1%以上にする目標を掲げる。東邦ガスの担当者は「先行技術より高効率なCO2回収設備の構築を目指す」と語る。
(梅野叶夢)
【関連記事】
- ・東邦ガス、地震時のガス供給訓練 移動式設備で
- ・東邦ガス4〜6月、純利益22%増 期ずれ差益が拡大

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。