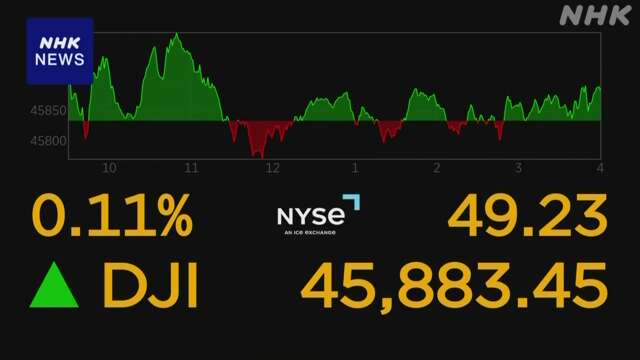手紙が好きだ。記者時代には前日会った人に礼状を書くのを日課にしていた。書くことで人物の記憶が定着する効果もあった。
それだけに北欧デンマークが、年内に郵便ポストを全て撤去するとのニュースに感慨を禁じえなかった。手渡しによって人と人をつなぐ役割を担ってきた郵便制度は貴重だが、デジタル社会の進展に伴う手紙の急激な減少は、否定できない。われわれが当然と思って享受している「全国一律公平なサービス」は今、岐路に立たされているようだ。
東京・大阪間で明治4(1871)年に郵便事業を始めた日本に比べ、デンマーク郵便の歴史ははるかに古く、1624年にさかのぼる。当時の国王クリスチャン4世は、宗教戦争「三十年戦争」(1618年~48年)を戦うに際し、指令を効果的に伝達する体制確立を目指し、9ルートを開設したのが起源とされる。
当初こそ上流階級の利用に限られていたが、1849年の立憲君主制移行で民主化が進み、郵便の需要も急拡大。どこでも公平にサービスが受けられることを法律で保障する「ユニバーサルサービス義務(USO)」に支えられ、1990年代後半には利用がピークを迎えている。
デンマークは今、「最もデジタル化が進んでいる政府」のランキングで常に上位を占め、スマホのアプリ「デジタルポスト」(電子私書箱)によって自治体と国民との連絡がオンラインで完結する体制が整えられている。
このためデンマークとスウェーデンが共有する政府系郵便会社「ポストノルド」のデンマークにおける手紙配達量は、2000年の14億5000万通から昨年は1億1000万通に9割以上減少し、採算が取れなくなってしまった。デンマーク政府は昨年1月に郵便法を改正してUSOを終了。「ポストノルド」は年内で手紙の配達業務から撤退し、増える一方の小包配達に専念することを決めるに至った。
来年からは民間の新聞配達会社「デオ」が手紙の配達も請け負うことになり、郵便ポストに代わって全国1500か所のデオ・ショップが配達を受け付ける。1通29デンマーククローネ(約650円)の配達料金は23デンマーククローネ(約510円)に値下げになるという。
欧州では1997年ころから市場開放の流れが加速し、コストのかかる遠隔地・過疎地への配達サービスが敬遠されるリスクが表面化、これを防ぐためUSOが導入された経緯がある。デジタル化が浸透するデンマークと異なり、他の欧州諸国では採算の悪化する郵便配達業務を前に、消費者の権利保護の核となるUSOとどう折り合いをつけるのかが、課題として立ちはだかる。
英国では郵便配達を担う旧政府系企業がチェコの実業家に買収され、平日は隔日配達になり、フランスでも利用頻度の低いポストを撤去し、土曜日配達廃止の議論が進むなど、USOは正念場を迎えている。
郵便物の減少は日本でも顕著だ。ピーク時(2001年度)に263億通あった郵便物は昨年度125億通と半減。2007年に民営化されてから約20年が経ち、全国2万カ所の郵便局、17万本の郵便ポストを何とか維持してはいるが、2003年の調査では1カ月にゼロか1通しか投函されなかったポストが6800本に達するとのショッキングなデータがある。
しかも日本郵便が配達員の点呼を適切に行っていなかった問題で、6月に拠点間の輸送を担う郵便用トラック2500台が5年間使用停止処分を受けたのに続き、来月からは配達用の軽バンの一部使用も制限される。
送信ボタンを押せば瞬時に届くメールと異なり、人の手を経て届けられる手書きの文字には温かみがある。タイパが重要視される時代だからこそ、手紙は必要に思える。日本の街角の赤いポストが、デンマークのように消える日がくるのだろうか?
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。