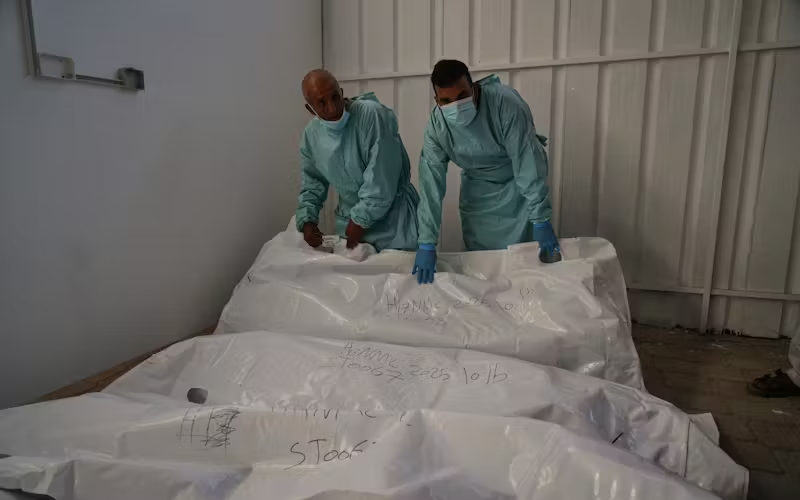【ジュネーブ=共同】野生動植物の過剰な国際取引を規制するワシントン条約の事務局は15日、食用のニホンウナギを含むウナギ全種を国際取引の規制対象にすべきだとした欧州連合(EU)などの提案について「採択を勧告する」との最終評価を公表した。11〜12月にウズベキスタンで開かれる締約国会議で投票国の3分の2以上が賛成して採択されれば、輸出が許可制となり、日本で価格が上昇する可能性がある。
日本のウナギ消費量は世界最大規模。かば焼きなどで食べる「養殖ウナギ」はほぼ全てが稚魚のシラスウナギを育てたもので、多くを輸入に頼っており、規制強化は養殖にも影響が出そうだ。
日本は「十分な資源量が確保され、国際取引による絶滅の恐れはない」として提案に強く反対。共同で資源管理する中国や韓国と連携して否決を目指す。
EUとホンジュラス、パナマが規制強化を提案。カナダやケニアは規制に前向きで、米国は反対を表明している。ロシアは十分なデータがないと慎重な姿勢だ。
ワシントン条約は規制対象となる動植物を「付属書」に掲載する。現在、ウナギではヨーロッパウナギのみ規制対象になっている。取引は可能なものの輸出国の許可書が必要な「付属書2」の対象で、許可を乱発する国などは、事務局から取引停止勧告を受ける可能性もある。
事務局は、違法に漁獲されたヨーロッパウナギが、ニホンウナギやアメリカウナギとして取引される「ロンダリング」が横行していると指摘。全種を付属書2に含めればロンダリングを減らし、適切に取り締まることができると結論付けた。養殖も野生の稚魚の捕獲に頼っていると問題視した。
ウナギは密漁や違法取引でどれだけ減っているのか正確に把握するのが難しく、流通の実態もよく分かっていない。
【関連記事】
- ・ウナギ製品「99%は絶滅危惧種」 中央大などDNA分析
- ・ウナギ稚魚の不透明取引が常態化、11〜24年無報告19トン流通か
- ・EU、ウナギの国際取引規制を正式提案 ワシントン条約締約国に
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。