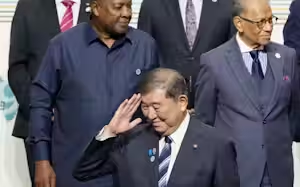中国経済の不振が一段と際立ってきました。特にさえないのが国内総生産(GDP)の4割を占める消費です。7月の小売売上高は2カ月連続で前の月に比べて減りました。背景にはいったい何があるのでしょうか。
専門家の間で注目を集めているのが、小売売上高の1割を占める飲食店収入の伸びの急激な鈍化です。5月までは5%を超える伸びを示していましたが、6月以降は1%前後にとどまっています。
伊藤忠総研で上席主任研究員を務める玉井芳野氏は、ラジオNIKKEIのポッドキャスト番組「NIKKEIで深読み 中国経済の真相」に出演し「公務員倹約令の影響が大きい」との見解を示しました。
中国当局は5月に「倹約と浪費反対に関する条例」を改定しました。共産党の関係者や公務員が接待の会食で高級料理や酒、たばこを提供するのを禁じる内容です。これに過剰反応し、宴会そのものを自粛する空気が中国全土で広がっているといいます。
ただでさえ、年後半にかけては耐久消費財の買い替えを喚起する政府補助金の効果がはげ落ち、その反動で消費は急減速しかねない状況です。玉井氏は「このままだと(中国の景気は)想定より下振れする懸念がある」とみています。
玉井氏の解説は以下のポッドキャストでお聴きいただけます。
「NIKKEIで深読み 中国経済の真相」番組サイトはこちら 詳しい内容は「note(ノート)」でもお読みいただけます。https://note.com/cnshinsou/n/n6f4996967da7?sub_rt=share_pw
詳しい内容は「note(ノート)」でもお読みいただけます。https://note.com/cnshinsou/n/n6f4996967da7?sub_rt=share_pw
 (編集委員 高橋哲史)
(編集委員 高橋哲史) 鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。