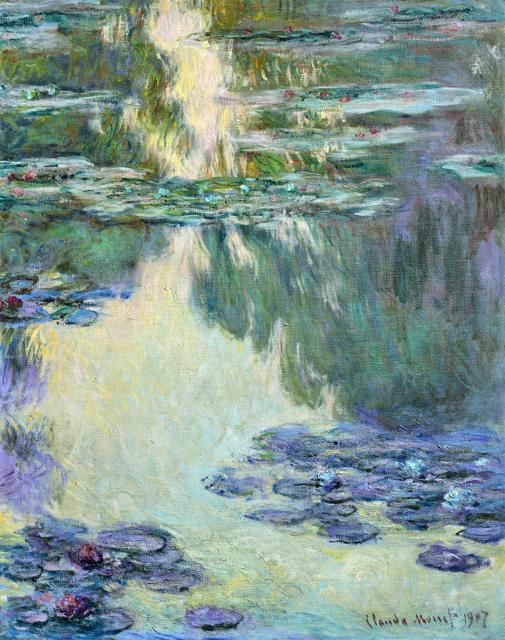「伝統的なメキシコ料理」が国連教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産に登録されてから今年で15年。メキシコの人々はトウモロコシ、豆、唐辛子などの食材を用い、独自の調理法による食文化を育んできた。実は現在のメキシコ料理の一部には日本の影響が垣間見えるという。
10月に東京都千代田区永田町にある在日メキシコ大使館を訪れると、シェフのディエゴ・ロペス・ファリアスさんが「白身魚のタコス」を用意してくれていた。ティラピアという白身魚には衣をつけて揚げる。トウモロコシなどで作ったトルティーヤの上に乗せ、タマネギの酢漬けなどを盛りつける。
北西部バハカリフォルニア州で一般的なタコスである。「天ぷらのような日本の衣揚げの技術が影響を与え、調理法を豊かにしました」とメルバ・プリーア駐日メキシコ大使は語る。
日本人による初めてのメキシコ移民は1897年に南部チアパス州に移り住み、コーヒー栽培に取り組んだ「榎本移民」に遡る。1920年代になるとバハカリフォルニア州のティファナなどに日本人が定住した。「タコスに天ぷら?」と日本人なら驚く食材の組み合わせの背景には、日本人移民が天ぷらの調理法を教えた事情がある。
これに先立つ16世紀からメキシコを植民地にしたスペインは、豚や牛、ヤギ、羊を現地に持ち込んだ。欧州の食材を取り入れ、食は独自の発展を遂げた。南部ユカタン半島の郷土料理「コチニータ」はその象徴だ。赤い香辛料「アチオテ」などを加えたオレンジ果汁に豚肉を漬け、その後最大12時間かけて弱火で焼いて仕上げる。スペインのもたらした豚肉やかんきつ類と、在来の香辛料を用い、スペイン統治前からあるオーブンで焼いていた。
伝統的に、メキシコ料理の最も基本的な食材はトウモロコシである。主食であるだけでなく神聖な存在として「アジアにおけるコメと同様の役割を担っている」と大使は指摘する。

「ニシュタマリゼーション」という調理法がある。食用の石灰や灰を加えたアルカリ性の水溶液にトウモロコシの粒を浸す。トウモロコシの外皮を取り除くとともに、栄養価を高める調理技術の起源は3500年以上も前にあるという。
先住民人口の多いオアハカ州には様々なトウモロコシ料理が伝わる。トウモロコシ粉の生地の上にインゲン豆のペーストをのせ、三角形に包んで焼いた「テテラ」はその一つだ。メキシコは豆の原産地の一つでもあり、50種類以上の在来種が今でも栽培されている。トウモロコシと豆、さらにカボチャを一緒に食べるのは、多くの先住民にとって「食の三位一体」といわれる。
メキシコ料理がユネスコの無形文化遺産に登録された理由の一つが、独自の農法だ。「ミルパ」はトウモロコシ、豆、カボチャを同時に栽培するやり方で、異なる作物同士が相互によい影響を与える。
たとえば、トウモロコシは支柱となる。カボチャの葉は畑に日陰をつくり、雑草の成長を防ぐ。豆は土壌の窒素量を安定させてトウモロコシ栽培を助ける。メキシコ人料理家のメルセデス・アウマダ氏は著書で「ミルパはもっとも効率的な農法のひとつであるとともに神秘的な意味を持つ。その土地、先祖、自然の霊をたたえる特別な儀式にも関係している」と指摘している。
現在のメキシコから中米までの地域はメソアメリカといわれる。紀元前1200年ごろからメキシコ湾岸にオルメカ文明が栄えた。その後、テオティワカン文明、マヤ文明、トルテカ文明、アステカ文明などが生まれた。
こうした古代文明の時代からトウモロコシ、豆、唐辛子、カボチャなどは基本食材だった。アボカド、カカオ、サツマイモ、トマト、ドラゴンフルーツ、バニラなどメキシコ原産の食材は非常に多く、植民地時代にスペイン経由で世界中に広がった。
逆にスペインは肉だけでなく小麦、乳製品、香辛料などもメキシコにもたらした。大使は「中東のレバノンや北アフリカからの移民がもたらした食材や食文化もある」と教えてくれた。世界各地の食材や料理を貪欲に取り込み変革を続けていく。そうした懐の深さがメキシコ料理にはある。

「ブニュエロ」は、シナモンや砂糖をまぶしたスペイン発祥の揚げ菓子だ。シナモンは「スペインが原産地のアジアから輸入し、メキシコに持ち込んだ」(大使)。食のグローバリゼーションを先取りしていたともいえる。
西部シナロア州の伝統料理「アグアチレ」は、ライム汁や唐辛子などで生のエビをマリネし、キュウリやタマネギ等を加える。こうした料理を参考に、すしなどの文化がある日本でも、かんきつ類や唐辛子を生魚に使う手法を料理人らが取り入れているという。食文化は国・地域の間で双方向に影響し合う。
現在、日本におけるメキシコ料理店は300を超えるといわれ、増加に目を見張る。西欧やアジアの料理に飽き足りなくなった日本の消費者を引き寄せるほか、メキシコや米国に駐在したり旅行したりした日本人が帰国後も楽しんでいる様子がうかがえる。
両国の食の接近の背後には経済関係の強まりもある。今年は日本とメキシコの経済連携協定(EPA)発効から20年の節目でもある。日本の自動車産業にとって、米国の隣国メキシコは重要な投資先。メキシコにとって日本は米国に次ぐ2番目の投資国だ。
「日本の食材でも本格的なメキシコ料理がつくれます。食材の80%は日本のスーパーでも入手可能で身近に楽しめますよ」と大使はPRする。大使館が作成したレシピ集「メキシコのキッチンから和の食卓へ」は今年改訂して無料で公開し、食を通じたさらなる交流に力を入れていくという。
瀬能繁
山田麻那美撮影
[NIKKEI The STYLE 2025年11月16日付]
 【関連記事】
【関連記事】
- ・伝統的フレンチの技を次代へ トップシェフ結集、食の変化に危機感
- ・インド料理初の三つ星店、誕生はドバイで 美食の街へと急成長中
■取材の裏話や未公開写真をご紹介するニューズレター「NIKKEI The STYLE 豊かな週末を探して」も配信しています。登録は次のURLからhttps://regist.nikkei.com/ds/setup/briefing.do?me=S004
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。