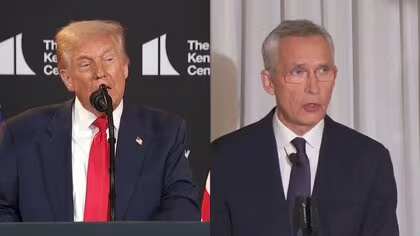プラスチックによる環境汚染が深刻化する中、この会議は2022年の国連環境総会の決議を受けて条約のとりまとめを目指していて、今回はスイスのジュネーブでおよそ180の国と地域の代表者が参加して5日から開かれていました。
最大の焦点となったのはプラスチックの生産量の規制で、EU=ヨーロッパ連合や太平洋の島しょ国などが規制を設ける必要性を主張する一方、サウジアラビアなどプラスチックの原料となる石油の産出国は反発を続けていました。
予定されていた最終日の14日も意見の対立が続き、会期を延長して15日の早朝まで協議が行われました。
しかし、各国の溝は埋まらず、最後の全体会合で合意の見送りが決まり次回の会議で協議を継続することになりました。
去年12月に韓国で行われた会議でも合意が見送られていて、規制をめぐる各国の溝が改めて浮き彫りになった形で、次回の会議に向けて課題を残しました。
中田環境副大臣 “引き続き実効性のある条約の早期策定を”
中田環境副大臣は合意が見送られたことについてスイスのジュネーブで記者団に対し、「本当に残念だが、引き続きわが国としてプラスチックの大量消費国、排出国を含む、できるかぎり多くの国が参加する実効性のある進歩的な条約の早期の策定を目指していきたい」と述べました。
専門家 “議論踏まえ国際的な合意を早急に”
環境問題の国際交渉に詳しい東京大学未来ビジョン研究センターの高村ゆかり教授は、今回の会議でプラスチックの生産量などの規制をめぐって意見の対立が続いていたことについて「産油国にとって非常に大きな経済的利益に関わる問題だ」と述べ、各国の利害が大きく異なる中、どのように合意をつくっていくかが課題だと指摘しました。
一方で、今回の会議では、議長や一部の参加国から、日本が合意の形成に向けて尽力したと評価する声も聞かれました。
これについて高村教授は、「日本が中立的な立場で、できるだけ合意をつくっていく方向で建設的な提案をしたという声を会場で耳にした。日本には意見の違う国との間の橋渡しの役割を期待したい」と述べました。
そのうえで、「プラスチックによる海の汚染に対する危機感は各国の間で非常に強い。今回の議論を踏まえ、国際的な合意をつくっていく方向で早急に考えていく必要がある」として各国が議論を続ける必要があると強調しました。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。