
pathdoc-shutterstock
<誰もが「他責」の傾向を持っていると、『なんでもまわりのせいにする人たち』の著者は言う。他責思考を生み出すメカニズムとその対処法は?>
・失敗やトラブルが起きたとき、自分の非を認めず、他人に責任転嫁する。
・問題解決のために自ら動かず、誰かがなんとかしてくれるのを待っている。
・言い訳が多く、被害者意識を抱えやすい。
例えばこのように、「トラブルの原因や責任を他人や環境のせいにする人」は昔からいるものだ。しかし、カウンセラーである『何でもまわりのせいにする人たち』(小日向るり子・著、フォレスト2545新書)の著者によると、近年は特にそういった人――「他責思考」の人――が増えているという。
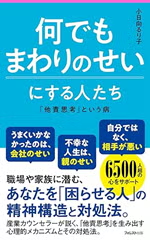
もちろん人は、本能的に自分の失敗や弱さから目を背けることで自己防衛を試みる生きものではある。つまり他責の傾向は、誰もが少なからず持ち合わせているのだ。ところが、他責思考は自覚しづらく、指摘されない限り自分では気づけないらしい。
著者の言葉を借りるなら、「無意識のうちに起こる自動的な思考パターン」だからこそ厄介なのだ。そこで本書では、他責思考を生み出す心理的メカニズムとその対処法を明らかにしているわけである。
「他責グセ」の人が増えている理由として、著者は以下の7点を挙げる。
①保身の時代がもたらす影響:他人との適切な距離感がつかめず、ハラスメント認定を恐れているため、刹那的で保身第一の考え方をする人が増えた。
②行きすぎた「自分らしさ」:本来、自分らしさとは、誰もが幸せに生きるための手段のひとつ。しかし、自分らしさと「自己中心的な生き方」をはき違える人が増えた。
③ネットの台頭:「生活が苦しいのは政治のせいだ」というように、ネットの情報の伝達の速さと拡散力が、他責思考を強固にする要因になっている。
④高齢化社会:価値観は加齢とともにアップデートしづらくなるため、「すべては若者が悪いのだ」というような他責思考を生む要因となりがち。
⑤就職氷河期と人口ボリュームゾーン:自分の努力ではどうにもならない社会情勢によって、不安定な雇用と低い年収のままで働かざるを得ない41〜55歳の人たち(2025年時点)が、今の日本のボリュームゾーン年代である。
⑥団塊世代と就職氷河期の対立構造:「文句を言わずに努力すれば道は開ける」と悪気なく信じている団塊世代(75〜78歳)がもうひとつの人口ボリュームゾーンであるため、日本全体に対立構造の空気が蔓延している。
⑦論破の賞賛:YouTubeやSNSの影響で、相手を論破するさまを賞賛する雰囲気が生まれた。
⑧貧富の差の拡大:「一生懸命働いても生活は豊かにならないが、一方には贅の限りを尽くしている人がいる」という不満が、他責思考につながる。
自分が感じる痛みは誰にも転嫁できない
なるほど。他責思考の人が増えた理由もある程度は理解できる。その一方、「自分も他責思考だった」ということもありうるわけだが。
では、もし「自分は他責思考かもしれない」と気づいたら、どうすればいいのだろう? まず、自分だけが感じる感覚は、誰にも代わってもらえないのだと自覚することが大切だと著者は言う。
自分の感覚は「今、ここにある自分」だけが感じることができるもの。したがって、「今の政治が自分の深い感情の根源だ」と思うのであれば、「選挙に行く」「政策を確認し、理念に共感できる政治家を応援する」「自分が政治家になる」など、その不快感を解消する手段を実践すればいい。
自分が感じる痛みは他人に転嫁させることができないのだから、自分自身が主体的に動く必要があるのだ。
そして、「自分の痛みそのものは誰にも代わってもらうことができない」という原理原則を納得したうえで、困ったときや悩んだときにはどんどん周りに頼ってみるべきだと著者は主張している。
自分の殻に閉じこもっていると、視野も狭まってしまう。そのため気づきにくいだろうが、確かにこの自覚は重要なことかもしれない。
「自分の感覚は自分だけが感じるもの」という心の軸をぶらさない覚悟さえあれば、それ以外の部分はどんどん助けを求めていいのです。
逆に、そもそも助けを出していない自分を棚に上げて、助けてくれないまわりを責める行為は矛盾していると言えます。(136ページより)
なお前述のとおり、他責グセがある人は「自分が悪いのではなく、〇〇が悪い」という自動思考(何かが起きたとき無意識に出てくる思考)に陥りがちである。だからこそ、自ら気づき、変わろうと努めることも大切だ。
「自分以外が楽しそうでムカつく」という妬み
行動だけでなく、思考においても「変わる」ことは怖いことです。他責が自動思考になって、変わることを拒む人が大半の中で、「自分は他責グセがあるかもしれない」となんとなくでも気づけたなら、まずはそう感じた自分を認めてあげてください。
自らの気づきは、他責グセから抜け出る大きな一歩です。(139ページより)
他責になる要因が「過剰な自己保護」であり、その点に関して見落とすべきでないのは、「過剰に自分を保護する」ことと「自分を労る」ことは違うという点だ。
「自分を過剰に保護する」とは、自分の周りに頑丈なバリケードを作り、その中心にとどまること。
一方、「自分を労わる」とは、「自由に動きはするけれど、その過程で疲れたり、傷ついたりした場合には無理をせず、体と心がリカバリーするまで充分に自分を休ませてあげる」感覚だという。
バリケードをつくってそこに閉じこもっている生活は、安全ではありますが、楽しくはありません。どんなに安全でも、自分自身の生活に楽しさがなければ、他人が楽しんでいる様子を微笑ましく見ることなどできません。他人が自由に動いている様子は、危なっかしくて、目を背けたくなります。
さらに、安全な場所から自由な世界を見ると、妬みの感情が生まれます。(140〜141ページより)
「自分以外が楽しそうでムカつく」といった妬みの感情は、それを吐き出したり、自分より弱い相手をいじめたりすることで一時的に解消できる。しかし、そんなことを繰り返していると他責思考がクセになってしまうのだ。
「○○が悪い」と悪者が出てきそうになった場合は...
とはいえ、頭で理解していたとしても、「この状態が嫌だ」「この人が嫌いだ」という不快感を抑えられないかもしれない。そんなときは、ただ拒否反応を示すのではなく、「この状況を自分の力だけで打破できないか」という観点からも考えるようにしてみるべきだという。
他責グセがある人の場合、まず「私は悪くない、〇〇が悪い」という結論があり、その〇〇に何を当てはめるのがしっくりくるか、という思考回路になっています。もちろん、公平な視点から見ても、自分以外のところに完全に責任がある場合や、逆に、どちらが悪いとも言えない場合がありますので、「他責の結論を絶対に出してはいけない」ということではありません。
しかし、「他責」を最優先の結論としてありきにしないで考えてみることをやっていただきたいのです。
「〇〇が悪い」と悪者が出てきそうになったら、「少なくとも自分のせいではない」というところで思考を終わりにしてください。(146〜147ページより)
そして他責思考に陥りそうになったら、まず自己解決できないかと考えてみる。そのうえで、「少なくとも自分のせいではない」というところで思考を終わりにし、自己解決のための方法を探し当て、そこに集中することが大切なのだ。
「自分に他責グセがあるかもしれない」と気づけたとしたら、従来の思考回路を変化させ、自動思考を止めるため、自分だけの解決策に集中するべきということである。
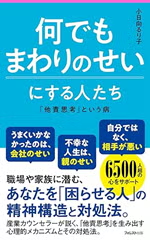 『何でもまわりのせいにする人たち』
『何でもまわりのせいにする人たち』
小日向るり子・著
フォレスト2545新書
(※画像をクリックするとアマゾンに飛びます)
[筆者]
印南敦史
1962年生まれ。東京都出身。作家、書評家。広告代理店勤務時代にライターとして活動開始。他に、ライフハッカー[日本版]、東洋経済オンライン、サライ.jpなどで連載を持つほか、「ダ・ヴィンチ」などにも寄稿。ベストセラーとなった『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社)をはじめ、『読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術』(星海社新書)、『人と会っても疲れない コミュ障のための聴き方・話し方』(日本実業出版社)など著作多数。2020年6月、日本一ネットにより「書評執筆本数日本一」に認定された。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。



