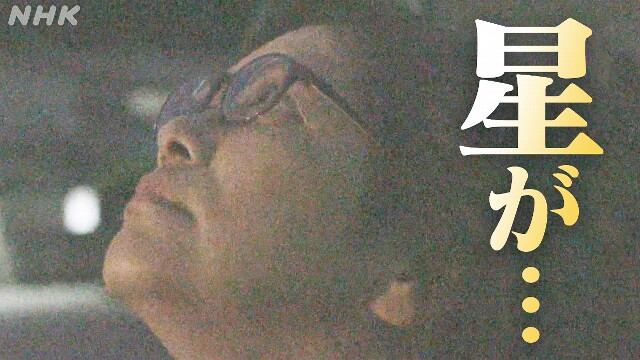物の価値は資産価値だけではない/shutterstock
<国立民族学博物館(通称「民博(みんぱく)」)の収蔵庫は、一般の人が足を踏み入れることのない聖域だ。そこには世界最大級の民族学コレクション33万5000点が眠っている>
民博は民族学・文化人類学の博物館だ。それゆえ、収蔵庫に収められているのは国宝や名画ではない。世界各地の人々が日常で使っていた、ごく普通の道具や衣装だ。
民博は「20円の物であっても学術的に意味があれば受け入れ」、「資料の廃棄は基本的にしない」という徹底した保存への姿勢を取る。年にいちどの資料管理係の職員総出による大掃除、害虫との果てしない戦い、災害への備え----収蔵庫の日常は、想像以上に厳格で、そして人間味に溢れている。
果たして「物の価値」とは何なのか?『変わり者たちの秘密基地 国立民族学博物館』(樫永真佐夫監修、ミンパクチャン著、CEメディアハウス)より、博物館のバックヤードで繰り広げられる、保存活動の日常を覗いてみよう。
■文化人類学の聖地「国立民族学博物館」全4回:[1]/[2]/[3](本記事)/[4]
◇ ◇ ◇「断捨離はしません」:博物館の使命
「ところで、整理整頓してスペースを見直すなかで、やっぱり断捨離もするんですか?」
「本当にもうどうしようもない資料については、廃棄する例も少しはあります。でも、基本的には資料の廃棄はしません。ここにあるものは学術資料で、たとえ傷んでいてもそのこと自体にも価値があるんです。それを我々が勝手に価値のあるなしを判断して仕分けをするなどということはありません」
文化庁は博物館の基本方針として、資料を未来永劫保管することを掲げている(※ただし民博は文化庁ではなく文部科学省に属する)。維持費用の問題はあるが、コレクションを後世につなげていくことが博物館の使命なのだ。その姿勢は民博でももちろん変わらない。
民博の収蔵庫の規模は博物館のなかでもとりわけ大きく、収蔵する資料点数も桁外れに多い。民族学のコレクションとしては世界最大級である。受け入れた物を、資料として登録し、保存し、未来に残していく。その姿勢はこれからもずっと変わらない。
災害に害虫...終わりなき戦い
収蔵庫を日々管理している西澤さんに苦労話を聞いてみた。
「こんなに厳しく管理されているわけですが、それでもやはりトラブルってあるんですか? 資料を破損してしまったり......」
「トラブルはどうしても起きてしまいますね。人為的な事故もあれば自然の事故もあります。阪神・淡路大震災や大阪北部地震では、ここも被害を受けて壊れた物もありました。水漏れが起きて濡れてしまったりということもありました」
震災や何かしらの災害で大規模停電が起きても、1〜2日はバックアップで空調を維持できる。建物の点検で電気を止めるような場合も、作業は1日で終わらせるようにしているそうだ。収蔵庫では定期的な資料の確認作業が行われている。各収蔵庫で年にいちどの大掃除を実施し、そのときにすべての棚をくまなく確認する。
「資料を1点ずつ細かく掃除することはできません。もともとの汚れはその資料が持つ情報でもあるし、汚れといっても簡単に判断できないんです」
照明の傘から始まって、上から下に向かって清掃していく。掃除機や立体吸着ドライシートを使用し棚を拭く。
また、害虫被害の点検も定期的に行われる。標本資料係のスタッフがほぼ全員参加する。大きな収蔵庫では2〜3日、小さな収蔵庫でも丸1日はかかる。
「虫は収蔵庫だけではなく、展示場にも発生します。だから展示場の資料も点検が必要な
んです。民博の本館展示は露出展示のものがほとんどです。こまめに点検しないと虫の発
生にすぐに気づくことができません」
虫の発生場所を把握するトラップ調査が年に4回行われるのは先述のとおりだ。収蔵庫も展示場も対象にして、虫の数や種類を確認している。30年以上のデータを蓄積しているので、異変があれば早めに対応できる。
「虫の知らせです。民博に湧く虫は文化財害虫と言われるわけですが、文化財だけを選んで食べる虫なんていませんから」
それはそうだ。うちのセーターを食べる虫は貴重な民族衣装だっておいしく食べるだろう。
20円でも受け入れる、100万円でも断る:物の価値とは?
最後に末森先生に気になっていたことを聞いてみた。34万7000点もの資料を収蔵する民博。その大半はいわば生活の延長にある品だ。文化財や国宝、名画といった、わかりやすい価値のあるものではない。それならば、ここに収蔵するべきか否かという価値はどうやって決まるのだろうか?
「資産価値という意味では、あまり金銭的な価値を付けられないものもありますし、資産価値を基準に資料を収集しているわけではありません。資料は破損などの事故に備えて保険をかけるんですが、その登録もけっこう大変なんですよ」
保険をかけるとき、研究者が集めてきた資料の場合はその購入金額、寄贈品ならば評価金額を登録しなくてはならない。評価が困難な場合は、過去の同様の物の登録方法や市販されている場合の価格を参考に評価基準額を設定する。
「物の金額って難しいですよね。どう評価していいかわからない物がけっこうあります。それに、当時は100円で買った物が、いまでは入手困難で高価格になっているという場合もありますしね」
世界中の人々の暮らしに関連したものを収集する。しかし、何かしらの基準を設けなければきりがない。収集するときの価値判断基準として、「モノに情報が付いていること」が重視されると末森先生は言う。
民博には寄贈の申し出も多い。収蔵の問題もあるので、断ることも多いのだが、受け入れの判断基準として、まず「情報がちゃんと付いているか」が問われる。美術館や宝物殿ではないので、美しい物や素晴らしい物、あるいは古い物でも情報がなければ受け入れない。逆に言えば、20円の物であっても学術的に意味があれば受け入れる。受け入れの際には、なぜその資料を受け入れるかを記した書類を研究者が作成する。
減りゆく収集、増え続ける責任
あらゆる道具は何らかの意味、つまり価値があるから道具として存在している。しかし、その道具に情報があるかないかが、今後に残していくうえで差を生む。どこで、いつ、誰によってつくられ、どこで、誰によって使われていたのか、どういう経緯で入手され、どこに保管されていたのか?
「物の履歴がわかるということが大事なんです。物の履歴に物語があって、その物語に価値が生まれるんですね。民博では、資料の情報をデータベース化して管理しています。それでも、すでに退職した教員(研究者)によって収集されたものなど、資料の情報が追えないこともしばしばあります。その当時は当たり前だった物でも、どんどんなくなっていくんです。当時はみんなわかっているので、ちゃんと記録していなかったりします。するともう追えなくなっちゃうんですね」
物の価値とは何か? 歴史学の鈴木英明先生が言っていたことを思い出した。「歴史では、普通に生きている人のことっていちばんわかりづらいんですよ」。人だけではない。人が使う物も同じだ。普通の物ほど後世に残らない。宝物と違って大事にされないから、忘れられていく。考えさせられる話である。
民博では年度による変動が大きいが、2024年度は500点ほどの資料を受け入れた。コレクションを引き取る機会が多い年は点数が多くなる。研究予算の削減などもあって、近年では研究者が調査で収集してくる資料の数は減っている。
ミンパクチャン[著者]
ルポライター 市井の国立民族学博物館ファン。
樫永真佐夫[監修者]
国立民族学博物館教授/文化人類学者 1971年兵庫県生まれ。2001年東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。博士(学術)。2010年、第6回日本学術振興会賞受賞。著書に『道を歩けば、神話 ベトナム・ラオス つながりの民族誌』『殴り合いの文化史』(左右社)他多数。2023年より『月刊みんぱく』編集長。ボクシング、釣り、イラスト、料理など、いろいろする変人二十面相。
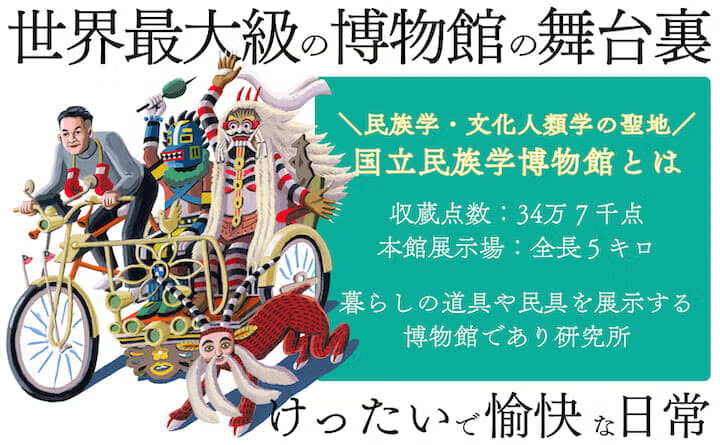

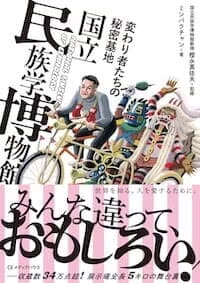
『変わり者たちの秘密基地 国立民族学博物館』
樫永真佐夫[監修]
ミンパクチャン[著]
CEメディアハウス[刊]
(※画像をクリックするとアマゾンに飛びます)
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。