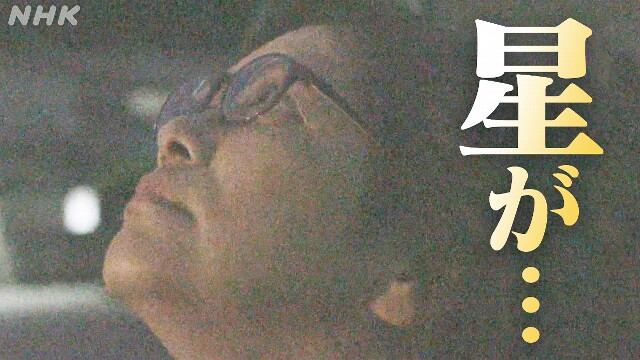フィールドにて。子を負い、畑に肥料を運ぶ黒タイ族の若いお母さん(写真:樫永真佐夫)
<グローバル化のなかで多様性が尊ばれているわりに、争いや差別はなくならない。世界の多様な民族を研究し、伝える国立民族学博物館の存在意義とは>
世界中どこに行っても似たような街並みが広がり、同じチェーン店が立ち並ぶ現代。グローバル化によって地域差が失われていくなかで、世界の多様な文化を研究対象とする民族学・文化人類学は今後どうなる?
過剰に効率性を重視するビジネスの風潮はアカデミアにもおよび、文化人類学分野では現地に浸かって人々との信頼関係を築く従来のフィールドワークも難しくなっている。
『変わり者たちの秘密基地 国立民族学博物館』(ミンパクチャン著、CEメディアハウス)で監修者を務めた文化人類学者の樫永真佐夫教授の率直な言葉から、文化人類学という学問と博物館の新たな意義を考える。
■文化人類学の聖地「国立民族学博物館」全4回:[1]/[2]/[3]/[4](本記事)
◇ ◇ ◇「親族という共同体なんて言われても」
「いまは文化人類学の様子も、ぼくらの時代とはずいぶん変化しています」
そう言うのは、樫永先生だ。どういうことだろうか?
「たとえば、20世紀はじめに生まれた文化人類学の理論の中心は、長いあいだ『親族』でした。人間がつくる最小の集団単位は家族だから、民族や地域によって多様な親族の機能や結合を知るのがその社会を知る基本。
そのうえに儀礼だとか信仰や習慣、政治や経済、生業、言語など、その社会の文化の営みがあるって発想だったんです。じっさい、ぼくが修士課程に進む前に読んだ概説書はたいがい家族・親族のテーマにたくさんページを割いていました。もっとも90年代でも、親族なんてテーマはとっくに古くなっていましたけど」
たしかにいま、親族なんて言われても、都会育ちの自分はあまりピンと来ないところがある。おそらく世界中の近代化した地域に似たような面があるだろう。
「人間の社会の核は家族・親族です、なんて言われても、はあ? ですよね。だけど、それをコアに据えて、世界のいろんな社会を調べまくった文化人類学が独自に理論化した領域って、やはり親族しかないのかもしれない。有名なレヴィ=ストロースの構造主義だって根幹に親族論がありますしね。
文化人類学者には長期のフィールドワークがある、って言われるかもしれませんが、それは方法であって理論ではありません。しかも、いわば一人一人の名人芸。もはや『未開社会』がどっかにある、なんて幻想も抱けないですし、この先、文化人類学の独自性ってどこにあるんかな?」
たしかに。文化人類学は比較的新しい学問だ。しかし時代の急速な変化によって、文化人類学とは? 文化人類学の意義とは? という学問の根っこに立ち返る時期を迎えているのかもしれない。
Zoomか現地密着か?:効率化で失われるもの
「いまは、現地に行って、そこの暮らしにどっぷり浸かって、一緒にいすぎてしんどいな、とか思いながらやる、そういう学問じゃなくなってきているんですよね」
また、いろんなビジネスの世界で語られるタイパやコスパの概念が文化人類学の研究分野にも浸透してきている。
「いまの研究環境では、まず目的を明確にし、かなり限られた時間内で、その目的を果たすことが求められます。電話したり、ZOOMを開いたりなどで効率化を図ることができる反面、目的以外のアソビの部分で発生する何かにいちいちかかずらってはいられないかも。フィールドワークにしても、今は現地の人に電話やメールで確認することだって可能になっています。
昔の経験を話せば、とにかく現地の人たちにコバンザメのようにくっ付いて、ちょっかい出さない程度に(?)話しかけてみたり、真似してみたり、じっくりゴソゴソやっていたのでした。ところで、なんでそんなにフィールドワークには時間がかかるのか。もちろん言葉の習得の問題もありますが、調査とか以前に、人との信頼関係を築き、ある社会のなかで一定のところにおさまるのって時間かかるんです」
フィールドワークの目的は単に情報やデータを集めることではない。現地の人たちと関係を築きながら彼らの文化や暮らしを深く理解する。この「深く理解する」の部分は、たしかに効率化とは相性が悪い。
民博は「昔の世界」を見せる場所になってしまうのか
文化人類学・民族学の変化は、その研究成果を展示している民博の存在価値も変えてしまうのではないかと樫永先生は考えている。
「民博も、いまは、ヨーロッパとか東南アジアとか地域ごとに分けて、こんな文化がありますって展示しています。でも、20年もしたら、『へえ、20世紀の人らの地域イメージってこんなんやったんか』ということになるかもしれないですよね」
「なるほど。言われてみると、日本の民俗学がそんなイメージですね。一般の人間にとっては、いまのことを知る学問というよりも、かつて日本のいろんな土地にあった風習を知る歴史の一部のようなイメージがあります。そうすると民博もやがて、『世界の現在』はなく『世界の過去』を展示する歴史博物館みたいになっていくんですかね......」
民博が開館した1977年、海外に出かけていくことはいまほど気軽ではなかった。民族学や文化人類学といった学問、そしてそのフィールドワーカーたちが、この広い世界の見知らぬ土地に住んでいる人々の暮らしを伝えてくれた。民博は博物館施設としてじっさいのブツを展示することで、人々のリアルを感じさせてくれる存在だった。
しかし、グローバル化によって地域差が消失し、世界がフラットになりつつあるいま、民博の存在意義とはなんだろう? 樫永先生は言う。
「どこかの民族や地域の文化・社会の特質に迫る、みたいなかつてとは、現代の文化人類学は様変わりしています。たとえば移民とか、技能集団とか、対象の幅はどんどん広り、個人の動きに注目しながらネットワークや関係を分析する研究が増えています」
なるほど。民博本館展示の「日本の文化」展示場には、日本に住む様々な移民の暮らしを紹介している一角がある。他にも戦禍を逃れてきた難民の移動を伝える展示もある。
「コミュニティの関係性の研究ですか。それって、民族学が社会学に接近しているような印象を持ちました。止めようのない時代の流れ、変化のなかで、先生はこれからの民族学や文化人類学をどう捉えますか?」
変わりゆく世界を後世に伝える
「まあぼくなんかは、自分が書いた黒タイ族の民族誌なんかを、ぼくにたくさんのことを教えてくれた人らの孫や、もっと下の世代の人が読んで、昔の黒タイ族のくらしってこんなんやったんやな、と知って楽しんでくれたら嬉しいなあ。そんなロマンチシズムですね」
ふと、かつて鎖国していた日本にやって来た外国人宣教師たちの存在を想像した。彼らが書き残した記録をいまの日本人である自分が読んで、いろんなことを知り、感じる。その「おもしろいなあ」という感覚。
先生は消えゆく文化、あるいは変わりゆく文化人類学の記録者としての役割を果たしていく。知るとは、残すこと。変わりゆく世界を後世に伝える。
ミンパクチャン[著者]
ルポライター 市井の国立民族学博物館ファン。
樫永真佐夫[監修者]
国立民族学博物館教授/文化人類学者 1971年兵庫県生まれ。2001年東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。博士(学術)。2010年、第6回日本学術振興会賞受賞。著書に『道を歩けば、神話 ベトナム・ラオス つながりの民族誌』『殴り合いの文化史』(左右社)他多数。2023年より『月刊みんぱく』編集長。ボクシング、釣り、イラスト、料理など、いろいろする変人二十面相。
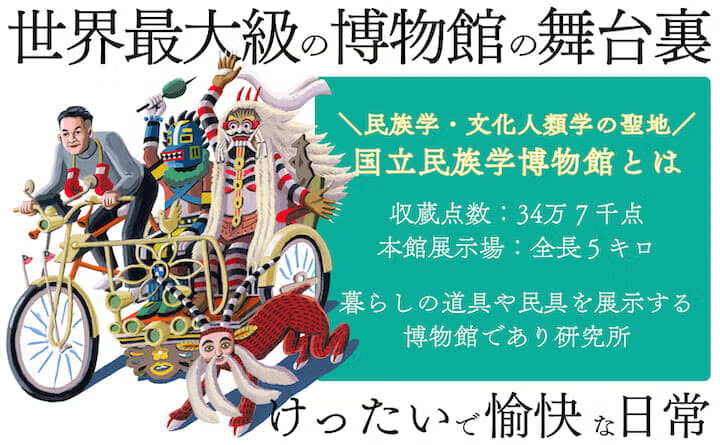

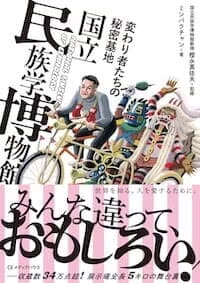
『変わり者たちの秘密基地 国立民族学博物館』
樫永真佐夫[監修]
ミンパクチャン[著]
CEメディアハウス[刊]
(※画像をクリックするとアマゾンに飛びます)
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。