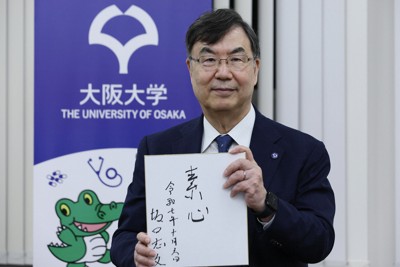水を張らない乾いた田んぼに直接種をまく「節水型乾田直播(かんでんちょくは)栽培」。これまでの水稲栽培に比べ、省力化や効率化を図ることができ、規模拡大や需要に応じた増産にも対応可能だ。NSGグループの農業法人ベジ・アビオ(新潟市)は2日、この手法で栽培した稲の収穫作業を公開した。
同社ではJA新潟市や新潟クボタなどとプロジェクトチームを組み、実証実験を開始。初年度は約57アールに作付けした。
この日は新潟市北区のほ場で、高温に強いコメの品種「にじのきらめき」をコンバインで刈り取った。
ベジ・アビオなどによると、従来型の水稲栽培に比べて、田んぼに直接種をまくため、苗づくりや田植えなどの工程を省略できる。水は必要な時に最小限を流すだけのため、水管理に必要な時間も削減できる。そのため作業量は約6割削減できると推計されている。また、水を張らないため、水田から排出される温室効果ガスのメタンの排出も抑制できるなど環境面での利点も生まれる。

収穫作業を見守ったベジ・アビオの加藤和彦取締役(42)は「初年度から収穫できる状態になり、喜んでいる。徐々に栽培面積を増やしていきたい」と述べ、今後の拡大に意欲を示した。さらに「遊休地は増えていく中、この栽培方法が社会実装できれば、農家1人あたりで2倍の面積を管理できるようになる。担い手不足の解消やコスト削減につながる」と期待を寄せた。
乾田直播を巡っては、政府が補助金による普及支援に乗り出し、県も収量などのデータを収集し、栽培の拡大に向け後押しする考えを示している。一方で、収量が不安定であることや雑草防除に手間がかかることなどの課題がある。
ベジ・アビオのプロジェクトに協力した化学メーカー「BASFジャパン」の坂田益朗マネジャーは「水がない状態では、さまざまな雑草は生えやすくなる。除草剤をまく適切なタイミングなど、来年以降もサポートしたい」と話した。【神崎修一】
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。