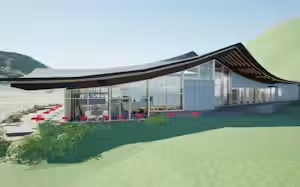来春佐賀県武雄市に開校する武雄アジア大学の学長に就任する小長谷(こながや)有紀さん(67)が、2025年度の文化功労者に選ばれた。文化人類学者の小長谷さんは1979年に日本人女性として初めてモンゴル留学を果たすなど、モンゴルを中心とした遊牧文化研究の第一人者として知られている。研究や佐賀への思いなどを聞いた。【聞き手・西貴晴】
――なぜモンゴルを選びましたか。
◆「どこか広い所へ行ってみたい」と思っていた京都大2回生の時、モンゴル語の夏季講座を知って参加しました。1カ月間ほぼ毎日です。講座終了が近づくと「モンゴル語を実際に試してみたい」と留学を考えました。
――それまでモンゴルと何か縁がありましたか。
◆いえ、たまたまです。当初は女性の留学は認められなかったので米国の大学でモンゴル語を学ぶことも考えたのですが、もう一人、女性の留学希望者が現れて一緒に行くことになりました。
――どんな研究を続けてきましたか。
◆遊牧民の暮らしの技術と儀礼▽社会主義的近代化のオーラルヒストリー(口述史)――の2本柱です。
――どんな狙いがありますか。
◆例えば牛のミルク搾りは、相手を殺さずに食べ物(飲み物)を得る人類史の中でもまれな方法ですが、どうやって始まったのか、それを遊牧民の暮らしから推測する。人類が多様な生き物の一員としてどう生きていくかの参考になります。
――壮大な話です。研究だけではなく、現地の学校に黒板を贈るプロジェクトにも取り組んだと聞きました。
◆現地で発生した雪害をきっかけに01年にNPO法人を設立して、12年間で1539枚の黒板を学校に贈りました。研究対象へのリスペクトは文化人類学の基礎的なところですが、人々が遊牧生活を捨てて都会に流出せざるを得ない現実を見て「なんとか応援したい」と思いました。
――佐賀の印象と、学長としての抱負を聞かせてください。
◆佐賀のよさを未来につなげるには何をしたらいいか。自分の育った場所を捨てずに、ここで暮らしていくことに意味がある。そんなことを考えながら大学として佐賀を応援していきたい。ただ佐賀にはすてきな魅力があるのに外から見えにくい。「もっと伝えましょうよ」と思います。
小長谷有紀さん
大阪府生まれ。京都大大学院博士課程修了。国立民族学博物館(大阪府、みんぱく)教授をはじめ、文部科学省の科学技術・学術審議会の委員などを務めた。2013年に紫綬褒章、22年にモンゴル国北極星勲章。23年から国際モンゴル学会会長。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。