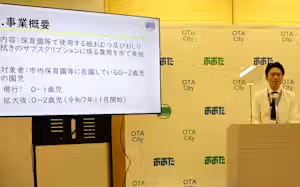水深20メートルの海底から、水面のさざ波がはっきり見えるほど澄んだ「ボニンブルー」の海です。ボニンブルーは、東京都小笠原諸島の海の色の美しさを象徴し、表現することば。小笠原は、江戸時代に発見されるまで無人島だったことから、無人=ボニンと呼ばれるようになったことに由来します。
私の個人的な印象ですが、沖縄・慶良間諸島の「ケラマブルー」が白い砂地とのグラデーションから成るやや淡いターコイズブルーのような色であるのに対し、ボニンブルーは群青がかった強い青色といえるでしょうか。皆さんが見てくださっているそれぞれの端末で、どこまでこの違いを反映できているのか、写真表現として悩ましい点でもあります。
◇
このボニンブルーの海に神々しいばかりの太陽光が降り注ぎ、天啓を受けたみこたちのように、ノコギリダイの群れが、形を変えながらゆるやかに舞を奉納しています。その後方には、大きなハマサンゴが堂々とした姿を浮かび上がらせています。陸上でも、円すい形の秀麗な山容そのものが神秘的な「ご神体」としてあがめられるように、このサンゴも神がかったものを感じさせてくれます。
それもそのはず。ハマサンゴの仲間は適切な環境条件下では極めて長寿命で、人知を超えた存在といってもおかしくない動物なのです。国内でもほかに、数百年あるいは1000年以上生きていると推定できる個体が確認されていて、「千年サンゴ」などと呼ばれています。
◇
ハマサンゴの仲間は国内で2023年までに29種が報告されていますが、このサンゴは「コブハマサンゴ」と思われます。高さは4~5メートル、直径は約10メートル。堅い骨格を持つイシサンゴ目(もく)に分類される硬質サンゴ、いわゆる「ハードコーラル」です。
1・5ミリほどの小さなポリープ(個虫)が群体となって巨大な塊を作り上げています。コブハマサンゴの成長速度は遅く、年間数ミリから1センチ程度。つまり、このサンゴの年齢は500歳以上だと思われます。
◇
サンゴの骨格が海底に沈んで積もり、悠久の時を経て地層となった地形が「サンゴ礁」です。このためハードコーラルは「造礁サンゴ」とも呼ばれます。サンゴ礁が隆起するなどして地表に現れたものが石灰岩。ヒトがコンクリートなどの原料に利用しています。地球上の石灰岩の多くはサンゴの骨格や貝の殻などからできた、海由来のものなのです。
また、ハードコーラルは季節によって成長に差異があるため、骨格の断面には樹木の断面と同じように年輪が刻まれます。成長の違いを調べ、年輪に沿って同位体比や微量元素の変動を測定することで、過去の環境の変化を知ることができます。ハマサンゴ類は長寿なので、造礁サンゴの中でも環境変動の研究という点で注目されています。極地の氷河などから掘り出される氷床コアと同じですね。
サンゴを中心としたこの風景には、地球のダイナミズムが映し出されているのでしょう。だからこそ、神サマが降臨しているかのように見えるのかもしれません。(東京都小笠原村で撮影)【三村政司】
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。