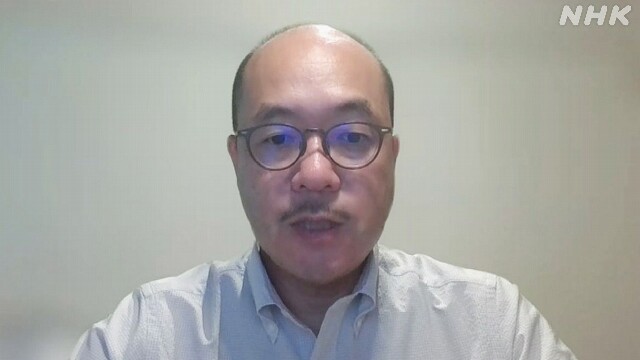
Q. 8月前後の時期、ヒグマは本来であれば何を食べているのでしょうか?
A. この時期は本当に山でヒグマの食べ物が少ない時期ですけれども、例えばまだやわらかいような植物を食べていたり、アリやハチなどの昆虫を掘って食べていたりします。
8月半ば以降になってくると、熟すのが早いくるみや木イチゴなどの木の実も少しずつ食べるような時期になってきます。
ただ、今は山の中で草がだいぶ硬くなっていると思いますし、まだ木の実が熟すには少し早い時期ですから、どうしても人里の農作物には寄ってきやすい時期だと思います。
9月の下旬ぐらいになれば、普通ですと山の中に木の実がたくさんつきますので、それまでは警戒を続けた方がいいと思います。
ただ、今年の秋の山の実りがもしも悪いと、それが10月ぐらいまで続いてしまう可能性がありますので、今年は去年に比べたら要注意ということで、特に畑の周辺などはしっかりと守っていただきたいと思います。
Q. クマは嗅覚が鋭く、遠くのにおいも嗅ぎつけると聞きますが、どれくらい鋭いのでしょうか。
A. 犬よりも嗅覚が鋭いという話もありますので、かなり鋭いと思います。
地形とか湿度にもよるかもしれませんが、いい匂いがすれば、1キロ以上離れたようなところからでも匂いを嗅ぎつけて寄ってくるというようなこともありますので、非常に嗅覚は鋭いということは、まずは知っておいていただければと思います。

Q. ヒグマはそもそも市街地によってくるものなのでしょうか?
A. 市街地に出没するパターンはいろいろあると思いますが、基本的に市街地にはクマが誘引されるようなものはふだんはありません。
出てくるとしたら、迷い込んでくるパターンで、例えば森から川につながる河畔林沿いに間違えて入ってきてしまうようなパターンや、繁殖期に親子連れのクマがオスグマを避けるために、あえて人の近くにいてそれが目撃されるようなパターン、それらが一番多いと思います。

そして、だんだん季節が進行していくにつれて、山に食べるものが少なくなり、食べ物を求めてクマが歩き回る季節になったときに、市街地に管理が不十分なゴミがあったり、庭先のコンポストから生ゴミの臭いがしていたり、畑でトウモロコシやスイカなどクマの好む作物がいい匂いをさせたりしていると、今度はそれを求めてクマが下りてきます。
ですから、市街地出没と一口に言っても、いろんなパターンが混ざっていますが、特に危険なのはその匂いにつられて市街地に来るというのが最悪ですので、そういったケースがないように、しっかり管理していくことが大事だと思います。
Q. ことしは特に市街地への出没が多いように思われますが、なぜでしょうか?
A. 特にことしというのが、直接何が原因かとかわからないところもありますが、去年は比較的静かで、その前の2023年にかなりの出没があり、このところ道内では2年おきぐらいにクマの出没の多い年が続いています。
そういった意味では、ことしは多い可能性は十分あるかなと思います。
それに加えてことしは非常に暑い年ですので、森の中で植物の生育状況がいつもとは違うかもしれません。
今、畑の作物についても生育状況にずれがきているというような報道があると思いますが、山の中でも同じようなことが起きていて、それがクマの夏場のエサ不足を助長している可能性はあるかなと思います。
そうすると、いつもよりもちょっと早い段階で畑に降りてきて、作物を求めて食べているというようなことが起きているかもしれないと思っています。
Q. 北海道の南部(道南)では、特にクマの出没が多くなっています。この地域には、人とクマが遭遇しやすくなる特徴があるのでしょうか?
A. そもそも道南のクマの生息率は高く、それは森林の環境が豊かであるということが要因の一つだと思います。
このため、道内の他の地域に比べても、森林の中で割と多くのクマが暮らしているという状況になります。
さらに道南は、地形的に山が海岸線まで迫っているような半島状の地形をしていて、人の生活圏がわりと海岸線の間に広がっていたり、川沿いの河口付近に広がる若干の平野に人が住んでいたりするような地域が多くあります。
そのため、クマと人の生活圏が非常に近くて、その範囲が長い距離にわたっているというのが特徴だと思います。
そうするとどうしても、クマと人との出会いや出没被害が増えやすいという特徴があるのではないかと思います。
Q. 道南のクマは、気性などの特徴があるのでしょうか?
A. 最近よく聞かれますが、私の知る限り、特に道南のクマは気性が荒いとか、そういうようなことはないと思います。
やはり地形的な影響で、人とクマの距離が近いということが、問題が多く発生しやすい状況に関係しているのかなと思います。
Q. ヒグマを駆除することについては、反対する意見もあります。
A. 北海道のヒグマというのはやはり北海道民にとっては大事な存在だと思いますし、ヒグマとの共存を進めていくことが大切だと思います。
一方で、やはり人の安全を守るということも非常に重要ですので、その二つの目標を同時に達成するために、すみ分けによるゾーニング管理ということを導入したところもあります。
人の安全を守るためには、人の生活圏に入ってきたクマは、確実に駆除するというようなことも、非常に重要な取り組みだと思いますので、決して全てのクマを駆除すると言っているわけではなく、共存を目指しながら人の安全を守るために必要なことが、駆除しますよということだろうと思いますので、ご理解いただければと思います。
対策1. ヒグマを生活圏に入れない
Q. ヒグマと人の生活圏が近い地域では、どのような対策が必要なのでしょうか?
A. “クマと共存しながら人の安全を守る”という大目標がありますが、そのためにはやはりクマの生息する場所と人の住む場所を極力離しておくということがまずは大事です。
そのためにはすみ分けを実践するための「ゾーニング計画」というのが重要な役割を果たすと思います。
人の生活圏に入れないために、草刈りや電気柵の設置といった対策が、まずは大事です。
また森林の中でも、特に人の生活圏に近いところでクマの密度を下げる、またはそこに定着しているクマをなくしていくような対策を通じて、(人への)警戒心がないようなクマが人の近くにいない状況を作るということがまずは大事なことだと思っています。
ゴミ出しについてもやはり基本ルールである、収集日の朝にしっかりと出すということを徹底してほしいですし、事業者が夜から外に出さなければならない場合でも、決してクマに壊されないような構造、または匂いの漏れないような構造のものの中に、保管していただくことが大事だと思います。
対策2. 電気柵設置の注意点

Q. 道南では電気柵の切れ目となる、沢や道路から侵入したケースもあると聞きますが、設置にあたっての注意点について教えてください。
A. 電気柵は、まずは適切に設置していただくということが大事です。
地上から20センチの高さに1本目を張るというような、必ずクマに適した張り方をしないと、せっかく張ったのに侵入されてしまいますし、『電気柵効かないんじゃないか』というような雰囲気になるかと思いますので、まずはクマ用の張り方をしっかりとしていただくことが大事だと思います。
ただどうしても、川沿いや道など、電気柵だけでは防げないような場所も必ず出てくると思います。
そういった場所からの侵入は100%防ぐというのは難しいかもしれません。
まずできるところはしっかり対策をしていただいて、万一侵入してしまった場合に対して、地域でしっかりと侵入してきた個体を追い払うとか、捕獲するとか、そういった緊急的な対応をしっかりできるような体制を整えておくことも重要かなと思います。
8月前後の時期は、山の中で冬眠前のクマの食べ物となる木の実などがない時期である一方、畑では農作物や果樹が実りの時期を迎えていて、どうしても誘引されてクマが出てきてしまいます。
まずは、誘因物があるようなところはきっちりと電気柵で囲っていただくということが必要だと思います。
また、いくつかの町で取り組みがあると思いますが、小さな集落であれば集落を丸ごと囲むというようなことも大事だと思います。
特に過去に侵入してきた場所は把握できていると思いますので、そういうところは重点的に、手厚く柵を設置していくというようなことが必要だと思います。
対策3. 個人でできる対策とは
Q. 個人や地域でできる対策について教えてください。
A. 個人や地域では、クマの出没が起きるような侵入ルートがあるところは、草刈りなどを進めていただくことと、畑や家庭菜園などクマを誘引してしまうものがあるところでは、しっかりと電気柵を設置するなど、クマが近づいてきても決して食べられないような、そういった対策を徹底していただきたいと思います。
人の生活圏の中では、ふだんからクマよけの対策をするのは難しいと思います。
クマの出没情報がある地域では、早朝や夜間などの外出を控える、犬の散歩などもクマの住むようなやぶや森の近くではしない、というようなことが必要かなと思います。
街の中でクマと出会ってしまったときには、決して背中を向けて走り出さずにゆっくりと後ずさりし、可能であれば建物や車の中に入る、それが難しい場合にも、電柱や車の影など何かの陰に隠れて目立たないようにすることが、まずは大事かなと思います。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。



