千葉大学などは、ぜんそくなどのアレルギー疾患が悪化する仕組みの一端を明らかにした。免疫の司令塔となる免疫細胞が脂肪酸を取り込んで分解し、病気を悪化させる細胞に変化していた。新たな治療法開発につながるという。研究成果をまとめた論文を科学誌「サイエンス・イムノロジー」に掲載した。
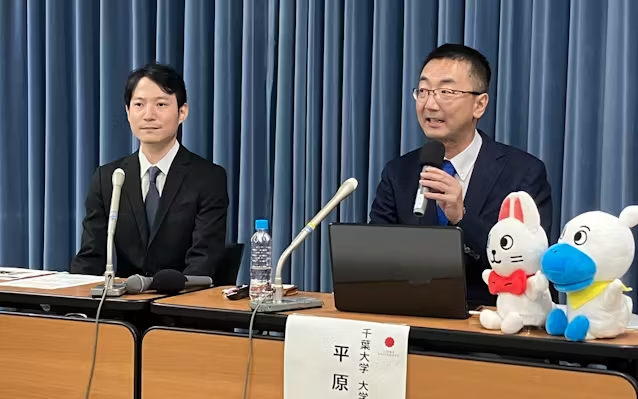
免疫細胞は通常、ウイルスや細菌などの外敵から体を守るために働く。一方、アレルギー疾患の患者では病気を悪化させる免疫細胞が増える。だが、その詳しいメカニズムはわかっていなかった。
研究グループはぜんそくを起こしたマウスの肺の様々な細胞でどのような遺伝子が働いているかを解析した。すると正常な免疫細胞が病気を促す細胞に変化する過程で、脂肪酸の貯蔵や代謝に関わる遺伝子が働くことがわかった。
肺の炎症を起こした場所を詳しく調べると、特定の脂肪酸が増えていた。それらの脂肪酸を正常な免疫細胞が取り込み、体内で細胞内の不要物を処理する仕組みや脂肪を分解する酵素を使って分解する様子が観察できた。
免疫細胞が蓄えた脂肪を分解する酵素をマウスで人工的に無くしたところ、病気を促す免疫細胞が減り、ぜんそくの症状も改善した。またアレルギー疾患の一種である慢性副鼻腔(びくう)炎の患者の鼻の粘膜にできたポリープを観察すると、免疫細胞が含む脂肪に酵素などが付いて分解していた。
記者会見を開いた千葉大学の平原潔教授は「脂肪を分解する酵素はこれまで治療法開発のターゲットになっていなかった。(今回の研究成果は)新しい治療法の開発につながる可能性がある」と話した。
【関連記事】
- ・アレルギー低減卵、広島大学とキユーピー開発 27年度以降実用化へ
- ・ノーベル賞坂口氏と起業、京大・河本氏「アレルギー治療など貢献」
- ・鼻づまりが1カ月続き、臭いを感じにくいなら 副鼻腔炎疑い耳鼻科へ
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。



