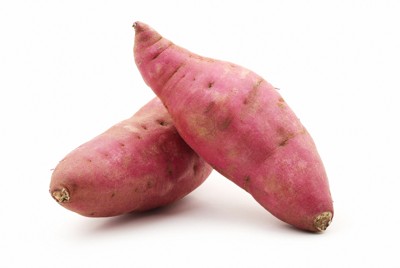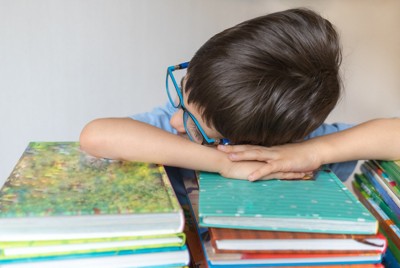京王線を走る平たい車両。「サヤ912形」は、京王電鉄で唯一、屋根のない無蓋(むがい)車です。一体何のために使われるのでしょうか。高幡不動駅(東京都日野市)近くの車両基地にお邪魔し、その謎を探ってきました。

全長20メートル。板状の車体は明るい灰色に塗られ、黄色い保護柵が立てられています。無蓋車という言葉から感じるようなぶこつなイメージはありません。それもそのはず2016年に導入されたばかり。京王線の現行車両では、現・5000系に次いで2番目に新しい形式です。
「新宿駅などの地下駅に空調装置を運ぶ際などに使っています」。教えてくれたのは京王電鉄で車両企画を担当している矢島隆之課長補佐です。地下駅も複数ある京王線では、地下からの重量物運搬にこうした車両が役に立つのだそうです。

車体中央には十字の白線が描かれていて、荷物を載せるときには重量バランスの目安にするそうです。台車はもともと旅客電車についていたものを転用。運転最高速度は110キロですが、荷物を積載する場合は低速で走行します。

このサヤをけん引するのは、事業用の電車「デヤ901形・902形」です。外観は旅客電車の9000系を踏襲していますが、前面は夜間に見えやすいようにしつつ、旅客電車とも区別するため黄色に塗装されています。また、床下に除雪に使うことのできる排雪板が装備されているのも特徴です。

車内も見せてもらいました。自動列車制御装置(ATC)の車上装置や蓄電池、ブレーキなどに使う圧縮空気のタンクなどさまざまな機器が搭載されています。「通常の電車ですと2両ですとか3両に分かれて積んでいる装置を1両にぎゅっとまとめて搭載をしているので床下だけでは空間が足りないのです」
デヤの最大の役割は、軌道や架線の検測をする総合高速検測車「DAX」(クヤ911)をけん引することです。デヤ901・クヤ911・サヤ912・デヤ902の4両編成で2カ月に1度、軌道や架線の検測をしています。
取材日はDAXが全般検査のため編成から外されており、デヤにサヤだけが連結された珍しい3両編成になっていました。DAXは12月に全般検査後初の検測走行をする予定ですので、その模様はまた別途お伝えしたいと思います。【渡部直樹】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。