
78image -shutterstock-
<周囲の理解不足や環境とのすれ違いが、発達障害のある人の力を埋もれさせている。見方を変え、職場の仕組みを整えれば、個性は確かな強みに変わる>
自分ではがんばっているつもりなのに周囲から「やる気がない」と言われてしまう。なぜなのか。
障害者の社会復帰を支援する就労移行支援事業所を運営している柏本知成氏は「周囲から誤解されることが多い人に、ぜひ見直してほしいポイントがある」という――。
※本稿は、柏本知成『ポストが怖くて開けられない! 発達障害の人のための「先延ばし」解決ブック』(サンマーク出版)の一部を再編集したものです。
※登場する人物の名前はすべて仮名です。個人情報保護のため、一部の属性や状況についても変更しています。

なぜ「やる気がない」ように見えるのか
大人数でワイワイと過ごすことが好きだという人。
大人数は苦手だという人。
カフェなど、少し雑音がある環境の方が集中できるという人。
自室にこもった方が集中できるという人。
人は誰しも得意なこと、苦手なこと、好きなこと、嫌いなことがあります。
これが、その人らしさであり、その人の「特性」でもあります。
じつはこのような「その人らしさ(特性)」と、仕事場など周りの「環境」が合っていないことがあります。
その場合、周囲から「やる気がない」と「誤解」を受けてしまうのです。
この「誤解」の正体に迫ってみたいと思います。
あるとき、高井ナオキさん(20代男性)が、私の運営する就労移行支援事業所へ転職の相談に来ました。
ナオキさんは、幼いころから人付き合いが苦手。周囲から「変わっている人」だと見られていました。本人も周りの人とは「何か違う」と感じていたため、深く人と付き合うことなく学生生活を過ごしていました。就職してからも、どの職場でも上手くいきませんでした。
「障害への理解がある会社を紹介してほしい」
そう言って、私のところを訪ねてきたのです。
意外な「生きづらさの要因」
彼は軽度の発達障害(ADHD)と診断されていました。
好きなことには何時間でも没頭できる一方で、興味のないことには10分と集中が続きません。
高校卒業後はずっと工場勤務をしていましたが、長時間におよぶ単調な作業は彼の特性には、合いませんでした。
ついぼーっとしてしまったり、他のことを考えてミスをしたりの繰り返しで、しかられつづけていました。
話を聞いていくうちに、彼が感じていた「生きづらさ」の正体が見えてきました。
それは「会社」の問題ではなく、自分自身への「思い込み」にあったのです。
ナオキさんに話を聞いてみると、次のような「思い込み」がありました。
仕事はがまん。勤務中はしかられないこと。ミスしないように気をつける。なるべくボロが出ないよう、上司・同僚とは関わらない......。
だけど、どの職場でも結局自分だけがしかられるから、転職活動でも「障害への理解がある職場」「しかられない職場」探しが最優先。
しかし、ナオキさんが本当に働きたかったのは、「ホビーショップ」でした。
彼の趣味はトレーディングカードゲーム。大会に出場するのはもちろん、YouTubeで専門チャンネルを見ることも好き。いつかそんな環境で働けたらと思っていましたが、人気職のホビーショップ店員なんて夢のまた夢......。
夢だった職場に出会った
そこで、まずナオキさんには、ご自身の特性や自己理解を深めるワークなどに取り組んでもらいました。
その結果、転職も上手くいき、長年の夢だったホビーショップの店員になれたのです。
「毎日、宝物に囲まれて働いているよう。お給料をもらうのが申し訳ないくらい」
トレーディングカードが大好きな彼は、笑顔でそう語ります。
上司からも、「彼の圧倒的な知識量には、本当に助けられています」との評価。
また、いままでの職場では同僚とも上手く馴染(なじ)めずに、存在感を消して過ごしていたそうですが、いまの同僚の方はこう教えてくれました。
「彼の好きな赤色が、職場でブームになっているんですよ」
学生時代は「なんでもできる器用さ」が評価されがちです。
でも、社会に出ると「ひとつの分野で秀でている」ことの方が、はるかに価値があります。
ナオキさんの場合、好きなことには驚くほどの集中力を発揮する一方で、興味のないことにはまったく集中できないという特性がありました。
だから、好きなことを仕事にすることが効果的でした。
好きだからこそ、学びつづける。学びが深まるから、パフォーマンスが上がる。
その結果、仕事でも高い評価を得られるようになりました。
ナオキさんのように、自分の特性と職業がマッチしていないために、仕事で力を発揮できない人は少なくありません。
あなたの周りにいる「やる気がない」ように見える人。その人は本当に、やる気がないのでしょうか?
もしかしたら、その人の特性と仕事が合っていないだけかもしれません。
その人らしい活躍の場所が、きっとどこかにあるはずです。
ADHD脳とASD脳の特徴とは
やる気がないのは、その人の特性と環境が合っていない、ということをお話ししました。
ここからは特性ごとに、なぜ「やる気がない」と見られがちなのかについて、お話ししていきましょう。
発達障害の中でも特に、特徴的な2つのタイプに、ADHDとASDがあります。
それぞれの脳の特性を理解すると、その理由がわかってきます。
「ADHD脳」の特徴
・興味のあることには、驚くほど集中できる
・興味のないことには、まったく集中が続かない
・複数のタスクを同時にこなすことが難しい
・優先順位をつけることに苦労する
最大の特徴は、興味や関心によって大きく集中力が変化すること。
そのため周囲の目には、気まぐれで気分の波が激しいように映ります。
また思いつきの行動が多いので、「あれ? なんでこれをしてるんだっけ?」と、気がついたら、当初の予定とまったく違うことをしていたりします。
感情表現が苦手なASD
「ASD脳」の特徴
・決められたルーティンを重視する
・変更や予定外の出来事に対して、ストレスを感じやすい
・細部へのこだわりが強い
・情報を文字通りに受け取る傾向がある
ASD脳は、秩序と一貫性を重視する傾向があります。
ASDの人は感情表現が苦手。コミュニケーションの困難さを感じている人が多いです。
そのため周囲から、一緒にいても何を考えているのかわからない、周囲が盛り上がっていてもつまらなそうに見えてしまうなど、本人の気持ちと、周りからの見られ方にギャップが起きやすいのです。ひとりでいることを好む人が多いといわれていますが、大人数で過ごすことが嫌いなワケではなく、苦手なのです。
刺激に対する反応がアンバランスな併発型
ADHD脳とASD脳を併せもつ「併発型」の特徴
・強いこだわりがありながら、実行に移すための集中力が続かない
・計画は緻密に立てられるが、実行の段階で予定通りに進まない
・新しいことへの興味は強いが、変化に対する不安も大きい
併発型の方の特徴は、刺激に対する反応がアンバランスになりがちなこと。
ADHDの特性から、内側からのアクセルがききやすい――自分の興味・関心があるものに飛びつく――傾向にあります。
しかし同時に、ASDの特性から、外側からのブレーキへ過敏に反応――他人からの予定変更やルール違反があると動けなくなる――ことにもなります。
そのため突然スイッチが入り、猛烈に動き出したかと思うと、直後の小さな変化やトラブルで動けなくなるという「極端な起伏」が目立ちます。
これらの特性は、その人固有の「脳の働き方」です。環境に応じて対処方法を適切に調整することで、それぞれの特性を強みとして活かすことができます。
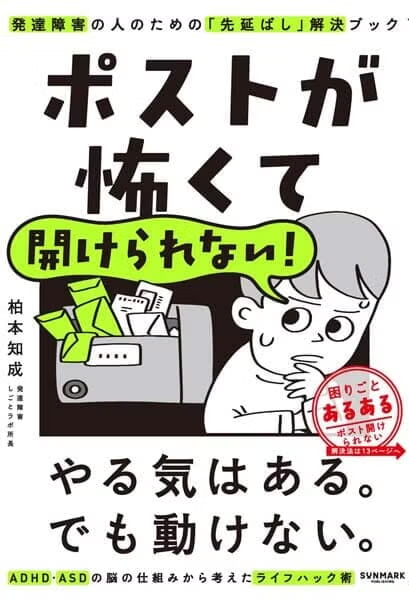 柏本知成『ポストが怖くて開けられない! 発達障害の人のための「先延ばし」解決ブック』(サンマーク出版)(※画像をクリックするとアマゾンに飛びます)
柏本知成『ポストが怖くて開けられない! 発達障害の人のための「先延ばし」解決ブック』(サンマーク出版)(※画像をクリックするとアマゾンに飛びます)

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。



