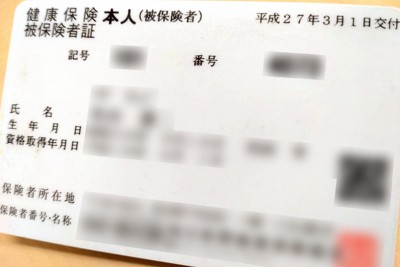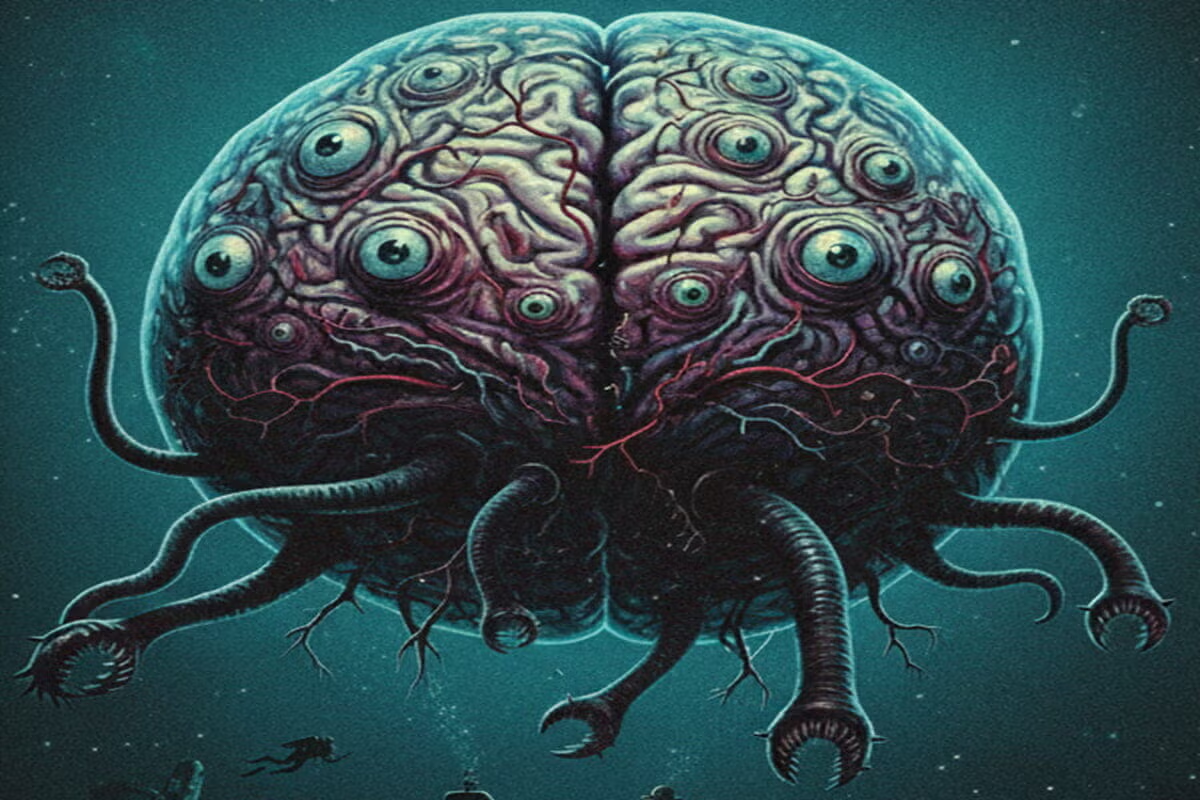
「全身が脳」かもしれないのは、我々もよく知る生物だ Generated by AI
<今まで「脳がない」と思われていた生物。実は脳がないのではなく「全身が脳」だった>
万物の霊長である人類でも、脳は体重の2~3%を占めるに過ぎない。しかし、欧州の研究チームは「全身が脳」という、俄かには信じがたい生物が存在することを発見した。
【写真・動画】「全身が脳」の生物の神経系とその生態
欧州の研究チームによれば、この生物の神経系はヒトのような脊椎動物の脳と似た遺伝的構造を持っていることが分かったという。全身には驚くほど複雑な中枢神経系が備えられており、本質的には「全身脳」として機能している。まるで全体が「頭部」でできているかのようだ。
「従来型の中枢神経系を持たない動物であっても、脳のような構造を発達させ得る」と、ベルリン自然史博物館の生物学者ジャック・ウルリッヒ・リューターは述べた。
「複雑な神経系の進化をどう捉えるかという点で、根本的な転換を迫る発見だ」
ウルリッヒ・リューターらのチームが研究対象にした「全身脳」生物は「Paracentrotus lividus」、つまりヨーロッパムラサキウニだ。ウニの他、ヒトデ、ナマコ、クモヒトデなどが属する棘皮動物門には、成長するにつれて体の対称性が変化するという特徴がある。
例えば、人間の身体は「左右対称」であり、体を左右二つに分けると、左右は相称(概ね対称)となる。実際、全動物種の99パーセントにあたる100万種の動物がこの特徴を持っており、「左右相称動物」と大きく分類されている。
もちろん、左右相称動物であっても、非対称の部分は存在する。例えば、人間の心臓は胸の中央よりやや左にあり、肝臓は主に右側に位置している。
ウニは光も感じられる?
棘皮動物は、自由に泳ぐ左右相称の幼生として成長を始め、成体になると五方向の放射相称(五放射相称)という形に変化する。
ウルリッヒ・リューターらが着目したのは、この相称性の変化だ。研究の目的は、同一のゲノムがいかにして2つのまったく異なる相称を生み出すのかを解明し、この変化を可能にする細胞を特定することだったのだ。
研究チームは、変態を終えたばかりの若いヨーロッパムラサキウニに含まれる細胞の種類を詳細に解析した。
結果、成体のウニの体は全身が圧倒的に「頭部に似ている」構造となっており、「胴体」と呼べるような領域は存在していないことが明らかとなった。
実際、他の動物種であれば胴体の構造を司る遺伝子は、ウニの場合、消化管などの内部器官や、運動、呼吸、摂食、排泄といった機能を担う「水管系」と呼ばれる器官群でしか活動していなかった。
研究チームが特に注目したのは、ウニに存在する神経細胞の種類の多さだ。棘皮動物に特有の「頭部」に関連した遺伝子だけでなく、脊椎動物の中枢神経系で見られるような、より古くから存在する遺伝子も発現していたのだ。
このことから、ウニは今まで考えられていたような「単なる神経節と神経網の集まり」ではなく、全身にわたって統合された、脳のような極めて特異な神経系を備えている可能性が浮上してきたのだ。
さらに、ウニの体全体にわたって、光を感知する細胞が存在していることも判明した。これらの細胞は、人間の網膜に見られる構造と類似しているという。ウニの神経系の大部分は光に反応し、光によって行動が制御されている可能性もある。
2種類の光受容体を持つ細胞も見つかっており、ウニが光を高度に感知・処理する能力が備わっている可能性が浮かび上がっている。
ただし、ウニは「全身が脳」であったとしても、人間が万物の霊長たらしめるような高度な脳機能があるかどうかは別問題だ(実際、鳥類などのように、脳の体重に占める割合が人間より高いケースもある)。ウニの神経系の機能はどれほどのものなのか、今後の研究の進展が待たれる。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。