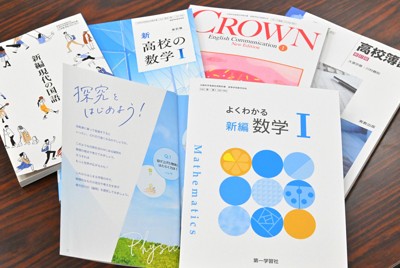大型の巻き貝「ジャンボタニシ」(スクミリンゴガイ)の水稲被害を、梅酒を漬け終えた実の投入によって減らすという奈良県立磯城野高校(田原本町、市原定典校長)農業クラブの研究成果がまとまった。実験苗床、実際の水田とも、何も投入しなかったものと比べて良い結果が出た。23日に橿原市の橿原神宮であった市農業祭で成果をポスター発表した。
梅酒を漬けた後の実は全国で年約9000トンが廃棄されているとみられるという。この有効活用も狙った。
吉野町の美吉野醸造から梅酒を漬け終えたばかりの梅数百キロの提供を受け、6月22日、校内で実験スタート。長さ約80センチ、幅約50センチの苗床を数個用意し、ジャンボタニシを5匹ずつ入れ、稲の苗24本ずつを植えた。梅の実25グラム、同50グラムを入れたものと無処理(何も入れない)に区分。その結果、1回目(6月22日~7月4日)は無処理だと苗は全滅したのに対し、25グラムだと15本、50グラムでは21本も生き残った。2回目(8月3~15日)も無処理は全滅、25グラム5本、50グラム19本が生き残り、いずれも50グラムで最も高い効果が出た。

同じく6月22日に、実際の水田約1000平方メートルでも実験。この田の東側に梅の実100キロを投入し、西側には何も投入しなかった。玄米の収量は例年、西側の方が1~2割多いというが、10月初めに収穫したところ、逆に西側520キロ、東側560キロと東側の方が多くなった。田の周囲にある苗3000本のうち、欠損したものも、西側198本に対し、東側は124本に抑えられたという。
なお、苗床レベルでは別途、酒かすも投入して実験。ジャンボタニシはことさら好むとみられ、梅の実以上の効果があったが、水田では時間がたつうちに外部へ流れ出てしまうため、利用しづらいという。
生徒たちはハシブトガラスのジャンボタニシ捕食にも注目。カラスの鳴き声を現場で再生しておびき寄せることも期待したが、カラス自体による農作物の食害を懸念し、見合わせた。
研究成果は、12月に近畿ブロック審査がある農林水産省「みどり戦略学生チャレンジ」にエントリーされる。
農業クラブで研究を指導する吉田宏教諭は「規模を拡大して来年も続けたい。梅の実の投入に労力がかかるため、田植え時に梅の実を(自動で)落とせる機械の試作を、連携している王寺工業高校に依頼したい」と展望する。
2年の山森充貴(あつき)さん(17)は「ジャンボタニシと共存する道が見えてきたかもしれない。研究が実用化され、食害が減ればうれしい」と話している。【梅山崇】
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。