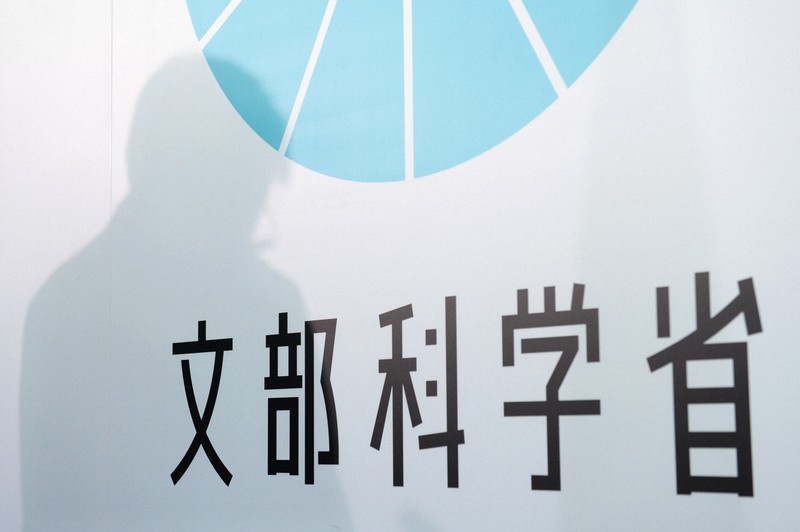
文部科学省は、正式導入が検討されているデジタル教科書について、教科の特性や児童生徒の発達段階に応じた活用の方法を示した指針を策定する方針を固めた。関係者への取材で判明した。5日の中央教育審議会(文科相の諮問機関)の作業部会で説明する。
デジタル教科書は教科や学年、年齢によって向き、不向きが生じる可能性があるため、教科書会社が編集・発行をしやすくし、自治体も採択をしやすいようにする狙いがある。
中教審の作業部会は2月、議論の「中間まとめ」で①紙媒体②完全デジタル③双方を含むハイブリッド――の3形式から教育委員会が選べるようにするとの案を了承した。文科省は2030年度以降の次期学習指導要領の実施に合わせた導入を目指している。
関係者によると、作業部会には「紙、デジタルそれぞれに良さがあり、学習場面や学年などによって異なる」といった意見も寄せられており、文科省はどういった学年や教科、学習場面デジタルの活用が期待されるかなど、デジタル教科書の構成や活用のあり方を指針で示す。策定にあたっては関係団体への意向調査も実施する。
デジタル教科書は現在、「代替教材」との扱いで教科書のように検定や無償配布の対象にはなっていない。正式に教科書と位置づけるには学校教育法や著作権法の改正が必要で、文科省は26年の通常国会に改正案を提出する。指針は法改正後に策定する。
文科省はデジタル教科書の効果として、動画や音声などの活用により深い学びにつながると見込む。現在の教科書でもQRコードから動画などを読み込めるが、内容は検定対象外だった。
デジタル教科書が正式に導入されれば、検定の対象範囲が膨らむ可能性もある。次期学習指導要領を巡る議論では教科書について内容や分量の精選が必要との意見も出ており、デジタル教科書の導入にあたっては動画の分量などに制限を設ける案が今後検討される見通しだ。【斎藤文太郎】
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。



