市井社長の提示した「あなたにとって止まる勇気は何ですか?」という課題に対し、多数の投稿をいただきました。紙面掲載分を含めて、当コーナーでその一部を紹介します。
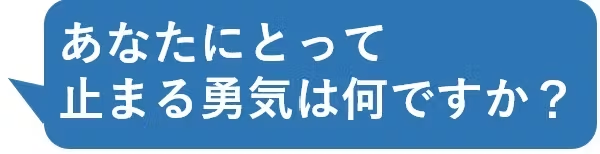
■受け身の自分を変える
高橋 怜那(産業能率大学経営学部3年、20歳)
私はこの夏、就職活動の一環としてインターンシップに参加した。「周囲が行っているから自分も」という受け身の理由で始めたが、終えると、「効率的に動いているようで、自分が大切にしている軸を見失っているのではないか」と感じた。
そこで私は「自分らしさを大切に主体的にやりたいことをする」姿勢に切り替えた。具体的には、まず自分がワクワクする瞬間はどんな時か振り返り、人の挑戦を支えることに喜びを感じる性格であると分析した。その後は、自分の価値観に合った企業を選ぶようになり、インターンシップへの参加目的を明確にしてから臨むようになった。
この経験から、周囲に流されず一度立ち止まって自分の軸を見直すことの大切さを学んだ。私にとって「止まる勇気」とは、受け身な姿勢をやめて主体的に動く、切り替えスイッチのようなものだ。今後もこの経験を生かし、周りに流されそうになった時は立ち止まって自分らしい選択を積み重ねていきたい。
■大切なものに向き合う
家田 知明(会社員、63歳)
私にとって「止まる勇気」は、人生の本質に立ち返り、大切なものと向き合うための選択だ。2021年に母が他界し父がひとり暮らしになった。要介護度が進む中、父は住み慣れた自宅での暮らしを強く望んだ。その気持ちは住まいへの愛着と、家族への変わらぬ思いからくるもので、その思いを深く理解できた。
私は30年以上勤めた会社で常に走り続けてきた。介護休業制度は知っていたが、職場に迷惑をかけるという思いから取得する考えはなかった。しかし認知症が進む父の姿に直面したとき、私が担わなければ誰もいないことに気づき、初めて「立ち止まる」選択をした。介護時短勤務制度を活用し、父の生活を支える時間を確保したのである。父との心のつながりを育み、感謝の気持ちを示す姿勢こそが止まる勇気だった。
最期に父の旅立ちに穏やかに向き合えたことは人生の大切な節目となった。立ち止まったことが、仕事にも人生においてもより深い意味と方向性をもたらしてくれている。
■肩の力を抜くこと
矢吹 美汐(学校法人石川高校3年、17歳)
私にとって止まる勇気とは、肩の力を抜くことだ。これまでの私はつらい時、「止まり方」が分からなかった。そんな時、「適当と気楽が一番」という言葉に出合った。言葉通り、一度深く考えることをやめて力を抜いてみると、心が軽くなり、歩き出す余裕ができた。私は止まることは、次の一歩への準備なのだと気付いた。立ち止まったからこそ動き続けていた時には見えなかった自分に気付き、「ゆっくりでよい」と思えるようになった。
今でも悩みは尽きないが、その時の経験があるからこそ無理だと感じたら止まってよいと思える。立ち止まる勇気が、自分と未来を見つめ直すきっかけになると信じている。私と同じように「走り続けなければ」と苦しんでいる人に伝えたい。止まることは、何もしないということではなく、自分を許し、成長するための行動である。止まり方は人によって違うが、止まることで本当の自分を知り、誰もが自分らしく未来に向かって歩んでほしい。
【以上が紙面掲載のアイデア】
■周りの優しさに気付く
工藤 咲南(中央大学経済学部2年、20歳)
自分のことで精いっぱいなときほど、周りの人の優しさやありがたみを見失いがちになる。そんなときこそ、止まる勇気が必要だ。
受験を控え、苦手な科目の点数が伸びず、焦っていたことがある。ある模試が終わり、迎えに来てくれた父の顔をふと見ると、疲れた表情をしていた。しかし、私が車に乗り込むと、明るい声で出来具合を聞いてくれた。遅い時間に図書館で待ってもらうことも、当たり前のようになっていった。
勉強でいっぱいいっぱいになると、母は毎晩、相談に乗ってくれた。忙しい中でも、両親は私を支えてくれていることに気付いた。受験生は勉強だけをしていればよいわけではない。もっと家事を手伝ったり、両親に感謝を伝えたりするべきだと思った。
今、精いっぱいになっているときこそ、一度止まってみるようにしている。すると、自分を支えてくれている存在と、そのありがたみに気付くことができる。
■止まって広がる世界
瀬川 貴子(会社員、53歳)
ビジネスパーソンは、止まらずに進み続けることが美徳とされがちだが、結婚や出産、育児や介護などでキャリアを一時的に中断せざるを得ない時もある。
そんな時、不安や焦る気持ちが生まれることもあるだろう。従来はそれを「遅れ」や「ブランク」と捉える傾向があった。しかし、そんな人生の節目で立ち止まったからこそ気づける「視点」や「感情」がある。
家族と向き合う時間は、自分自身を見つめ直し、支え合いや助け合いのありがたさを知る機会となる。止まることで広がる世界は、進み続けるだけでは得られないものがある。つまり、止まることは自分らしいキャリアを描くための「充電期間」なのだ。
止まることは、決して競争からの脱落ではない。誰もが安心して立ち止まれる社会こそが、多様な生き方を尊重し合える社会ではないだろうか。何かをつかんだら、何かを捨てないといけないという時代ではない。「止まる勇気」こそが、そのような社会をつくる第一歩になるのだ。
■発信前の立ち止まり
田村 結(駒沢大学グローバル・メディア・スタディーズ学部4年、21歳)
誰かにメッセージを送ったりSNSで発信をしたりする前には、必ず一度立ち止まり、確認してから送信や投稿をするようにしている。自身の見解とは異なる意図で相手に伝わったり、誤解が生まれたりすることを避けるためにだ。当たり前のことだが、それは今、非常に大切な立ち止まりの瞬間なのではないだろうか。
スポーツ観戦をしている際、選手がミスをしてしまったとき、やじを飛ばす人を目にすることがある。SNSでは、その投稿を見たファンの人まで傷ついてしまうような内容を目にすることもある。スポーツだけに限らず、日常の中でも目にすることが多い。
愛のムチだという意見もあるかもしれないが、言葉一つで心や命を奪われてしまうこともある。だからこそ、発信する前に一度立ち止まって考える。そうすることで、違う言葉を見いだすことができ、傷つける言葉ではなく応援や励ましの声に変えられるのではないだろうか。様々な手法で発信できる時代だからこそ、原点に立ち返り発信前に立ち止まることが必要だ。
■自信を取り戻すための力
清水 亨(会社員、63歳)
長年務めた取締役を退いたとき、私は自分の存在意義を見失い、立ち止まることを初めて余儀なくされた。それまでの肩書や自分を縛り付けていた常識をいったん手放す必要があると実感させられたのである。この立ち止まりは、私の人生において、自分自身を深く見つめ直す貴重な機会となった。
すべてをリセットし、これまでの経験や知識を生かして「社会に貢献できることは何か」と自問した。その結果、デジタルトランスフォーメーション(DX)への知見で地域に貢献するという新たな道が見えた。市庁舎整備審議会委員に応募したのは、その第一歩だった。
この経験を経たからこそ「止まることは後退ではない」と確信を持って言える。むしろ、これまでの歩みを振り返り、自分の持つ価値を再定義し、新たな一歩を踏み出すための前向きな選択だ。私にとっての「止まる勇気」とは、一人の人間としての自信を取り戻し、次なる挑戦へと私を導いてくれた力だった。
■自分の発言を振り返る
鈴木 凛々(学校法人石川高校1年、16歳)
人と話しているときに止まることができるかどうか。私はこれが、いい人間関係を築くために必要不可欠なことだと思っている。対話中に止まるとは、自分の発言を適宜、客観的に振り返ることだ。
私は人と話しているとき、自分の発言に気を配るよう心がけている。例えば、自分の言葉や話し方が相手にどんな印象を与えたか、知らないうちに傲慢になっていないか、人によって異なる解釈ができてしまうような曖昧な言葉を使っていないか、などだ。気を配るべきことはたくさんある。
会話しながら、うまく自分の発言を客観的に振り返ることができているときは、コミュニケーションがスムーズで、いい人間関係が構築できる。反対に、対話中に止まることができないと、話が自己中心的になりがちで、相手を困らせたり傷つけたりしてしまうことが多い気がする。
人と関わるからには良好な関係をつくりたい。そのために私は、対話中に止まれる人でありたい。
■とどめを刺さない
村山 悠子(会社員、45歳)
私の止まる勇気は、人と話すときに「とどめを刺さない」ことだ。
仕事や生活の中では、思い通りにいかず、感情が波立つ場面が多々ある。そんな時こそ、祖母から聞いた「口から出た言葉は二度と戻らない」という教えを思い出す。たとえどんなに言いたいことがあったとしても、一呼吸おいて言葉を選ぶよう心がけている。
とっさに感情のまま発した言葉は、相手を深く傷つけ、信頼を失う大きな要因となり得る。だが、逆に立ち止まって、冷静さを取り戻すことができれば、相手の考えに耳を傾ける余裕も生まれ、結果として建設的な対話や前向きな解決策につながることもある。
その積み重ねが、円滑な業務の遂行や人間関係の安定を支えていると感じることもしばしばある。一見すれば地味で当たり前の行動に映るが、長い目で見てみると、信頼関係や安心感をもたらす。そして、何よりも大切な土台を築く力につながるのだと信じている。
■寄り添うために止まる
久保田 高徳(立命館大学文学部4年、21歳)
私にとって止まる勇気とは、「寄り添うために立ち止まる」ことである。能登半島地震の避難所でボランティアをした際、私は物資を仕分け、炊き出しを手伝い、次々と作業をこなすことに必死だった。しかし、炊き出しの列に並ぶおばあちゃんにお茶を渡した時、「ありがとう、あなたも一緒に飲みなさい」と声をかけられた。その瞬間、私は支援する側とされる側という立場を超え、「共にいる人」として受け入れられたと感じた。立ち止まり、言葉を交わし、同じ時間を共有することこそが、人の孤独や不安を和らげる最も大きな支えになるのだと実感した。
避難所には、静かに泣く子どもや、仮設トイレに長い列をつくる高齢者の姿もあった。そうした過酷な状況の中で、私は「止まることは怠慢ではなく、人と関係を築くための余白である」と学んだ。この気付きは、教育者を志す私にとって大切な指針になった。慌ただしい日々の中でも、立ち止まる勇気を忘れずに人と向き合っていきたい。
■自分を見つめ直すことから始まる
仙波 仁子(公務員、60歳)
今夏で還暦を迎えた。30余年勤めてきた教員生活に終止符を打つ。組織から離れる。いつも教室に行けば待っていてくれた子どもたちは、いない。自分で稼ぐとはどういうことか。徹底的に60年を棚卸しした。
仕事とは人の役に立つこと、収入はその対価。ならば、自分のスキルを生かすすべが社会にきっとある。もがき苦しんできた人生、培ってきた「楽しい」を、今度は幅広い世代に提供してみよう。
5年前のコロナ禍、学校は止まった。オンラインもままならないあの時、教材を「近くの山」で見いだした。竹を切り、音楽を奏でた。どのグループからも異なる音があふれ、低く高く、力強く、そして優しかった。あの音、あの響きは、最適な行動が作り出した。
止まるとは、自身ができること、つまり過去を見つめ、今この時最適なものを見いだす、次へつなぐ大切な行為だ。人生100年時代。5分の3を見つめ直したことで、残る5分の2の未来へ新しい扉が開かれた。
■手を止めて見える素描
岸田 夏(関東学院六浦高校3年、17歳)
私は美術系大学を目指している。美術系大学ではほぼ必ずデッサンの課題が出る。その場にあるものを置かれたとおりに描き、3〜7時間で描き終える必要がある。
私は筆が遅く、時間を気にし、手を止めないように描く。制限時間内に終え、未完成にならないようにと。だが、手を止めて離れると、形の狂いや見落とした影、足りない表現など様々な問題が見えてくる。止まる時間が作品をより良いものに変えるのだ。
制限時間があると、私は停止している1分1秒も惜しく、周りの鉛筆の音に焦り、手を止めることが怖くなりがちだった。だが、描くことを一旦止めて、落ち着いて作品と向き合うと、見えなかった問題点が見えるようになり、止まる時間が大事だと理解した。それ以降デッサンを描く際には毎回、手を止める時間を作るようにしている。止まる時間が長いほうが良い作品を描けるようになり、突き進むことが毎回正解ではないと実感した。
■自分なりの時間
山田 智也(不動産会社経営、45歳)
23歳で結婚し、妻と二人三脚で歩んできた22年。息子たちも成人し、私も45歳になった。最近は父を見送り、お世話になった先輩たちも次々に世を去っていく。振り返る間もなく、気づけばここまで駆け抜けてきたように思う。
この夏、母と妹、そして家族で(亡き父や祖父母の写真も持って)はじめてパリを訪れた。早朝に一人セーヌ川沿いを歩き、開店したばかりのカフェでコーヒーを飲み、本を開く。何気ない時間のはずなのに、これまで流れていなかった別の時間を見つけたように感じた。
日常では予定や仕事に追われ、立ち止まることを忘れがちだ。忙しさに我を失うこともある。だが旅先で止まったことで、時間が有限であること、そしてその流れを決めるのは自分自身なのだと再認識した。
私にとって「止まる勇気」とは、変えられない大きな流れをひとまず受け止め、今ここに在ることに感謝し、静けさの中で自分なりの時間を味わうことなのかもしれない。
■正直に自分と向き合う
永沼 佳子(学校法人石川高校1年、16歳)
全力で走っている時、視界はクリアではなくなる。左右の視野はスピードに流されてぼやけ、遠くに見えるゴールだけに集中する。
私は昨年、半年ほど駅伝に打ち込んだ。練習が終わった後は、チームメートと目標を話しながら帰るのが日課だった。私は初心者だったため、後れをとらないように常に全力で練習に取り組んだ。しかし大会前、それまで明確に見えていた目標に届かないことに気付いた。この時、私は「止まる」ことを決意した。
立ち止まって初めて気付いた。今まで全力で取り組んでいたのは不安を隠すためだった。駅伝で上の成績を目指すためではなく、チームメートより能力も経験も劣る自分の弱さが見えないように、必死だった。しかし、止まったからこそ今まで無意識に目をそらしていた自分の弱さを直視し、受け入れることができた。そして、自分の走りで「チームに貢献したい」という本当の思いに気付いた。私にとっての止まる勇気とは、正直に自分と向き合う勇気である。
■役職定年も悪くない
本田 常章(会社員、61歳)
役職定年を機に、職場の風景が大きく変わった。管理職としての責任とそれに伴う諸々の権限を手放すことになり、給与などの待遇面も大きくレベルが下がった。多くのビジネスパーソンの先輩たちが直面してきたと思われるこの現実に、私も当初、大いに戸惑った。今までの部下が上司になったことによる人間関係の再構築、毎月の生活費のやり繰りの大幅な見直し──。苦労は多かった。
しかし、あながち悪いことばかりではないことにも気付いた。管理職としての業務から解放されたことで、広く仕事を捉えなおすことができた。それによって後進にアドバイスできる余裕が生まれたし、終業後には、ずっと習いたかった外国語講座に通う時間もできた。仕事もプライベートも充実してきたのである。
役職定年によって半ば強制的にではあったが、流れから外れて立ち止まることで見えてきた新しい生活は、とても新鮮だ。人生100年時代の後半に向けて、いいスタートが切れたと思う。
■胸を張って話せますか
後藤 葵琉(会社員、26歳)
私にとって「止まる勇気」とは、目標に向かって進む中で、自身の行動が本当に正しいのかを問い直すための、誠実で戦略的な一時停止だ。単なる停滞や後退ではなく、より良い未来へ向かうための重要な羅針盤の確認作業だと考えている。
その際、3つの視点で自問する。第1に「関わる人すべてに公正か」。自分の利益や効率のために、誰かを不当に扱っていないか。第2に「社会に堂々と説明できるか」。その判断のプロセスと結果は、公明正大で透明性があるか。そして最も重要なのが「家族や友人に胸を張って話せるか」だ。
これらの内面的な問いに少しでも曇りがあれば、立ち止まるべきサインだと捉える。そして立ち止まった後は、一人で抱え込まずに信頼できる上司や同僚に相談し、客観的な意見を求める。この一連の行動こそが、目先の成果やプレッシャーに流されず、長い期間にわたって続く本質的な信頼を築く「止まる勇気」だ。それは自分の良心を守り、持続的な成長のために不可欠だと考えている。
日本精工・市井明俊社長の講評
今回、これまでで最も多くの投稿をいただきました。ありがとうございました。私自身、なかなか止まる勇気を持てず、止まるのが苦手だなと思っているので、皆さんのご意見から大いに勇気と元気をいただきました。

「受け身の自分を変える」は、インターンシップの体験に基づいています。周囲の友人たちがどんどん就職活動を進めているのをみると、あせるのは当然で、その心情はよく理解できます。それでも勇気を出していったん止まることで、自分が何をしたいのか、明確になりました。止まることは主体的に動くことへの切り替えスイッチ、その通りですね。自ら選んで止まる。それにより、気づかなかった自分の価値観を再認識する。素晴らしい体験ですね。
「大切なものに向き合う」は同世代ゆえ、大いに共感しました。親の介護で仕事を離れるのは、会社員というキャリアからみれば一時停止ですが、介護へ挑戦することは、新しい始まりです。止まることは、動くことへのプロセスです。我が社にも介護休暇制度があり、利用する社員は増えています。実際に介護休暇を取得し、どう思ったか。これまで利用者の声を聞く機会が少なかったので、今後はしっかり意見や感想を聞き、制度改善につなげます。会社として、いったん止まるチャンスを与えてもらいました。
「肩の力を抜くこと」は17歳の高校生とは思えない、しっかりした内容でした。走り続けねばと苦しむ人たちに向かって、「止まることは自分を許し、成長する行動だ」と呼びかけています。止まる勇気だけでなく、止める勇気を持っておられると感心しました。人生、うまくいっている時は余裕があるので、止まりやすい。逆に厳しい時、苦しい状況の時ほど、止まるのは難しい。自ら止まる勇気だけでなく、止まれずに苦しんでいる人を止めてあげる勇気も持ち合わせれば、社会はもっと良くなると思います。
◇――――――◇
注目している7人組女性アイドルグループがある。全員ダンスがうまい。その中でひときわ目立つメンバーがいる。高校時代はダンス部、運動能力を競う「SASUKE」というテレビ番組に出場するほど、体幹が強いゆえだと思っていた。
ある時、気がついた。この人のダンスがうまいのは止まるからだと。流れるような激しい振り付けの中、時間にすればゼロコンマ何秒か、彼女は止まる。それがダンスにメリハリを付ける。止まることから生まれるものは多い。(編集委員 鈴木亮)

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。



