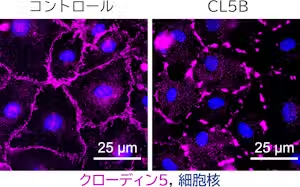救急や集中治療における終末期医療に関するガイドライン(指針)の改定を進める関連学会は30日、人工呼吸など生命維持措置の終了や差し控えに伴う「緩和ケア」の開始時期について、患者が1年以内に死亡する見込みがある場合を目安にすることを指針に付す方針を示した。生命維持措置終了の事例集も盛り込む。
現在の指針は、日本救急医学会や日本集中治療医学会など3学会が2014年に策定した。終末期の状況を定義して生命維持措置の終了などを容認しているが、延命が長期化するケースに対応しておらず、生命維持措置を終えた後の医療行為が具体的でないなどの課題があった。
大阪市内で30日にあった日本救急医学会のシンポジウムで、改定作業に加わった日本緩和医療学会の理事長、木沢義之・筑波大教授は、患者が1年以内に死亡すると見込まれた場合、本人や家族と治療のゴールを話し合うなど緩和ケアの取り組みを始める考え方を示した。その上で「治療と緩和ケアは二者択一ではなく、並行して提供されるもの」と語った。
指針には措置終了の具体的な手順や、終了後の患者の苦痛を和らげる薬剤の扱いなども明記する。
指針改定委員長の伊藤香・帝京大准教授は「終末期の定義はしない」とし、治療の終了や差し控えが考慮される場合、患者本人にとって最善の意思決定ができるよう、関係者が多角的に検討するプロセスを示すとした。生命維持措置の終了に関する事例集を作ることや、期限付きで治療を始め、効果がみられない場合に中止する手法も盛り込むとした。
指針はパブリックコメント(意見公募)を経て、26年3月の日本集中治療医学会で公表する予定。【寺町六花】
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。