
fizkes -shutterstock-
<作家の橘玲さんは「俗に『親ガチャ』といわれ、家庭環境の良し悪しについて語られることが多いが、本当の親ガチャは遺伝にほかならない。幸福度の違いも、実はそれでほとんど説明できる」という――>
豪奢な生活をしている人がうらやましくなることがある。でも、そうしたいかどうかはまた別の話だ。
※本稿は、橘玲、樺山美夏『しんどい世の中でどうすれば幸せになれますか?』(文響社)の一部を再編集したものです。
「親ガチャ」って、やっぱりあるの?
Q 母子家庭で育ち、大学進学時に借りた奨学金を毎月数万円ずつ返済し続けています。出産を機に会社を辞め、いまはライターを仕事に。同世代のバリキャリで華やかな子たちと比べると地味な人生ですが、質素な暮らしには慣れているし、ポジティブな母親の影響なのか自分が不幸だとは思わない。でも、結局、人生の幸不幸は"親ガチャ"で決まるの? (30代 ライター 女性Dさん)
【Dさん】会社員時代は周りの上昇志向が高すぎてついていけなかった。いまは子育ての合間にフリーライターの仕事をしていて、収入は減ったけれど、自分らしく生きられるようになった気がする。でも、やっぱり"親ガチャ"ってあるのかな?
【AI】「親ガチャ」というのは、親の学歴や経済状況、養育環境などによって子どもの人生が大きく左右されるから、生まれるまで当たりか外れかわからないという意味の言葉じゃ。キミはどっちだと思っているのかね?
【Dさん】母子家庭で貧乏だったという意味では「外れ」かもしれないけど、ポジティブな母親の子どもでよかったという意味では「当たり」かも......?
【AI】それは正しく言うと"遺伝ガチャ"の当たりじゃな。誰しも親から家庭環境だけでなく、遺伝子も受け継いでいる。知性、能力、性格、そして運まで、人は遺伝の影響から逃れられないことが行動遺伝学で明らかになっておる。
【Dさん】え? 能力が遺伝することは聞いたことがあるけど、知性や性格、運まで遺伝するなんて知らなかった!
思春期をすぎると「親の努力」は無駄になる
【AI】そうじゃ。早期教育や英才教育はたいして意味がない。幼児期は遺伝より環境の影響のほうが大きいから、親の努力が結果に結びつきやすい。しかし、思春期を過ぎると、本来の遺伝的な資質で才能が決まっていくから、親の努力はほとんど関係なくなるんじゃ。
【Dさん】へえ、私はてっきり習い事や塾に通っていた人ほど、能力が高くなって成功するんだろうと思ってた。
【AI】早期教育の効果が期待できるのは早期だけじゃ。「十で神童 十五で天才 二十過ぎればただの人」はよくある話で、その逆もある。子どもの頃は落ちこぼれでも、大人になってから偉業を成し遂げるケースはめずらしくない。
【Dさん】そういえば、私の同級生にもそういう人いるなあ。
自分が幸福ならそれが最強
【AI】キミの場合、母子家庭ではあってもポジティブな母親の遺伝子を受け継いだおかげで、幸福度が高くなったんじゃろう。
【Dさん】幸せのハードルが低いんですよね。美味しいものを食べるたびに「幸せ!」と思うし、本や映画や音楽に感動するたびに「生きててよかった!」と思うから。
【AI】いいことじゃ。しかし、目の前の幸福(楽しみ)と将来の幸福(富や成功)の両立は難しい。成功とは多くの場合、短期的な快楽を我慢して自己投資したり、実績をつくったりして、長期的な利益を最大化することだから。優れた人に刺激を受けながらつき合ったほうが、成功はしやすいぞ。
【Dさん】私の場合、成功したいというより、生活を楽しみたいって感じかな。もちろん、それだけ収入も必要だけど、家族との時間を大事にしたいから。
【AI】自分が幸福ならそれが最強じゃ。他人がとやかくいう筋合いはないから、そのまま楽しく生きていくのが一番じゃ。
[解説]親ガチャの正体は家庭環境より「遺伝」
「親ガチャ」は、どんな家庭に生まれたかで人生が左右されることで、どちらかというと悪い意味で使われるケースが多い。さらに子どもは、親から家庭環境だけでなく、遺伝子も受け継いでいる。
行動遺伝学では、人の知能、性格、運にいたるまで「遺伝」の影響の大きさが明らかになっているため、親ガチャは「遺伝ガチャ」でもあると言える。
環境や遺伝が、人生の幸福度にどう影響するのか知るためには、幸福を定義する必要がある。しかし、幸福の定義は千差万別で、哲学、心理学、宗教学などの膨大な議論もあり結論はない。そこで、ここでは、脳科学・遺伝学のエビデンスにもとづく有力な2つの説で幸福を定義しよう。
①幸福度はひとりひとり異なり、ほとんど遺伝と幼少期の環境で決まっている。
②よいことがあれば短期的に幸福度は上がり、悲しいことがあれば幸福度は下がるが、長期的には生まれもった幸福度に収斂(しゅうれん)していく。
これは、「親ガチャによって幸福度が高い人と低い人がいる」ということで、幸福度の基本的な水準は大人になってからもほとんど変わらないと言える。
「悲観的」「楽観的」は遺伝する
水が半分入っているコップを見て「半分しかない」と思う人は悲観的で幸福度が低く、それに比べると「まだ半分も水がある」と思える人は楽観的で幸福度が高い。
自分がどちら寄りかは遺伝でおおよそ決まっている。
とはいえ、幸福とは相対的なものだから、他人と自分の境遇を比較して、喜んだりガッカリしたりしているに過ぎない。これは脳が上方比較を「損失」、下方比較を「報酬」と見なすようにできているからだ。
ただし、ここには大きな皮肉がある。自分より劣った者とばかり接して自分より優れた者を避けていると、長期的には幸福から遠ざかっていく。なぜなら、同類性(ホモフィリー)によって、キミは「親しい友だち5人の平均」になるから。
自分のレベルが5だとして、レベル3の友だちばかりとつき合えば、そのなかでは優位に立てるだろうが、キミのレベルもいずれ3に下がってしまう。
それに対して、自分よりレベルの高い相手と友だちになれば、切磋琢磨してみんなのレベルが上がっていくだろう。
自分の人生を受け入れられるか
人の脳は多くの情報を処理できないため、幸福感の良し悪しは、会社や学校、ママ友などの半径10メートル以内の人間関係のなかで判断するしかない。
今はネットの影響で、必要以上に他人と自分を比較してしまいがちな社会だから、生まれもった幸福度がより重要になっていくかもしれない。
高い能力をもっていて社会的・経済的にも成功しているのに、自分のことを不幸だと思っている人はたくさんいる。
その一方で、貧乏でかつかつの暮らしをしながら、ささやかな趣味を楽しんでストレスのない毎日を送っている人もいる。これは理不尽に思えるが、人生というのはそういうものなのだ。
性格の遺伝率は「50%」
人のパーソナリティ(性格)は、「外向的/内向的」「楽観的/悲観的」「協調性(同調性+共感力)」「堅実性(自制力)」「経験への開放性(好奇心、チャレンジ精神)」のビッグファイブと呼ばれる5つの要素の組み合わせによってできている。
この5つはより分かりやすく8つの要素に分解できる。具体的には、はじめての相手と出会ったとき、誰もが無意識に次の8つを気にする、というように。
①明るいか、暗いか(外向的/内向的)
②精神的に安定しているか、神経質か(楽観的/悲観的)
③みんなといっしょにやっていけるか、自分勝手か(同調性)
④相手に共感できるか、冷淡か(共感力)
⑤信頼できるか、あてにならないか(堅実性)
⑥おもしろいか、つまらないか(経験への開放性)
⑦賢いか、そうでないか(知能)
⑧魅力的か、そうでないか(外見)
性格の遺伝率はおよそ50%、残りは主に環境要因(親の子育てよりも友だち関係などの非共有環境)によって形成される。さらに、「環境も遺伝する」と言ったら驚くと思うが、これもまた行動遺伝学で解明されている。
遺伝と環境はまったく異なる要因ではなく、遺伝的な特性によって、無意識のうちに自分に合った環境を選び、構築しているのだ。だから自分と似ている人といると楽しいし、関係も長続きしやすい。
3つの「資本」のうち2つがあれば幸せに生きられる
もしも、自分の人生は幸福だと思えるなら、それは良い意味で親ガチャ(遺伝ガチャ)の影響があるが、逆に幸福度が低くても絶望する必要はない。
幸福には客観的な基準がないのだから、人生の土台(人的資本・金融資本・社会資本)がある程度そろうことを目指し、それが達成できたなら、自分は「幸福」だと思えばいいのだ。
3つの「資本」の土台があれば間違いなく「幸福」だと言えるし、2つだけでも幸せに生きている人はたくさんいる。3つの資本をどう組み合わせるかは自分次第だ。
〈幸福な人生設計の法則〉
幸福度に遺伝の影響はあるが客観的基準はない。 3つの「人生の資本」のうち2つあれば幸せに生きられる。
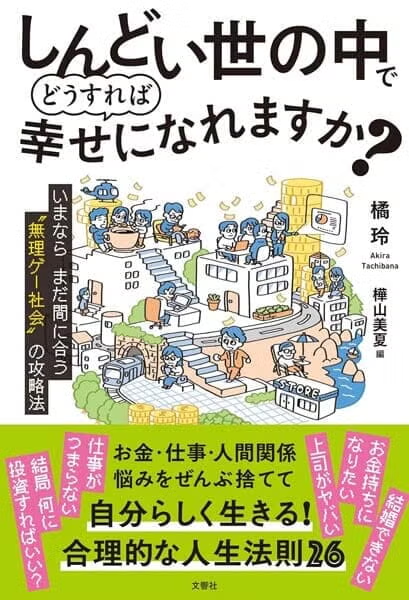 橘玲、樺山美夏『しんどい世の中でどうすれば幸せになれますか?』(文響社)(※画像をクリックするとアマゾンに飛びます)
橘玲、樺山美夏『しんどい世の中でどうすれば幸せになれますか?』(文響社)(※画像をクリックするとアマゾンに飛びます)

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。



