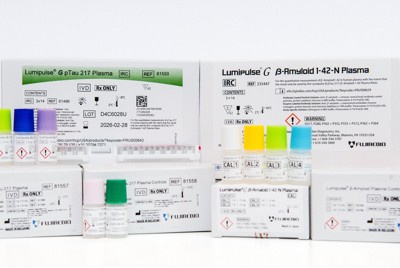古代のワインは天日干ししたレーズンを自然発酵させて造られていたかもしれない――。そんな研究結果を京都大の研究チームが明らかにした。
一般的に、ワインはブドウ果汁にワイン酵母を加え発酵させて造られる。一方、紀元前にはブドウの皮などを自然発酵させワインを造っていたと考えられているが、ブドウの皮にはワイン酵母がほとんど存在せず、その由来は謎に包まれている。
京都大大学院農学研究科の橋本渉教授らの研究チームはまず、市販のレーズンにワイン酵母が多く存在することを確認。アルコールを生み出す能力もブドウに存在するワイン酵母より高かった。そこで、レーズンを水に浸して25度の環境下に置いたところ、3日目ごろから発泡が見られ、14日目にはアルコールの一種のエタノール濃度が8%に達したという。
次に、乾燥機▽天日干し▽両者を組み合わせた半天日干し――の3種類の乾燥方法で生食用のブドウからレーズンを作り、それぞれ三つの瓶に分けて水に浸し、発酵が進むか実験した。
すると、乾燥機や半天日干しのレーズン水では発泡しなかった瓶もあったが、天日干ししたレーズン水では三つ全てで発泡。天日干しする前にはなかった種類のワイン酵母も検出され、エタノールの量も乾燥機を使ったレーズン水と比べて20倍以上だった。

市販の酒には及ばないものの、研究チームの大学院生、日尾守さんは「飲めるクオリティーのものもあった」と話す。今後は、ブドウを天日干しする過程でワイン酵母が定着する要因などの解明を進めたいとし、「複数の酵母や使われていなかった酵母を使うことで、これまでになかった風味のワインができるのでは」と意気込む。橋本教授も「エタノールができれば、規格外品を使ってバイオ燃料も作れるのではないか。フードロス対策にもつなげたい」と期待している。
研究成果は25日、英科学誌の電子版に掲載された。【中村園子】
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。