
「あの人に、あの時の思いを伝えておきたい。でも、どうすれば……」
初恋の相手や元恋人など過去に思いを寄せた人に、あの時の思いを伝えておけばよかった、とモヤモヤを抱えている人も少なくないのではないだろうか。そんな気持ちに区切りを付けてもらおうと、後押しする活動をしている人がいる。本人に代わって手紙を書く「ラブレター代筆屋」の看板を掲げる小林慎太郎さん(47)だ。これまで12年続けてきて、その依頼内容も、コロナ禍を経て、変化しているという。どう変わったのか――。
小4の時にもらったラブレターが原点
小林さんには、こんな原体験がある。
小学4年の時、学校のげた箱にノートの端切れのような小さな紙が置いてあった。開いてみると、「好き」の2文字が書かれていた。
送り主は同級生の女の子。自分も思いを寄せていた相手だっただけに「ものすごくうれしかった」。
女の子はやがて転校し、離れ離れになってしまったが、この時の良き思い出が、後に副業のヒントを与えてくれることになる。
小林さんはプライベートでは10通ほどのラブレターを書いた経験がある。「外向的な子ではなかったので、思いを伝える手段はいつも手紙でした。人より経験値は多いのではないでしょうか」

代筆屋を思いついたのは30代半ば。東京都内のIT企業に勤め、仕事も家庭生活も順調だったが「誰かに対して『心から役に立てている』と実感できるような仕事をしたい」という思いを強くしていた。そこで思い立ったのがラブレターの代筆だった。
2014年の春、東京・新宿などの繁華街でチラシを配ったり、ホームページを開設したりするなどしてPRし、顧客の獲得に奔走した。
最初に舞い込んだ依頼は、仲たがいした知人に許しを求める手紙だった。病気のため、うまく字が書けないから、と文字通り“代筆”するだけの仕事だった。
だが、依頼主の人生に関わることだと、この仕事の意義と責任を痛感した。
清書と投函は依頼主の手で
ホームページの申し込みフォームから依頼を受け、手紙の文案を作成してデータで“納品”する。実際の清書と投函(とうかん)は依頼主の手で自ら行ってもらうことにしている。「やっぱり文字は、その人固有のものですから」
これまで300通以上の手紙を書いてきた。
依頼主に代わって思いの丈を込めた文章を書くため、事前の打ち合わせは基本的に対面で行い、手紙を出す意図だけではなく、依頼主の人となりや、送り先との関係性も丁寧に聞き取る。
依頼主が口にする主語が「わたし」なのか「オレ」なのか、日ごろの言葉遣いや表現の特徴など、細かな点にも気を配る。

料金は1件1万円。月に2件ほどの依頼がある。
依頼主は男性が6割、女性が4割。年代別では30代が最も多く4割を占めるが、10代から80代までと幅広い。
内容は恋愛に絡むものが多いが、家族への感謝や、友人への謝罪・おわび、自分を褒める手紙を書いてほしいとの依頼もあった。
依頼の理由としては、あふれる思いを自分ではまとめきれないからだったり、複雑な事情を整理して説明したいという希望だったりと、さまざまだ。
多くの依頼主に共通するのは「伝えていいのだろうか」と悩んでいることだという。
交際中の相手へのプロポーズであれば、成功率は「ほぼ100%」というが、依頼主の思いが必ずしも相手に届いて成就するとも限らない。
それでも、手紙を送ることで自分の気持ちが整理され、胸のつかえが取れると感じる人が多いといい、小林さんは「ぜひ思いを伝えてほしい」と呼びかける。
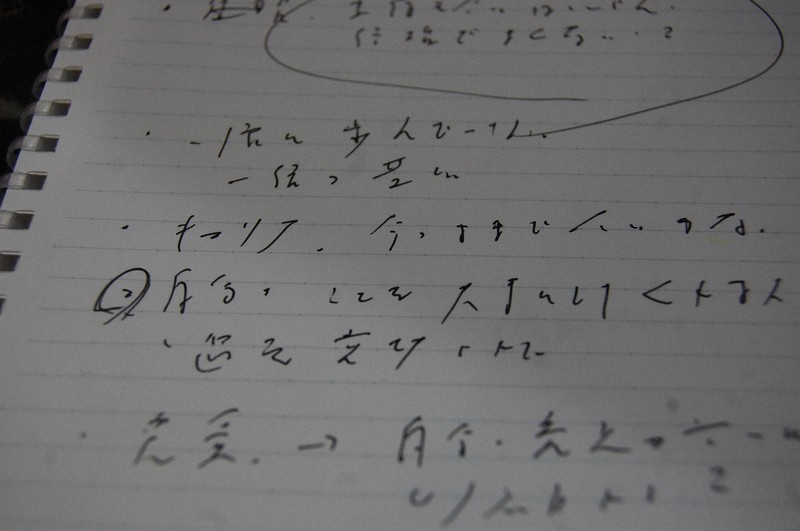
いつまでもいると思っていた人が…
以前は、「告白をしたい」といった依頼が主流だったが、コロナ禍を経て、ここ数年は、初恋の人や昔の恋人あてに、伝えそびれていた感謝や謝罪の気持ちを届けたいという依頼が増えているという。
「コロナ禍で、いつまでも当たり前にいると思っていた人が、突然いなくなるという経験を多くの人がしたことが影響しているのではないかと感じています」
瞬時にメッセージが相手に届くSNSの時代に、文案を練って、清書して、投函し、来るかどうかもわからない返事を待つ手紙の何が魅力なのか。
「過去に区切りを付けて前に進むために、手紙を書きたいという人もいました。手紙にはそんな効果もあると思います。代筆屋の役割は、そんな伝えたいと思う人の背中を押すことです」
手紙をしたためる時間は、相手を思い、自分を見つめ直す時間でもあるようだ。【山崎明子】
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。



